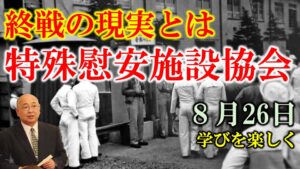ナイジェリア発の誤報から端を発した「アフリカホームタウン」問題。外務省の対応不足や移民リスクを坂東忠信先生と共に検証し、日本の国際的信頼と国防の危機を論じました。
はじめに|国際的誤報と日本の大失態
今回のyoutube倭塾では、坂東忠信先生を迎え、アフリカ諸国との「ホームタウン」問題について語りました。事の発端はナイジェリア政府の誤ったプレスリリースであり、現地メディアやBBCまでが「日本が特別ビザを発給する」と報じ、日本の自治体が大混乱に陥りました。市役所には問い合わせが殺到し業務に支障をきたす事態となりました。外務省やJICAは「誤報」と釈明しましたが、言葉選びや情報管理の甘さが国際的信用失墜を招いたのです。
坂東忠信先生が語る移民リスク
坂東先生は元警察官としての経験から、移民政策の実態を厳しく批判しました。
「短期滞在」「インターン」と説明されても、実際には1年を超えれば国連定義上「移民」となります。
さらに、滞在中に結婚や出産があれば「帰れない理由」となり、事実上の永住化に直結します。
また、こうした制度の背後には「受け入れ施設や企業への補助金」という利権構造が存在することを指摘しました。恩恵を受けるのは一部の企業幹部であり、地域社会や市民には何の利益ももたらされません。坂東先生は「人権」を隠れ蓑にしたわがままの横行、日本のメディア不信、外務省の言葉選びの稚拙さを痛烈に批判しました。
言葉の重みと国際感覚の欠如
問題を深刻化させた一因は「ホームタウン」という呼称です。日本では「馴染んだ町」という軽いニュアンスで使われますが、英語圏では「安住の地」「自分の家」を意味し、国の一部を譲渡するかのように受け取られかねません。外務省は「姉妹都市的な交流」と説明しましたが、国際社会には通用しない自己解釈でした。結果として「日本は移民を受け入れる」と誤解され、国際的な信頼を損ねたのです。
坂東先生は「これは自業自得だ。外交感覚が稚拙すぎる」と断じ、日本の役人たちが「ネクタイ姿の外国人」としか付き合わない現実を鋭く指摘しました。実際の外国人コミュニティの実態を知らぬまま政策を決めていることこそ、大きな問題だと語りました。
「日月神示」と時代の兆し
今回の対談では、坂東先生が新著『日月神示の大峠2044』に込めた思いにも触れました。警察官時代の不思議な体験や現場での死生観が、後に「神示」を学ぶきっかけとなったと語ります。執筆中は、まるで“何かに書かされている”ような没入状態に入り、時が経つのも忘れるほどだったと述懐しました。
『日月神示』は、未来に向けた人類への警告と導きを示すものです。坂東先生は、これから人類が迎えるのは「一瞬で滅ぶ終末」ではなく、「徐々に苦しくなりながらも人々の心が試される峠の時代」だと強調しました。
そして「制度や法律だけでは人は守れない。信仰や精神の次元で人間がどう磨かれるかが問われる」との見解を示しました。
スパイ防止法の必要性
また、坂東先生は「スパイ防止法」の必要性についても改めて強調しました。元公安の経験を踏まえ、日本が「スパイ天国」と揶揄される現状を放置すれば、移民問題や外交問題と結びついて更なる混乱を招くと警鐘を鳴らしました。
「スパイ防止法を作るだけでは機能しない。大切なのは国民がスパイの実態を理解し、通報や監視の目を社会全体で持つことだ」と説きました。つまり、法律と同時に「国民の意識」を育てることが不可欠だというのです。これは「移民問題」への対応と根を同じくしており、坂東先生は「意識なき制度は形骸化する」と警告しました。
日本人の意識と国の未来
坂東先生は「制度を作るのは国会議員だが、意識を作るのは国民だ」と繰り返しました。参政党がスパイ防止法を提案したことで、他党も無視できなくなった事実を挙げ、これは「国民の意識が政治を動かす」一例だと説明しました。
今回の「ホームタウン」問題も、誤報や誤解で片付けられるものではなく、国民一人ひとりが「移民リスク」「言葉の重み」「外交の現実」に敏感になることが、日本の国防と文化を守る第一歩だと結論づけました。
結び|誤報を超えて真実を見る目を
「アフリカホームタウン」問題は、一つの誤報に端を発した混乱でした。しかし根本には、日本の言葉選びの軽さ、移民リスクへの無理解、そして利権優先の政治構造があります。
さらに、坂東先生が語った「日月神示」の示す未来像、そして「スパイ防止法」の必要性は、単なる制度論を超えた精神的・意識的課題であることを教えてくれます。
私たちが学ぶべきは、誤報に踊らされない眼と、自分の国を守る意識。そして、制度だけに頼らず心を磨く覚悟です。坂東先生の怒りと提言は、日本がこれ以上「自虐」と「失態」を重ねないための真摯な警告であり、国民に向けた強い呼びかけでした。
【所感】
今回の問題で改めて感じたことは、制度や外交の稚拙さだけが問題なのではなく、言葉の重みをどう理解するか、そして国民がどのような意識を持つかが問われているということです。
「ホームタウン」という一語の軽さが、国際社会では国家の根幹を揺るがす誤解を招きました。また、制度を作るのは国会議員ですが、その制度を生かすも殺すも国民の意識次第です。
外から押しつけられた制度に頼るだけでは問題は解決しません。
本当に必要なことは、私たち自身が意識を高め、響き合う社会をつくっていくことにあると思います。