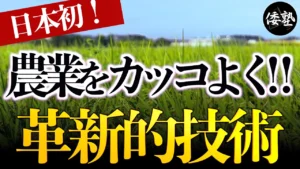臓器移植の有効性と生存率の高さに対し、日本では制度や利権により普及が進んでいません。免許更新時の「一言の声かけ」でドナー数を5倍にできる現実、そして透析偏重の医療体制の背景を問います。
◉ 臓器移植の「圧倒的な有効性」と現状の問題点
動画冒頭では、心臓や肝臓などの臓器移植が、他の治療法と比べて圧倒的に高い生存率と生活の質(QOL)をもたらすことが明確に示されました。たとえば心臓移植では5年生存率が90%に達し、人工心臓や薬物療法を大きく上回ります。腎臓に至っては5年生存率95%、10年でも85%と、透析に比べて格段に高い成果を挙げているのです。
しかし現在の日本では、臓器移植がごく一部にとどまり、代替治療としての透析が主流になっている現状があります。その理由として、移植施設や専門医・コーディネーターの不足、そして啓発活動の低予算(5億円)という構造的な課題が指摘されました。透析には年間500億円の補助金が投じられているのに対し、臓器移植全体にはわずか20億円程度の支援しかありません。
◉ 警察の「ひと言」がドナー数を5倍にする
移植医療の推進において注目すべきは、「運転免許証の裏面」にある臓器提供の意思表示欄です。現在、日本人の意思表示率はわずか19%。ところが、米国のように免許更新時に「意思表示をお願いします」と一言添えるだけで、この割合は一気に100%近くにまで跳ね上がることが実証されています。
つまり、法律改正も不要で、単に窓口職員がひと声かけるだけで、ドナー候補者は5倍に増えるというのです。これは臓器のブラックマーケットを減らすことにもつながり、正規ルートでの移植が広がれば、患者の命を救うだけでなく、犯罪抑止にもなるという重要な視点が語られました。
ところが、厚生労働省が警察庁に一通のお願い文書を出すだけのことが、なぜか行われていない。この“何もしないこと”に対して、出演者は利権や天下りなどの思惑が背後にあるのではないかと疑問を呈しています。
◉ なぜ透析が優遇されるのか? 利権構造と医療体制の歪み
移植推進が進まない背景には、医療経済の構造的な問題も存在します。透析には年間600万円もの費用がかかりますが、病院にとっては安定した長期収入源となり得るのです。一方、移植は初年度に3000万円のコストがかかる一方で、その後の収益は大幅に減少します。つまり、移植が進めば病院経営にとっては“損”になるという矛盾があるのです。
加えて、日本国内には透析施設が4400ヵ所あるのに対し、移植ができる病院はわずか50ヵ所、移植医は300人、コーディネーターは80人しかいません。スペインでは全病院に1人、アメリカでは1500人のコーディネーターがいるという現実との大きな差に愕然とさせられます。
この医療体制の偏重は、国民全体の社会保障費にも影響を及ぼしています。日本の医療保険全体の8.7%が透析に費やされており、もし移植へと切り替われば、年間最大1兆200億円もの削減が理論的には可能だと指摘されました。
◉ 国民が声を上げる時 〜倫理と制度改革の必要性〜
ここまで明らかになった数々の問題に対して、動画では「神に任せるな、国民が声を上げよう」と強く呼びかけています。臓器移植をめぐる制度改革は単なる医療の話にとどまらず、命を救い、医療費を抑制し、犯罪を防ぐ、まさに“社会全体の倫理”に関わる問題です。
出演者は、移植ドナーへのインセンティブ(例:上限30万円の葬祭費援助)なども提案し、家族の同意を得やすくするための工夫についても言及しました。さらに、行方不明の子供が近年増加しているという統計にも触れ、ブラックマーケットや臓器売買との関連性に懸念を示しつつ、国家の安全保障にもつながる重要な課題であることを訴えています。
*
臓器移植というテーマを通して、日本社会の制度・倫理・経済のゆがみを浮き彫りにした本動画。誰にとっても決して他人事ではないこの問題について、あなたもぜひ一緒に考えてみませんか?