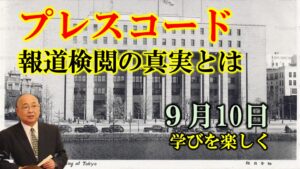党員構造と企業票が政策を歪める実相、若年層の就業観の変化が招く移民依存、独裁国家の後継不在、そして日月神示の「食料難―分岐―富士」を踏まえ、備えと希望の道筋を示しました。
Ⅰ 総裁選の熱気と「見えない空白」──企業票・幽霊党員・政策遅延の連鎖
総裁選の日程が走り出すと、永田町は一斉に選挙モードへと傾きます。
会合の場では、重要案件の相談中であっても幹部からの呼び出し一つで空気が変わり、目の前の課題よりも「配分」「根回し」へと意識が流れがちです。こうした体質を支えるのが、企業ぐるみの党員確保と投票取りまとめに根差した構造です。
いわゆる幽霊党員が数字として積み上がり、社長や組織の意向が何百票単位で動く現実が、政策論より「数の論理」を優先させます。
保守系候補への期待は確かに高まっていますが、移民・労働政策をめぐっては企業側の利害が強固です。
仮に保守色の強いリーダーが誕生しても、企業票の剥落が党勢を直撃するという“逆風”が同時に発生します。
結果として、理念と実務の間に大きな摩擦が生まれ、肝心の制度改めは「先送り」に陥りやすくなります。
一方、国内の人材環境にも根深い課題があります。
大卒比率の上昇と学費負担の重さが、若年層の就業選択を狭め、地域の一次・二次産業や現場職から距離を生じさせています。
「誇りある現場」を社会が再定義し、教育と職業の接続を現実的に組み直さない限り、企業は人手を海外に求め、制度は移民依存へと傾きます。
ここで問われるのは、単なる受入れ数量の議論ではなく、「作法」「規律」「同化の設計」を含む国家の意思です。
規範なき受入れは、将来の対立を内包します。
だからこそ、地域共同体の再生、技能の継承、若者の挑戦を支える仕組みづくりを、選挙の喧噪に紛れさせず進める必要があります。
Ⅱ 独裁国家の演出と後継不在──中露朝の「歳」と「継承」を読む
国際情勢では、演出と象徴が重い意味を帯びます。
中国の軍事パレードに見られる高度な行進の練度は、実戦能力と同一ではないにせよ、「統制の美学」を国内外に示す政治的サインです。
さらに注目すべきは、首脳たちの年齢と後継問題です。
両大国のトップはともに高齢域にあり、北朝鮮は“後継の兆し”を意図的に見せます。
並び歩く三者の雑談を拾った“ホットマイク”報道は、寿命観やバイオ技術への言及を通じて、暗に「権力の持続」を誇示する側面も感じさせました。
こうした場では、言外の圧力や比喩が外交言語になります。
過去には、贈り物や写真の構図までもが「含意」を帯び、相手の面子や神経を巧妙に刺激してきました。
今回も、若い後継を“視覚的に提示”する北朝鮮に対し、老練な二強が年齢談義を交わす構図は、静かな牽制として映ります。
問題は、三者いずれも「明確な継承の設計図」を外に示し切れていないことです。
もし同時期に権力移行が重なれば、各国内の権力闘争は対外強硬姿勢として噴き出しやすく、国際秩序は不安定化します。
この地政学的リスクに、日本の政治空白が重なる最悪のタイミングを避けるには、国内の意思決定を「選挙ロジック」から引きはがし、安定的な危機管理ラインを確保することが欠かせません。
エネルギー・食料・通信・物流・防災のバックアップ体制、同盟・近隣外交の即応性、そして有事における在留外国人・難民対応の具体的プロトコルを、平時から磨いておくことが求められます。
Ⅲ 日月神示が指し示す峠──「食料難―分岐―富士」の先にある希望と設計
対談の後半では、日月神示に記された時間軸を仮説として読み解き、現実の事象と照合しました。
鍵は三段階、「食料難」「分岐」「富士」です。
まず世界的な供給網のひずみや異常気象等によって、食料の逼迫が段階的に強まる可能性があります。
次に、社会のマナー・規範・信義が試され、人々の生き方が「神(かみ)の道」と「獣(けもの)の道」に分かれる分岐点が訪れます。
当初は区別が曖昧でも、やがて振る舞いの差が明確になります。
さらに象徴的な出来事――富士の動き――が、国民心理に大きな動揺を与える局面が示唆されています。
ここで大切なのは、恐怖に呑まれず、準備と秩序を粛々と積み上げることです。
具体的には、
① 備蓄:水・主食・常温たんぱく・医薬・衛生のローリングストック、
② 分散:住まい・拠点・通信の冗長化、
③ 共助:自治会・町内・学校・企業の横連携、
④ 作法:配給・避難・医療・治安の現場手順を地域言語で共有、
⑤ 作庭:心を整える祈り・学び・芸能(能・詩歌等)を日常に戻し、動揺を鎮める文化の場を持つことです。
「分岐」の局面では、言葉と行為の一貫性が問われます。
利便性のために規範を売り渡す選択は短期的には楽でも、長期には共同体の信頼を損ねます。
逆に、時間をかけてでも信義を通す振る舞いは、周囲の心を落ち着かせ、秩序を保ちます。
ここで役立つのが日本の「しらす」の知恵です。
上意で縛るのではなく、事実を広く「知らし」、皆で合意し、役割を分担して粛々と実行する。
江戸の町が火事や飢饉を何度もくぐり抜けられた底力は、この作法に支えられてきました。
富士をめぐる象徴的事態が起きたとしても、そこが“終わり”ではなく“始まり”だと読み解く視点が重要です。
峠を越える道筋は、すでに文化の記憶の中に刻まれています。
清明なる礼節、互助の働き、そして「学びを楽しく」という心の灯りが、暗がりを照らします。
行政の支援を待つだけでなく、地域の小さな手当てを積み重ねることが、最終的に最大の安心へとつながります。
政治にできることは多くありますが、すべてを政治任せにはできません。
家庭での備え、職場での訓練、地域での顔の見えるつながり、学校での実地の学び――どれも今日から始められます。
移民受入れの是非を語る前に、まず日本側の作法を整え、共に暮らすための規範と責務を明文化し、機能させることが肝要です。
結びに、希望について。
峠は試練であり、同時に選択の機会です。
声高な対立や恐怖で心を乱すより、静かに準備し、淡々と務めを果たす。
その積み重ねが、次世代の安心と誇りを支えます。
歴史は、人が作法を保ち続けた所から再び立ち上がってきました。
今回も同じです。学びを楽しく、心を正しく、手を携えて前へ進みましょう。
【所感】
今回のお話は、どうしても重たい内容になりました。
政界の裏側、移民依存の実態、そして世界の大国が抱える不安定さ。
さらに日月神示が示す「峠」の厳しさを重ね合わせると、先行きに心が沈む方も多いかもしれません。
けれど大切なことは、「影を見た上で、その先に光を見出す」ことだと思います。
苦難の時代が訪れようとも、日本には必ず立ち直る力が備わっています。
歴史を通して、幾度も大きな困難を越えてきたのもまた事実です。
だからこそ、
知ることを恐れず、
正しく見つめ、
希望を持って備えていきたい。
日々の学びと実践の中にこそ、未来を照らす光があるのです。