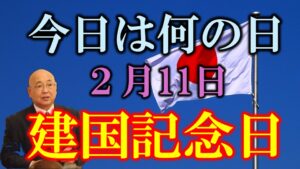日本のバレンタインデーは、昭和33年にメリーチョコレートが「女性から男性へ愛を伝える日」として売り出したことが始まり。その発端は昭和11年のモロゾフの広告にありました。なぜ日本だけが独自の形をとったのか、その理由を解説します。
バレンタインデーのルーツと「ブラジャーの日」
2月12日は、「ブラジャーの日」でもあります。1914年、大正2年のこの日、アメリカのメアリー・フェルプス・ジェイコブがハンカチをリボンで結んだ簡単なブラジャーを考案し、特許を申請しました。それまでの女性の下着といえばコルセットが主流でしたが、この発明によって女性の衣服の在り方が大きく変わったのです。女性の歴史においても重要な出来事でしたが、今回はもう一つの話題、バレンタインデーについて深掘りしていきます。
バレンタインデーといえば、毎年2月14日。日本では「女性が男性にチョコレートを贈る日」として知られていますが、実はこの習慣は日本独自のものです。そもそもバレンタインデーとは、キリスト教圏では家族や恋人にプレゼントを贈る日でした。ところが、日本では「女性が男性にチョコレートを贈る」という独自の形で定着しました。この文化の起源をたどると、昭和11年の神戸のモロゾフ製菓(現・モロゾフ)の広告にたどり着きます。
バレンタインデーを仕掛けたのは神戸のモロゾフ
1936年(昭和11年)2月12日、神戸のモロゾフ製菓が外国人向けの英字新聞『ザ・ジャパン・アドバタイザー』に「あなたのバレンタイン(=愛しい方)にチョコレートを贈りましょう」という広告を掲載しました。この広告が、日本でのバレンタインデーの最初の試みでした。
しかし、この時点では、日本の文化に根付くことはありませんでした。そもそも日本では、男性が女性にプレゼントを贈るという習慣がほとんどなく、「愛しい人に贈り物をする」という欧米のバレンタイン文化が、なかなか日本社会にフィットしなかったのです。
その後、1958年(昭和33年)に、東京・新宿の伊勢丹百貨店でメリーチョコレートが「バレンタインチョコ」を販売しました。実は、この時点でもチョコレートは「男女どちらからでも贈れるもの」として売り出されました。しかし、この販売戦略も最初はあまりヒットしませんでした。
「女性から男性へ」の文化を作ったのはメリーチョコレート
当時のメリーチョコレートは、2月に売り上げが落ち込むことに頭を悩ませていました。どうすればこの時期にチョコレートが売れるのか。そのヒントとなったのが、昭和11年のモロゾフの広告でした。
そこでメリーチョコレートは、新たな販売戦略を打ち立てます。それが、「女性が男性にチョコレートを贈る日」という形にすることでした。欧米では男性から女性にプレゼントをすることが一般的でしたが、日本ではその逆、「女性から男性へ愛を伝える日」というキャッチコピーを付けたのです。
このアイデアが日本でバズりました。特に「女性から男性に気持ちを伝える」という新しい概念が、多くの女性に支持されました。その結果、バレンタインデーは「女性がチョコレートを贈る日」として定着し、現在の日本独特のバレンタイン文化が生まれたのです。
バレンタイン商戦と現代の形
こうして、日本独自のバレンタイン文化が確立されましたが、さらにこの習慣は商業戦略によって強化されていきました。
バレンタインの定着とともに、チョコレート業界は様々な形のチョコを企画しました。例えば、
・義理チョコ(職場や友人間でのチョコレートの贈与)
・友チョコ(女性同士で交換するチョコ)
・逆チョコ(男性から女性へ贈るチョコ)
これらの文化は、すべて日本独自の発展を遂げたものです。特に義理チョコ文化は、日本の企業社会に根付くようになり、バレンタインデーが単なる恋愛イベントではなくなっていきました。
バレンタイン文化の今後とまとめ
日本のバレンタイン文化は、元々欧米の風習とは異なる形で誕生しました。その背景には、チョコレート会社の販売戦略と、日本の伝統的な価値観が組み合わさった結果がありました。
また、バレンタインデーが持つ「女性から男性へ愛を伝える日」という概念も、時代とともに変化しつつあります。近年では「逆チョコ」や「友チョコ」など、多様な形が登場し、必ずしも男女の恋愛関係に限定されない文化となっています。
こうした変化を踏まえると、バレンタインデーは今後も新たな形に進化していく可能性があります。しかし、その原点にある「人と人が感謝や愛情を表現する日」という意味は、変わらないのではないでしょうか。
このように、バレンタインデーはただの商業イベントではなく、日本独自の文化として定着したものなのです。今後もどのように発展していくのか、注目していきたいところです。