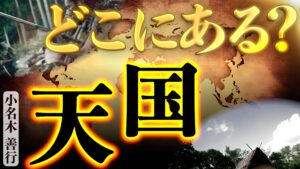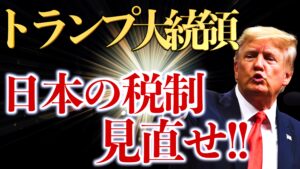2月25日は『頭の体操』で有名な多湖輝先生の誕生日。彼の提唱した「柔軟な思考」は、歴史や社会問題の本質を見抜く鍵となります。固定概念に囚われず、物事を多角的に考える重要性について考察します。
- 2月25日、多湖輝先生の誕生日と『頭の体操』
2月25日は、昭和元年生まれの心理学者、多湖輝先生の誕生日です。彼は『頭の体操』という思考パズル本を1966年に出版し、大ヒットを記録しました。累計1200万部以上を売り上げたこの本は、単なるなぞなぞではなく、「柔軟な思考を育む」ことを目的としていました。
例えば、『頭の体操』には以下のような問題があります。
【問題1】
ある細菌は1分ごとに2倍に増殖し、1時間で瓶いっぱいになる。では、最初の細菌が2個だったら、瓶がいっぱいになるのは何分後か?
答え: 59分後(1分短縮されるだけ)
【問題2】
坂道で荷車を引く人に「後ろの人は息子ですか?」と聞くと「はい」と答えた。しかし、後ろの人に「前の人はお父さんですか?」と聞くと「違います」と答えた。2人の関係は?
答え: 母と息子
このように、一見すると簡単な問題でも、先入観を取り払って考えなければ解けないものが多く含まれています。
多湖先生は「諸悪の根源は個人の頭の固さにある」と語り、固定概念に囚われず、多角的に考えることの重要性を訴えました。これは、単なるパズルの話ではなく、社会全般にも通じる考え方なのです。
- 歴史と情報に対する柔軟な思考
この柔軟な思考は、歴史や情報の捉え方にも重要な役割を果たします。
例えば、「織田信長は本能寺の変で亡くなった」とされますが、遺体は見つかっていません。そのため、「信長は生き延びていた可能性があるのでは?」という視点を持つことも必要です。しかし、多くの人は「信長は本能寺で死んだ」と思い込んでしまい、そこから発展的な議論をしなくなります。
また、現代の情報社会でも、政府やメディアの発信を鵜呑みにしてしまうことで、真実が見えなくなることがあります。例えば、新型ウイルス対策としてマスクやワクチンが推奨されましたが、その結果、斎場が予約できないほど死亡者が増えている現状を見れば、「本当に正しい選択だったのか?」と疑問を持つべきです。
・固定概念を疑うことの重要性
・政府・メディアの発信は常に正しいのか?
・歴史的事実は本当に一つの視点で決めつけられるものか?
・他の視点から見たら、新たな真実が見えてくるのでは?
歴史も現代の問題も、多角的に見ることが大切であり、「これしかない」と考えるのは思考を停止させることになります。
- 日本の現状と思考の転換
現在の日本には、固定概念に囚われたまま改善されない問題が多く存在します。
例えば、日本銀行が発行する紙幣の量は増えているにもかかわらず、市場に出回るお金の総量は横ばいです。これは、日本の資産が国外へ流出している可能性を示唆しています。実際、アメリカのフォートノックスには、日本政府の金も保管されているとされ、すでに使われている可能性すらあるのです。
また、政治に関しても「減税すればいい」という単純な議論だけでなく、財源の見直しや支出削減といった根本的な議論が必要です。しかし、こうした本質的な議論がなされず、感情的な論争に終始している現状は、多湖先生が警鐘を鳴らした「思考の硬直化」の典型例といえます。
・現代日本の問題点
・日本の資産が海外に流出している可能性
・減税・増税議論の単純化と本質的な議論の欠如
・政治家も国民も閉塞感を抱えているが、打破する知恵が生かされていない
これらの問題を解決するには、「頭の体操」の考え方を取り入れ、柔軟な思考を持つことが不可欠です。
まとめ
2月25日は、『頭の体操』の多湖輝先生の誕生日です。彼の提唱した「柔軟な思考」は、歴史や社会問題を正しく理解するために欠かせない視点です。
現代社会では、「政府の言うことが正しい」「歴史はこうだった」といった固定概念に囚われがちですが、本当にそうなのかを疑い、別の視点から考えてみることが重要です。
日本の歴史や政治、経済に関する問題も、既存の枠組みの中で解決策を探すのではなく、「そもそも何が問題なのか?」という根本的な視点を持つことが必要です。
多湖先生の『頭の体操』は単なるパズルではなく、思考を柔軟にするための訓練書でもありました。今こそ、その教えを活かし、閉塞感を打破する思考力を養うべきではないでしょうか。