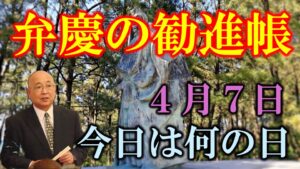修行の拠点・園城寺を焼き討ちされた行尊が、倒れながらも咲く一本の山桜に心を動かされ、再建の決意を固めます。彼の歌に込められた「誰も見ていなくても咲く」信念は、日本人の生き方そのものを映し出しています。
◉ 一本の山桜が教えてくれた「まこと」の姿
春、山中でひっそりと咲く一本の山桜。その姿を詠んだのが、百人一首66番歌の
もろともにあはれと思へ山桜
花よりほかに知る人もなし
この和歌の作者は、前大僧正行尊(ぎょうそん)。
彼は12歳で園城寺に出家し、厳しい修験の道をひたすらに歩みました。園城寺とは霊力を得るための滝行や山修行を行う、実に苛烈な修行寺です。行尊にとって、園城寺は青春のすべてであり、生き方そのものでした。
しかしその園城寺が、行尊が26歳のとき、比叡山延暦寺の僧兵たちによって焼き討ちにされてしまいます。原因は、園城寺が天台宗の中でも日本古来の神道と仏教を融合させようとする姿勢にあり、それを邪道とみなした延暦寺の一部過激僧が暴走したのです。
寺の焼失は、信仰の拠点だけでなく、食糧・衣類までも失う死活問題でした。行尊たち修行僧は黙って托鉢に出ます。そのとき行尊が山中で出会ったのが、風に倒されながらも満開の花を咲かせていた一本の山桜でした。
◉ 折れても咲く──修行僧の生き様と再建の道
倒れてなお咲く山桜。その健気な姿に、行尊は自らの姿を重ねました。
誰に見られることもなく、褒められることもない。それでも、なお咲く。その山桜に、「自分たちもまた、こうでありたい」と深く心を動かされたのです。
そのとき詠まれたもう一つの歌が、
折りふせて 後さへ匂ふ 山桜
あはれ知れらん 人に見せばや
「倒れてもなお香る山桜。誰かにこの気高さを伝えたい」と詠むこの歌には、理不尽を前にしても、暴力に報いるのではなく、淡々と「自分たちの道」を歩もうとする覚悟が込められています。
行尊たちは全国を托鉢し、やがて園城寺を見事に再建。そして行尊は、白河院や待賢門院の病気を癒し、鬼神のような法力をもった高僧として名を馳せます。やがて、大僧正という僧侶の最高位にまで上りつめました。
しかし運命は容赦しません。67歳のとき、園城寺は再び延暦寺の僧兵によって焼き討ちされます。高齢になった行尊は、それでも再び托鉢に出て、もう一度、寺を再建するのです。
◉ 「誰も見ていなくても咲く」それが日本人の心意気
この行尊の姿に、日本人の心意気が見えてきます。
評価されなくても、見てもらえなくても、誰かのためにではなく、自らの「まこと」に従って生き抜く。そこに日本人の美学があるのです。
それはまさに、折れた幹からも花を咲かせる山桜のような生き方です。
「俺たちはな、幹が折れたって立派に咲くんだ。山桜なんかに負けてられっかよ!」
この精神が、理不尽に打ちのめされそうになったとき、人をもう一度奮い立たせてくれるのです。
現代の百人一首の解説では、この歌を「孤独や寂しさの歌」とするものが多いようです。けれど、行尊の背景を知れば、それはもっと力強い“再起の歌”であり、“希望の歌”であることがわかります。
人生には、誰にも言えないような辛さがあります。
でも、そんなときこそ、山桜のように、自分の「まこと」を信じて咲いていく。
この行尊の歌は、現代に生きる私たちにも、大切なメッセージを届けてくれているのです。