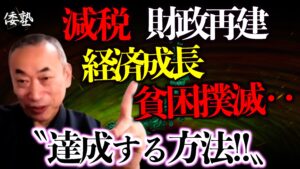家田荘子さんが語る、極妻取材の裏側とAIDS差別への挑戦、そして現在の「歩く駆け込み寺」活動。命を懸けた取材と魂の言葉が紡ぐ、衝撃と感動のノンフィクション対談です。
■ 命懸けのノンフィクション──極妻取材の舞台裏
小柄な若き女性が、ヤクザの抗争真っ只中に突撃取材を決行。家田荘子さんが23歳のとき、ノンフィクション作家としての第一歩を踏み出したのは、「極道の妻たち」のリアルな姿を描きたいという衝動からでした。
つてもなく、信頼もゼロの状態から、半年以上かけて一人の女性に辿りついたという取材経緯は、まさに命がけのドラマそのもの。警察と裏社会の境界すら曖昧な時代、取材現場は火炎瓶が飛び交う戦場さながら。
それでも「男性の背後にいる家族の想いを伝えたい」という女性ならではの視点で、家族の愛、覚悟、苦悩を描き出しました。
出版社とのやりとりもまた壮絶です。「つてはある」と虚勢を張って、命を懸けて書いた原稿。編集長の「事実なら何を書いてもいい」という一言に支えられながらも、「言っていないことは書かない」「語尾まで真実に忠実に」が家田さんの徹底した信条。
嘘を書かない、誰にも媚びない、でも誰かのために伝える──その精神が、次第に業界内で尊敬を集め、読者の心を打つ作品を生んでいきました。
■ 差別と偏見を超えて──AIDS取材と再出発
取材後、心身ともに疲弊し、一時は筆を置こうとまで思いつめた家田さん。そんなとき、元・米軍人の夫とともに渡米し、偶然出会ったのがエイズ患者の人々でした。
日本では「握手や便座でも感染する」といった誤った情報がまかり通り、患者への差別は深刻なものでした。
家田さんはアメリカ赤十字でホームナースの資格を取り、患者に寄り添いながら、真実を記録し続けます。
その行動が評価され、日本に戻ってからノンフィクション大賞を受賞することに。
しかしそれ以上に大きかったのは、「知識によって差別は減らせる」「理解こそが人を救う」という信念を得たことでした。
■ 心に寄り添う「歩く駆け込み寺」へ
取材を続ける中で、「悩みを抱えた女性たちが、話してスッキリ帰れる場所をつくりたい」という願いが芽生えた家田さん。
その想いは「住職資格取得」への挑戦につながり、現在ではミニ駆け込み寺の実現に向けて活動を続けています。
仏門修行だけでなく、吉原で亡くなった遊女たちの月命日供養や、霊山での修験道行など、身体を張って「魂の声」に耳を傾ける日々。
今も「歩くお寺」として多くの人の話を聞き、支え続けています。
家田荘子さんのYouTubeチャンネルでは、こうした魂の取材と人間ドラマの数々が公開中。どの回も、真実と人情がたっぷり詰まっています。