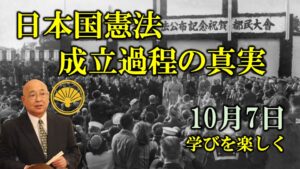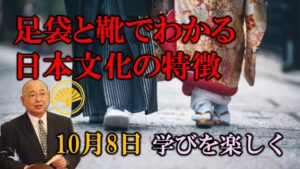【日本は変わる?】高市新総裁でこれからどうなる!|小名木善行
高市新総裁誕生を機に、日本を活かす政治の要件を俯瞰しました。靖国観と連立の行方、解散含みの展望、卑弥呼・推古・持統・北条政子に学ぶ統治の智慧についてお話ししました。
Ⅰ 政局ではなく「国の芯」を見る──高市新総裁誕生の意味
今回のライブでは、高市新総裁の誕生に祝意を申し上げつつ、目先の政局や人物評に偏らない視点を提示しました。
倭塾チャンネルの趣旨は、誰が何を言ったかの追いかけではなく、
日本人として「いま・ここの扉を開く力」を養うことにあります。
そのため、高市新体制の出発点を「日本を活かすのか、党勢維持を優先するのか」という分岐として捉え、政治の根っこにある価値判断を確認していきました。
焦点のひとつは靖国神社への向き合い方です。
戦場へ赴いた方々との「永劫に祀る」という約束は、見えない世界との契約であり、破ってはならないとお伝えしました。
国内外の雑音に流されず、英霊に対する礼をどう貫くかは、主権国家としての矜持を測る試金石になります。
連立関係への影響も想定されますが、そこで原点が揺らぐのか、守り抜くのかが問われます。
もう一つの焦点は国会運営の現実です。
現下の議席構成では、法案や予算の通過に厳しさが伴う可能性があります。
年明け以降の局面によっては、解散総選挙という選択が視野に入るかもしれません。
ここで露わになるのは、「日本を守る」ために政権運営へ協力するのか、それとも利権を守るために内側から妨げるのかという各議員の姿勢です。
情報統制が効かなくなった時代において、内紛は党勢を急速に削ります。
したがって、権力を何のために用いるのかという根本が改めて問われます。
Ⅱ 女性リーダーが変える統治の質──卑弥呼・推古・持統・北条政子
番組では、女性リーダーの登場が日本史の転換点をもたらしてきた事実にも触れました。
卑弥呼が乱れを収めた伝承に象徴されるように、女性的な統治は「命令と支配」よりも「共感と関係性」を軸に組織を動かす力を持ちます。
推古天皇の時代には神仏習合の方向が示され、異なる価値を日本流に包摂する器が形作られました。
持統天皇は教育と文化を国家の柱に据え、古事記・日本書紀の編纂や万葉文化の土壌を整えました。
学びが民度を高め、社会に安心感をもたらすという視点は、現代でも有効だと考えています。
北条政子は「心をつなぐ統治」を体現しました。
承久の乱に際し、人々の心を束ねる言葉が多くの兵を動かした逸話は、形式的権威だけでは人は動かないことを教えてくれます。
恩義と信頼という見えない網が結ばれてこそ、共同体は力を発揮します。
日本の武士道が「力の誇示」ではなく「理非と情理」を重んじる道となった背景には、こうした女性的統治の記憶が息づいています。
高市新総裁のもとでは、政策の是非に加えて「国民が安心して暮らせる社会設計」をどのように組み立てるかが要になることでしょう。
また、女性トップが国家を立て直した海外事例として、イギリスのマーガレット・サッチャー首相を挙げました。
少数与党という厳しい条件下でも、目的と原則を明確にし、骨格改革を断行した歴史は、困難な局面こそ羅針盤が必要だという示唆を与えてくれます。
日本においても、原則・礼・約束を軸に据えた政治運営が、長い視野での信頼を育むと考えます。
Ⅲ これからの数カ月をどう読むか──内外の奔流と「扉を開く力」
今後しばらくは、激流の中を進む航海が続く見通しです。
国会運営、連立の力学、内外の圧力、メディアや世論の風向きなど、複合的な課題が重なります。
荒天は羅針盤の精度を試しますが、羅針盤とは国家観・歴史観・人間観のセットです。
靖国への礼、教育と文化への投資、国柄を守る規範の再確認、そして「日本を活かす」という目的からの逆算。
これらを外さなければ、たとえ遠回りに見えても進むべき航路は見えてきます。
番組では、年末から年明けにかけて緊張が高まる可能性を示しつつ、日本が良い方向へ舵を切るための条件を整理しました。
第一に、政権内部の「何のために」を揃えること。
第二に、国民が情報の断片ではなく原理原則で判断できるよう、歴史的視座を共有すること。
第三に、政策選択を利便だけで測らず、「約束・礼・安心」という日本文明の根で点検することです。
卑弥呼、推古、持統、北条政子が示した「つなぐ力」は、現代政治にも有効です。
倭塾は、過去を賛美したり誰かを断罪したりする場ではありません。
先人の叡智から「いま開くべき扉」を一つずつ見つけ、子どもたちの未来へ橋を架ける学びの場です。
高市新総裁誕生という出来事を、その橋を強くする契機にできるよう、これからも歴史と現実を往復しながら「学びを楽しく」進めていきます。
ご視聴に感謝いたします。
【所感】
今回の高市新総裁誕生をめぐる話題を通して、改めて感じるのは、日本の政治や社会の根底には、古代から受け継がれてきた「心をつなぐ統治」の精神があるということです。
卑弥呼、推古天皇、持統天皇、北条政子――時代を超えて女性がリーダーとなったとき、日本は「力による支配」ではなく、「共感と響き合いによる安定」を選んできました。高市新総裁の登場もまた、その系譜に連なる新しい時代の兆しといえるのかもしれません。
政治の話はとかく対立や批判の言葉に傾きがちですが、本当に大切なのは「どんな未来を子どもたちに手渡したいのか」という一点に尽きると思います。
その意味で今回のライブは、政局を語る場ではなく、古代から現代へと続く「日本のこころ」を見つめ直す時間になったように感じます。
学びを楽しく、そして誇りをもって。
倭塾が掲げる「響き合い」の志を、これからも大切にしていきたいと思います。