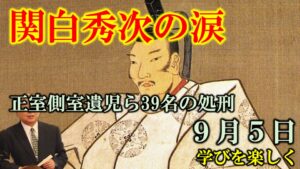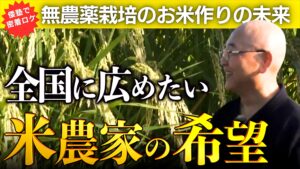大東亜戦争は「勝つため」ではなく、日本人が民族の尊厳を守るための戦いでした。白人列強の差別と挑発、ルーズベルトの戦争準備、降伏すれば待っていた植民地化の現実を掘り下げています。
大東亜戦争は「日本が帝国主義の野望で始めた侵略戦争」と語られることが多いですが、本当の姿はまったく異なります。日本は「勝つため」に戦ったのではなく、「戦わなければ民族が消滅する」という現実に直面し、苦渋の末に戦いを選んだのです。
通常、戦争は相手を屈服させ、外交交渉を有利に進めるために行われます。しかし日本は最初から勝利を見込んでいたわけではありません。なぜなら、その背景には500年にわたって続いてきた白人列強による有色人種支配と差別の構造があったからです。
人種平等提案と列強の反発
1919年、日本はパリ講和会議で「人種平等提案」を世界に突きつけました。これは白人優位の世界秩序を根底から揺るがす提案であり、列強にとっては耐えがたい挑戦でした。
「お前たちの支配は不正だ」と突きつけられたのと同じことであり、以降、日本に対して執拗な圧力と挑発が加えられるようになったのです。ABCD包囲網や経済制裁、外交上の嫌がらせは、その流れの一環でした。
ルーズベルト大統領の戦争準備
アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領は、表向き「戦争はしない」と公約して当選しました。しかし実際には徴兵法を成立させ、軍備を急速に拡張し、イギリスや中国への軍事援助を強化し、事実上の参戦準備を進めていました。
真珠湾攻撃がなければ日米戦争を避けられた、というのは幻想にすぎません。日本がどれほど我慢を重ねても、いずれ衝突は避けられなかったのです。
降伏すれば待っていた「民族の消滅」
「初めから降伏していれば原爆も落ちなかった」という意見もあります。しかしそれは、白人優位の差別的世界観をそのまま受け入れることに等しい選択でした。
もし日本が屈服していれば、アメリカ先住民やインドのように民族は解体され、混血と同化によって日本人も日本語も消滅していた可能性が高いのです。日本列島は白人の支配下に置かれ、文化や伝統は博物館的な展示物程度にしか残らなかったでしょう。
「負けるとわかっていた戦い」に込められた精神
東條英機ら当時の指導者たちは、シミュレーションの結果「アメリカには勝てない」と理解していました。それでも戦う決断をしたのは、勝利以上に大切なものがあったからです。
海軍軍令部総長・永野修身は、「戦わざれば亡国必至。戦って亡国を免れんとすれば、戦わずして亡国に委ねるは民族永遠の亡国であるが、戦って亡国すれば魂は残り、子孫は必ず再起する」と述べました。
たとえ敗れても、戦い抜いた精神は子孫に受け継がれる。その信念こそが、日本人が選んだ道だったのです。
日本が示した可能性と未来への問い
戦争の決断は、帝国主義的な野望ではなく、人類の未来に対する責任から生まれたものでした。白人が有色人種を支配する世界の常識を打ち破り、「人類は共に生きられる」という可能性を初めて行動で示したのが日本だったのです。
もちろん大東亜戦争は悲惨な結果をもたらしました。しかしその精神は、「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」という言葉の通り、未来への道を開く力となりました。
今日、私たちが考えるべきことは、「勝つためではなく守るために戦った日本」の真実をどう受け止め、未来の文明にどう生かしていくかということです。戦争の是非を超え、日本人の覚悟と精神性に触れることが、現代を生きる私たちにとっても大切な指針となるのではないでしょうか。
【所感】
今回の対談の内容は、従来からある一般的な歴史の整理である「大東亜戦争=侵略戦争」という主流の見方とは、まったく異なる視点のものです。
異なる点は、以下の通り。
1.戦争の目的の違い
「勝つための戦争」ではなく、「民族の尊厳を守るための戦い」であったという指摘は、これまでの通説を根本から問い直すものです。東條英機らが「負けるとわかっていても戦うしかなかった」という点は、単なる軍事的判断ではなく、文明史的な意味を持つ決断であったのです。
2.人種平等提案からの流れ
1919年の人種平等提案が、その後の白人列強の態度を決定的に変えたという視点は、歴史の大きな因果を説明する強力な軸といえるものです。そして従来の歴史叙述ではほとんど触れられない部分でもあります。
3.「もし降伏していれば」の現実性
もし戦わなければ、日本民族はアメリカ先住民やインドのように分断・同化・消滅していたかもしれない。この可能性を具体的にイメージすると、「戦わざるを得なかった」という説明が非常にリアルに響くものです。
これらの視点は、先の大戦を「侵略戦争」とする戦後史観とは、真逆の立場に立つものです。その視点を、ここでは単なる「反論」としてではなく、事実や史料に基づいて冷静に提示しています。
歴史は多角的に見ていかなければならないものなのです。
東郷先生をはじめ、私たちが伝えようとしているのは「戦争を正当化すること」ではありません。
「なぜ日本人があの時代にその決断をしたのか」という「文明史的な問い」です。
ここを共有できると、従来の固定観念とは違う“もう一つの真実”が見えてきます。
それは、従来説との「対立」を前提とするものではありません。
多角的な見方による「学び」を提示するものなのです。
歴史の見方は一つではありません。
だからこそ私たち一人ひとりが、通説に縛られず、異なる視点を学び、問い直していくことが大切です。その積み重ねが、未来の文明を支える新しい叡智を育てていくのだと思います。