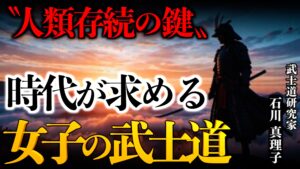戦後体制に縛られた教育現場の実態と、それに抗い立ち上がった現代の寺子屋。
子どもたちの目を輝かせる歴史授業が、感謝と誇りを取り戻す鍵になります。
🌱 学校では学べない「本当の歴史」を伝えたい──田村先生の志
今回ご登場いただいたのは、元小学校教員であり、現在は“現代版の寺子屋”を運営されている田村匡俊先生です。
教育現場で十数年にわたり子どもたちと向き合ってきた田村先生は、現代の学校教育に対し、特に歴史教育の在り方に強い疑問を抱くようになりました。
戦後の価値観に基づいた教科書では、日本の歴史が歪められ、子どもたちが自分の国を好きになることすら難しい。その実情に向き合いながら、「自分が徳川家康だったらどうする?」「西郷さんと大久保さん、どちらを支持する?」といった問いかけによって、子どもたちが“自分の頭で考え、心で感じる”授業を始めたのです。
斎藤雄生先生による、考えさせる歴史授業を手本とし、子どもたちが歴史を「他人ごと」ではなく「自分ごと」として捉えられるよう工夫が凝らされています。
🧭 教育委員会の現実と、戦後体制の壁
田村先生のような授業が、多くの子どもたちの心に火を灯し、「日本ってすごい国だ!」「自分も頑張りたい!」という感想が寄せられる一方で、現実の教育現場はそう簡単ではありません。
ある日韓併合についての授業を行った際、保護者から「娘が傷ついた」とのクレームが入り、教育委員会から指導が入る事態に。
その後、授業担当を外されるという理不尽な経験をされました。
これは単なる個別の問題ではありません。
教育委員会そのものがGHQの公職追放政策から生まれた仕組みであり、「愛国心」や「誇りある歴史観」を持つ教師が排除される構造が全国的に存在しています。
「教育は何のためにあるのか?」という根本を見失ったこの現状を変えるには、まず実践を積み上げていくしかない。
そうした決意のもと、田村先生は自ら寺子屋を開設されました。
🌸 寺子屋から始まる、新しい学びのカタチ
田村先生の寺子屋では、歴史だけでなく、古典『実語教』や『心の教科書』を用いた道徳教育、「いただきます」の意味を学ぶ命の授業など、魂に響くカリキュラムが展開されています。
とりわけ印象的だったのは、実際に通っていた小学生たちの感想文。
「日本人として誇りを持てた」「歴史から人の生き方を学んだ」といった声が、自発的に綴られています。
GHQの洗脳に気づき、未来の日本を守りたいという願いが子どもたちの言葉に込められており、その成熟した表現力に、ただただ感動せざるを得ませんでした。
さらに、田村先生は新たに“学校”の設立を構想中とのこと。
神道・古事記・経済・政治・国際関係など、教科書だけにとらわれない学びを提供し、志あるリーダーを育てる教育の場を目指されています。
給食もオーガニックを基本とし、心身ともに健全な子どもを育てる環境づくりにも並々ならぬ情熱を注いでおられます。
🌟 日本の未来は「感謝」と「誇り」から始まる
かつて1000年続いた「実語教」による寺子屋教育。
それは日本人が大切にしてきた心と魂を育む、世界に誇る教育文化でした。
今の時代だからこそ、こうした“原点回帰”の教育が必要とされていると感じています。
私たちが本当に伝えるべきものは、正しい知識だけではありません。
「ありがとう」と言える心。
「自分は何のために生きているのか」と考える力。
そして、「ご先祖様に恥じない生き方をしたい」という健全な誇りです。
田村先生の実践は、まさに“教育の再起動”です。
この取り組みが全国に広がれば、きっと日本の未来は明るくなる。
そう、心から確信しています。
【感想】
今回の対談を通じて、教育とは“知識の詰め込み”ではなく、“魂に火を灯す”営みなのだと、あらためて強く感じました。
とりわけ印象的だったのは、子どもたち自身が「歴史は自分のことだ」と語り、自らの生き方を見つめ始めていること。
このような教育がもっと広がれば、日本はきっと、志を持った若者たちの手で再び輝くことでしょう。
教育の原点は、家庭と地域、そして私たち一人ひとりの心の中にあります。
田村先生の取り組みは、そのことを思い出させてくれる、かけがえのない希望の灯火でした。
私もまた、この“学びの炎”を、次の世代へと繋いでいきたいと思います。