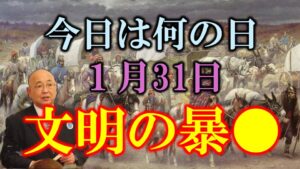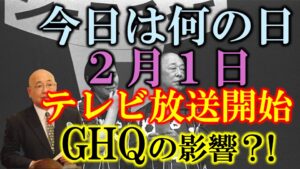精神科医療の実態に迫る本動画では、診断基準の曖昧さや薬物依存の問題を深掘り。
心理療法の専門家が冷遇される一方、精神科医による薬物治療が推奨される仕組みとは?
製薬会社の利権と国家制度の問題を検証します。
- 精神科の診断基準と薬物依存の問題
精神科の診断基準には曖昧な点が多く、誰でも「うつ病」と診断される可能性がある。
特に「DSM-5」や「ICD-10」といった診断基準は、精神科医の主観による部分が大きい。
実際、軽い気分の落ち込みや一時的なストレスでも「うつ病」と診断され、
強い依存性を持つ精神薬が処方されるケースが増加している。
精神科の薬物療法はあくまで「対症療法」であり、
根本的な治療ではなく患者を長期的に依存させる仕組みになっている。
また、副作用として自殺念慮が発生する薬もあり、
精神科を受診した人のうち約3割が最終的に自殺に至っているというデータも存在する。
- 精神科医と心理士の矛盾した制度
日本では、精神科医は心理学の専門知識がなくても開業できるが、
心理療法を専門とする臨床心理士や公認心理師は、国家資格を取得し、
厳しい研修を受けても診断権や治療の主導権を持てないという矛盾がある。
心理士が単独で心理療法を行うと保険適用外となり、
結果として経済的負担の大きい自費診療しか選択肢がない。
一方で、精神科医が薬物療法を行えば保険適用となるため、
経済的な理由で薬漬け治療が優先される現実がある。
さらに、精神科医の指導のもとでのみ心理療法が保険適用されるため、
心理士が精神科医の下請けになる構造になっている。
つまり、専門的な心理療法が受けづらい環境が制度的に作られているのだ。
- 製薬会社の利権と精神医療の実態
精神科で処方される向精神薬の60%以上が米国製薬会社のものであり、
日本市場だけで年間数千億円規模のビジネスになっている。
例えば、抗うつ薬(SSRI・SNRI)の日本市場の70%以上が米国製薬会社の開発品である。
また、精神疾患による障害年金の受給者は全体の約6割を占め、
年間約3兆円もの支給が行われている。
精神科医による診断がなければ障害年金や障害者手帳の取得もできず、
結果として、患者は精神科に通い続けるしかない構造になっている。
加えて、精神科病院の入院日数は平均328.9日と極端に長く、
一般病院(約28日)の11倍以上の長期入院が常態化している。
これは、患者を「治さない」ことで病院経営を安定させる仕組みになっている証拠である。
- 精神鑑定の問題と戦後日本の闇
日本の裁判では、精神鑑定の結果が判決を左右するケースが多い。
しかし、精神鑑定を担当するのは心理学の専門家ではなく、
心理学を学んでいない可能性のある精神科医である。
これにより、適切な鑑定が行われず、不適切な判決が下されるリスクがある。
また、精神疾患の診断を受けることで免責が適用される制度もあり、
犯罪者が意図的に「心神喪失」を装うケースも問題視されている。
本来、犯罪心理学の専門家が鑑定を行うべきだが、
現行制度では心理士が鑑定に関与できないため、適正な判断が難しい。
このように、日本の精神医療は戦後のGHQ政策の影響を受けた制度のままであり、
国民を「飼い殺し」にする仕組みが維持されている可能性が高い。
- まとめ:精神医療の独立と未来への課題
現在の精神医療制度は、患者の回復よりも経済的利益を優先する構造になっている。
その背景には、製薬会社の巨大な利権があり、
精神科医療と国の年金制度が結びついてしまっている。
本来であれば、心理療法の専門家が適正に治療を行い、
薬に頼らない治療法を推進するべきだが、
現行制度ではそれが難しく、患者が長期依存する仕組みが維持されている。
日本がこの状況を変えるためには、
「精神医療の独立」と「新しい医療体制の構築」が必要不可欠である。
また、精神医療の問題を個人レベルで意識し、
安易な薬物治療に依存しない姿勢を持つことも重要だ。
精神科の闇を知り、本当の解決策を考えることが求められている。