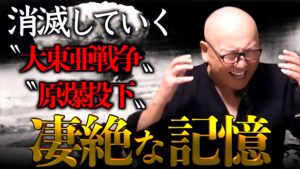終戦から80年──日本の「平和観」を問い直す
昭和20年8月15日。日本は戦いを終え、国土は焼け野原となりました。
無数の命と時間を失ったあの日から、日本は新しい歩みを始めました。
戦争を放棄した憲法を掲げ、「平和国家」として歩んできたと多くの人は信じてきました。
しかし、果たして日本は本当に中立の国だったのでしょうか。
日本は中立国ではなかった
戦後80年間、世界では朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガニスタンやイラク、そしてロシア・ウクライナ戦争まで、数多くの紛争がありました。
そのたびにアメリカは当事国となり、日本の在日米軍基地は補給や出撃、負傷兵の治療の拠点として使われました。
つまり日本は「戦争をしていない」一方で、常に戦争当事国の一部であったのです。
これを中立と比べると、その違いは明白です。
スイスは第二次大戦中、ナチス・ドイツに自国領の通過を迫られても「中立を守るために戦う」と徹底抗戦の構えを取りました。
中立は「一切関与しない」ことを貫く強い意志に基づきます。
事実上の占領下にある日本は、その条件を満たしていません。
日本人の強さの源泉──「和」の精神
それでも日本は、戦後に自衛隊を戦場へ送り銃撃戦をすることなく、平和を維持してきました。
その背景には、日本人の特質があります。
自衛隊は最新装備でなくとも高い技量を誇り、海上自衛隊は環太平洋で最強とされ、陸上自衛隊も世界屈指の力を持っています。
その強さの根底には、個人主義ではなく「和をもって貴しとなす」という精神があります。
考え方は人それぞれ違っても、共感し合い、心を響かせ合うことができる。
この「共振」「共鳴」の感覚こそ、日本人の強みであり、平和の礎になってきました。
さらに日本文化には「祀る」という独自の在り方があります。
祇園祭に象徴されるように、疫病や怨霊さえも「敵」とせず、祭りに招き入れて共に楽しむ。
この寛容さは、悪や恐怖をも排除せず、共に生きる方向へと転換させてきました。
平和は築くもの
昭和20年8月15日、日本はすべてを失いました。
けれども立ち上がる原動力は憎しみではなく、「再び豊かに暮らそう」という祈りと再生への思いでした。
職場でも政治や宗教の違いを超えて「まずは仕事をしよう」と声を掛け合い、生活を立て直していったのです。
平和は願うものではありません。築き上げるものです。
そのためには、過去を知り、苦しみを学び、違いを恐れずに語り合うことが欠かせません。
日本は「知ること」を大切にしてきた国柄を持っています。
知り、響き合い、共に生きる。
その営みの積み重ねこそが、新しい平和な社会を築いていくのだと思います。
終戦から80年を迎える今こそ、私たちは「誰かを恨む」ことではなく、
「共感と響き合い」によって平和をつくりあげていく道を選ぶべき時ではないでしょうか。