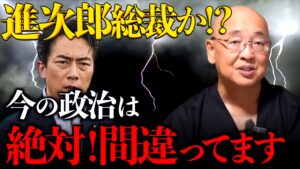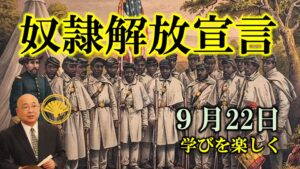プレスコードは終戦直後に発布された言論統制の規定でした。政府は「すでに失効」と答弁しますが、現実には報道と国民意識を縛り続け、自由を弱めています。その本質と意義を考えます。
戦後日本を縛った「プレスコード」の正体
終戦直後の1945年8月、GHQが日本に上陸して間もなく示したのが「プレスコード」でした。
9月10日付の覚書は、表向きには「真実の報道を守る」「虚偽や扇動を避ける」といった至極まっとうな内容で、日本政府はこれを正式に受け取り、1952年の主権回復とともにすでに失効している、というのが現代の政府答弁です。
ところが実際には、その後9月19日に発布された26項目のGHQの内部指令が事実上の言論統制として機能しました。
そこには「アメリカや連合国への批判禁止」「中国やソ連への否定的言及の禁止」「日本を愛する発言や神々への言及の禁止」などが含まれていました。これらは正式な覚書ではなく、あくまでGHQが一方的に運用したものでしたが、当時の新聞社や放送局は違反すれば廃業や処罰に直結するため、徹底的に従わざるを得ませんでした。
こうして「事実上のプレスコード」は、建前上は存在しないにもかかわらず、報道現場を縛り続ける結果となりました。
報道の「腰抜け化」と日本社会への影響
戦後80年を経たいまでも、その影響は色濃く残っています。
新聞やテレビは「自由に報道できる」と言いながらも、スポンサーや圧力に弱く、すぐに腰砕けになる。これは当時の恐怖がDNAのように刻まれているからです。
さらに問題なのは、報道機関にとどまらず、国民全体の意識に「本当のことを言ってはいけない」という風潮が広がったことです。
異論を述べる人は組織の中で疎まれ、波風を立てる者は敬遠される。
こうして「事実を語らない文化」が形成され、プレスコードの延長線上に今日の言論空間や庶民の意識が出来上がってしまったのです。
現代のSNSやネット空間でも、不都合な真実が削除されたり拡散されなかったりする現象が起きています。
これは直接的にプレスコードが生きているのではなくても、同じ構造が再生産されている証拠といえるでしょう。
本来の「自由」と話し合いの文化
では、言論の自由とは本来どうあるべきでしょうか。
自由とは「何を言っても良い」という放縦ではありません。事実に即して責任を持って発言し、誤りがあれば潔く謝罪する覚悟を伴うものです。そして異なる意見を尊重し合いながら、ともに真実を探し求める営みこそが、本来の自由の姿です。
議論(ディスカッション)は勝ち負けを競う潰し合いですが、話し合いは違います。
お互いの違いを認め、尊重し、真実を共に探す姿勢が大切です。
日本の伝統には「結びの文化」があります。相手を敬い合い、愛情を持って話し合うことで、新しい道筋を見出す力です。
自由は誰かに与えられるものではなく、自ら立ち上がり責任をもって築くものです。
親からも国からも会社からも与えられません。
与えられるものは束縛にすぎない。自由は「自ら寄って立つ」ことから生まれるのです。
結びに
プレスコードの歴史は、外から押し付けられた統制がいかに人々の意識を縛り、自由な社会を崩すかを示す教訓です。
そしてまた、形式上の規定ではなく「実態としての言論統制」がどれほど強力に働くかを教えてくれます。
私たちに求められているのは、意見の違いを尊重しながら話し合うこと、相手を敬い合いながら真実を探していく姿勢です。
戦後の言論統制の影を乗り越え、日本人が本来培ってきた「話し合いと結びの文化」を取り戻すときが来ています。