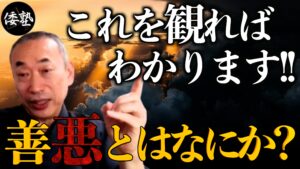祇園祭は、疫病という恐怖を排除せず受け入れ、祀ることで社会の調和を築いてきた日本人の知恵を示します。この文化的態度は、西洋や中国の災厄観と大きく異なり、現代の不安や分断にもヒントを与えてくれます。
【1】祇園祭の起源──疫病と「祀る」智慧の誕生
祇園祭は、平安時代の869年に京の都で大流行した疫病を鎮めるために始まりました。正体不明の病により人々は次々と命を落とし、その死体にたかる蛆や蝿がさらなる感染を広げる、まさに地獄絵図のような事態に。
当時の人々はその原因を怨霊や神の怒りと考え、「御霊会」という形で怨霊を鎮める儀式を行いました。この儀式が、後の祇園祭の原点です。祇園祭で祀られる神「牛頭天王」は、疫病の象徴とされる異国の神でした。
つまり、祇園祭とは恐ろしい存在を排除するのではなく、「迎え入れ、祀る」ことで災厄とともに生きようとした、日本人の知恵の現れだったのです。
【2】西洋・中国と日本──災厄に対する三つの態度の比較
この祀るという態度は、他国の文明と対照的です。
(1) 西洋的態度:善悪二元論
悪(災厄や悪魔)は排除し、征服・浄化すべき対象とみなされます。善と悪の戦いが世界観の根底にあるため、恐怖を断ち切ることが最優先です。
(2) 中国的態度:管理と封印
厄災や悪霊は、封印したり、時に利用したりする対象です。力と管理を重視し、社会秩序を保つためには厳格な統制が必要とされます。
(3) 日本的態度:受容と調和
厄災すら「祀る」ことで沈め、共に生きることを選びます。そこには「和」の精神と、魂の調和を求める文化的基盤があります。
このように、日本人は災いを否定するのではなく、その存在を一旦受け止め、社会の一部に組み込むことで調和を図るのです。
【3】現代への応用──「祀る文化」がもたらす心の再生
この「祀る」という行為は、現代の心理学でも再評価されています。恐怖やトラウマを無理に否定せず、感じきって受け入れることで癒しが始まる──これはマインドフルネスやIFS(内的家族システム)にも通じる考え方です。
つまり、我々の祖先は既に千年以上前に、こうした知恵を持ち合わせていたのです。
祇園祭は、単なる宗教儀式ではありません。それは、不安や恐れを共同体全体で引き受け、心を整える「集団ヒーリング」のようなものだったのです。
現代の日本社会において、異文化や不安、分断とどう向き合うべきか。祇園祭は私たちに、「迎え入れ、祀り、共にある」という選択肢を示してくれています。
そして「祀る」とは、単なる容認ではなく「日本の一部にする」という強い文化的統合の意思。外国由来のものでも、日本人の価値観で受け止め、日本化していく。この精神こそ、今の時代にこそ大切にすべき「祇園の心」なのではないでしょうか。