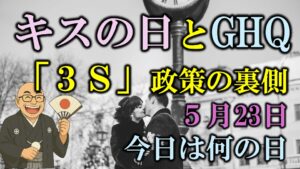善悪や犯罪と不倫を一括りにする思考は、現実の多様性を見失わせます。錯覚の本質に気づくことで、曖昧な現実をありのままに受け止め、真の問題解決への視座が得られます。
◉ 錯覚が見えるということは、現実が見えるということ
東郷潤氏は20年にわたって「錯覚」や「心理トリック」に取り組み、特に善悪にまつわる錯覚を見抜く思考法を探求してきたと語ります。文章はごまかしが効くが、絵本の創作はそうはいかない。登場人物の心の動きを具体的に描かねばならず、わかっていないことは書けない。だからこそ、曖昧さを曖昧なまま耐える力が重要になるのです。
この「モヤモヤしたものをそのまま見つめる力」こそが、錯覚を見抜く第一歩です。現実世界は複雑で、決して単純に二分できるものではありません。戦争もテロも、未成年の反抗も、全ての現象には異なる背景と原因があり、それをすべて「悪」とひとまとめにする単純思考は、現実を見誤らせてしまいます。
◉ 「単純化の罠」──善悪二元論がもたらす錯覚
この対談の核心は、「全ての問題を“悪”として捉え、対処法を“悪と戦う”に統一する思考」がいかに危険か、という点にあります。不倫、いじめ、戦争、テロ、喫煙、虐待など、現実には全く異なる背景と心理があります。それを「悪と戦う」一言で処理することは、問題の原因に目を向けないどころか、同じ過ちを繰り返す土壌を育てるのです。
さらに、この単純思考は教育や司法制度にも深く根を下ろしています。罪刑法定主義もその一端であり、「罰すれば解決」という錯覚が社会を歪めている現状があるといいます。本当に問題を解決するためには、すべてを一括りにするのではなく、個々の事象を深く観察し、それぞれの原因と向き合うことが不可欠です。
◉ 「善悪」か「よしあし」か──日本的価値観の再発見
善悪という言葉には「対立する二項の固定観念」が含まれていますが、日本語には「よしあし」という訓読みがあります。これは曖昧さや揺らぎを内包した表現であり、「どちらかが絶対的に正しい」とは限らない、柔らかな思考を促します。
古事記に登場する「もゆらにゆらかして」の場面など、日本文化にはもともと曖昧さや複雑さを肯定し、受け入れる感性が息づいています。曖昧なものを曖昧なまま受け止める勇気こそが、錯覚を見抜くための感性を育てるのです。
また、「1+1=2」すら、現実の中では腐ったリンゴやサイズの異なるリンゴを前にすると当てはまらない。数字や三段論法のような“明快な理屈”に安心を求めるのではなく、現実の多様性や複雑さを受け止める柔軟な思考が必要です。
◉ 結論──「錯覚」を超えるために私たちができること
錯覚は、モヤモヤとした曖昧な領域から生まれます。そのモヤモヤを“なかったこと”にせず、「そういう曖昧さがある」と認めることで、ようやく錯覚の芽を見抜けるようになるのです。
「善悪を峻別せよ」という言葉が、実は錯覚を助長しているケースも少なくありません。誰かの行為を悪と断じ、罰を与えて終わらせる社会では、原因は放置されたまま。新たな対立と分断が繰り返されるばかりです。
私たちに必要なのは、曖昧さを受け入れる力、多様な現実を多様なままに受け止める感性、そして「個別の事象に個別の原因がある」ことを見失わない思考力です。
日本が本来持っていた“揺らぎの文化”にこそ、これからの時代を生きるための知恵がある──そんな気づきが、この対談には込められています。