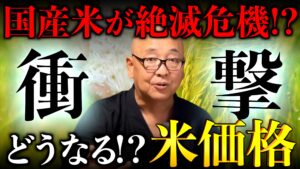対立ではなく合力を、支配ではなく共鳴を。田の香りが立つ季節に、「天下の大将軍」とは何かを、日々の作法と笑顔の波動から考え直したい。
Ⅰ 9月24日に重なる出来事──歴史の転換とものづくりの精神
9月24日は、歴史と現在をつなぐ節目がいくつも重なる日です。
まず1338年(延元3年8月11日)、足利尊氏が北朝から征夷大将軍に任ぜられ、事実上の室町幕府が動き出しました。
征夷大将軍は単なる呼称ではありません。軍政の頂点を任ずる重い役職です。
近年は人気作品『キングダム』の影響で“大将軍”という言葉のイメージが若い世代にも浸透しましたが、本質は「王権のもとで統帥権を担う責任者」という点にあります。
上意に忠実でありながら、現場を動かす判断力・統率力・人心掌握を兼ね備える。
その姿は、混乱期の秩序回復において真価を発揮します。
尊氏任官の日を振り返ることは、肩書ではなく“役割”の重さを見つめ直す機会でもあるのです。
同じ9月24日、1948年には本田技研工業が創業しました。
技術で世界に挑む意志と、品質への執念は、日本の「ものづくりの矜持」を象徴します。
価格競争に埋没せず、性能と安全、そして楽しさを追求する姿勢は、歴史に名を刻むリーダーが果たすべき“役目”と相似形です。
名だけの将でなく、実の伴う将であること。
社名や肩書よりも「良いものを世に出す」という責任を貫くこと。
ここにも“大将軍の条件”が重なって見えます。
さらに1572年には、ビルカバンバ(Vilcabamba)のインカ王トゥパク・アマルが処刑され、文明の断絶が決定づけられました。
外圧の前に文化の芯が折れると、技や言葉、祈りや食が断ち切られ、回復は困難になります。
守るべきは領土だけではなく、生活の作法や心の秩序です。
歴史が示すこの教訓は、今日の日本にとっても無関係ではありません。
Ⅱ 稲刈りの季節と自然栽培──共存の知恵が米を強くする
彼岸を過ぎ、旧暦ではまだ八月。
猛暑が和らぎ、各地で稲刈りが進む季節です。
このチャンネルで、倭塾とご縁のある田んぼで農薬を使わない自然栽培に挑戦し、黒い斑点(カメムシ被害)が見られない見事な米が得られた報告が共有されました。
精米後の白さと粒の張りからも、生命力に満ちた米であることが伝わります。
特徴的なのは「雑草と戦う」のではなく「棲み分けて共存する」という考え方です。
畦や周縁に雑草の居場所を与え、田の中では稲そのものを強く育てる。
結果として、薬剤で外から抑え込むのではなく、作物自身の健やかさで害を寄せつけにくくする。
これは日本の農の知恵と非常に相性が良い発想です。
大量生産・空中散布・一律管理という近代のやり方には、規模の経済という利点があります。
しかし味、香り、消化の良さ、体への負担の少なさといった“静かな価値”は、自然と調和する栽培ほど手応えが大きくなります。
お米の値段をめぐる議論は大切ですが、それだけでは味や安全、田んぼの風景や地域文化まで含めた全体像を捉えきれません。
米は単なるカロリーではなく、文化そのものです。
炊き上がりの湯気の香り、味噌汁と交わる余韻、家族の会話が弾む食卓──こうした体験が、心身の安定と地域の連帯を支えます。
自然栽培の成功例は、価格や収量の議論に偏りがちな社会へ、「強さとは共存にある」という別解を示してくれます。
Ⅲ 言葉の作法と“笑顔の波動”──秩序を支える目に見えない力
番組では、後醍醐天皇を「後醍醐」と呼び捨てにする書き方への違和感も語られました。
呼称は単なる形式ではなく、秩序の確認です。
公的な立場にはふさわしい敬称があり、歴史の人物にも守るべき作法があります。
雑な呼び方は、やがて思考の雑さを呼び込み、議論は過激化しがちです。
また、流通や出版の現場で起きるレッテル貼りや選書の偏りにも触れました。
売れ筋や話題性に流されるだけでは、骨太の議論が細る心配があります。
必要なのは、対立ではなく「話し合い」。
意見をぶつけ合う“議論”に偏ると勝ち負けに縛られますが、“話し合い”は相手の背景ごと受け止め、次に進む合意を探す営みです。
ここで大切にされているキーワードが「共振・共鳴・響き合い」です。
笑顔や感謝の所作は、目に見えにくいものの、場の空気を整え、人の心を開き、現実の行動を変えます。
怒りの連鎖は怒りを呼び、笑顔の連鎖は協力を呼ぶ。
歴史が動くとき、その前触れは往々にして“心の向き”の変化として表れます。
征夷大将軍がただの肩書ではなく“役割”であったように、消費者・生産者・教育者・メディア・行政それぞれにも果たすべき役割があります。
正しい呼称を守ること、
情報を丁寧に伝えること、
自然と共存する作法を学び合うこと、
そして笑顔で場を整えること。
どれも華やかではありませんが、文明の芯を太くする力です。
9月24日という一日の中に、
将の任官、
企業の創業、
文明の断絶
という三つの物語が重なりました。
対立ではなく合力を、支配ではなく共鳴を。
田の香りが立つ季節に、「天下の大将軍」とは何かを、日々の作法と笑顔の波動からもう一度考え直す時期に来ています。