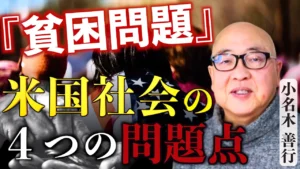明治3年(1870年)の「大教宣布詔」は、日本を神道の国と定める国家方針を示したものでした。しかし、背景には欧米の宗教観の影響や、廃仏毀釈の混乱がありました。本来の「道」と「教え」を見直し、日本の「むすび」の文化を再考します。
大教宣布詔と2月3日の意義
>立春と乳酸菌の日
2月3日は「立春」であり、日本の季節の移り変わりを象徴する日です。また、「乳酸菌の日」でもあり、日本古来の発酵食品文化の重要性を思い出させる日でもあります。しかし、歴史的に見ると、1870年の2月3日には「大教宣布詔」という、日本の国家方針に大きな影響を与えた詔が発布されました。
>大教宣布詔とは何か
大教宣布詔(たいきょうせんぷのみことのり)は、明治3年(1870年)に発布された詔で、日本を「祭政一致」の国家とし、神道を国の柱とする方針を示しました。
この詔は、欧米列強がキリスト教を国教とすることを前提として外交を行っていたため、日本も「宗教」を明確に持たなければならないという背景から生まれました。
明治政府は、「日本には天照大神を中心とする神道がある」と宣言することで、国家のアイデンティティを確立しようとしたのです。
廃仏毀釈と神仏分離の流れ
>廃仏毀釈とは何だったのか
明治元年(1868年)には「神仏分離令」が出されました。これにより、日本各地で仏教寺院の破壊や仏像の廃棄が進みました。この流れを推し進めたのが、大教宣布詔の背景にある廃仏毀釈運動です。仏教を排除し、神道のみを重視するという方針が一時的に取られましたが、これは完全な成功とは言えませんでした。
>廃仏毀釈の終焉
廃仏毀釈の動きは激しいものでしたが、実際には長くは続かず、明治9年(1876年)には終息しました。日本の文化には仏教が深く根付いており、完全な排除は不可能だったのです。結果として、仏教は国家神道と並存する形で存続しました。
>大教宣布詔の意味
このような流れの中で発布された大教宣布詔は、祭政一致の理念を掲げながらも、最終的には形骸化しました。つまり、一時的に国家神道を確立しようとしたものの、日本は再び神仏習合の道へと回帰したのです。
「道」と「教え」— 日本文化の本質
>道と教えの関係
日本の文化において、神道は「道」として、仏教や儒教などの教えは「道を歩むための教え」として考えられてきました。これは、受験に例えるなら「合格までの道」と「合格するための教え」の関係に似ています。
どちらか一方が欠けても、目標達成は困難になります。したがって、日本の文化は「道」と「教え」の両立によって成り立ってきました。
>現代日本と「教え」の偏り
現代日本では、「拝金教」とも言えるような「金こそすべて」という価値観が広がっています。しかし、これは「教え」ではなく「欲」です。本来、日本は「むすび」の文化を持っており、「道」と「教え」が結ばれることで、社会の調和が生まれる仕組みになっています。
しかし、現代では「道」が失われ、「教え」だけが独り歩きしてしまい、結果として日本の精神的な基盤が揺らいでいるのです。
日本文化の本質—「むすび」の力
>「むすび」の意味
「むすび」とは「産霊(むすひ)」とも書きます。「むす」とは自然と発生するもの、「ひ」は神秘的な力を意味します。
つまり、「むすび」は「自然と発生する神秘的な力」のことを指し、これこそが日本文化の根幹です。
例えば、日本では男と女が結ばれることで新しい命が生まれるように、異なるものが結びつくことで新たな価値が生まれます。
>日本は「和の国」である
日本の古称である「倭(わ)」は、まさに「和(わ)」を意味し、異なるものが結ばれ調和する国であることを示しています。
この考え方が、神道と仏教の神仏習合を生み、廃仏毀釈後も結局は仏教を排除せずに残すという選択につながったのです。
まとめ
◆ 1870年2月3日に「大教宣布詔」が発布され、日本は「祭政一致」の国家を目指した。
◆ しかし、廃仏毀釈の影響もあり、仏教を排除することは難しく、最終的に日本は再び神仏習合へと回帰した。
◆ 日本文化の本質は「道」と「教え」の両立にあり、それが結びつくことで調和が生まれる。
◆ 「むすび」の力を見直すことが、今後の日本にとって重要。
日本が本来持っていた「むすび」の文化を再認識し、道と教えを調和させることが、これからの時代に必要なのではないでしょうか。