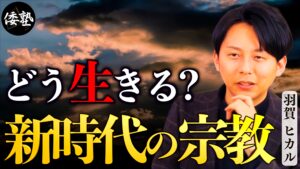昭和天皇の幼年期における教育と躾、そして日本人に根づく「本家=天皇家」との精神的つながりを振り返ります。
日本人の道徳観と誇り、その源流がここにあります。
■ 幼年期から育まれた品格と道徳心
昭和天皇(裕仁親王)は、明治34年に明治天皇の初のお孫としてお生まれになりました。名に込められた「裕仁」という二字には、「広く大きな心で国を治め、人類の幸福に尽くす」という深い意味があり、それはまさに昭和天皇のご生涯そのものでもありました。
ご誕生後、生後70日で枢密顧問官・川村純義伯爵邸に預けられ、3歳までの養育が始まります。川村家では「心身の健康」「天性を曲げぬ」「人を尊ぶ」「難事に耐える」「わがままを許さぬ」という五つの方針が実行されました。これに基づいた厳格なしつけの一例として、食べ物の好き嫌いを叱責され、以後一切の偏食がなくなったという逸話もあります。
このように、人格形成の土台は幼年期からしっかりと築かれていたのです。日本の伝統的教育においては、知識の詰め込みではなく、まず「人としてのあり方」を教えることが根本にありました。
■ 乃木希典院長による質素と礼節の教え
明治40年、裕仁親王は学習院初等科に入学されます。学習院の院長はあの乃木希典大将。彼は「健康第一」「ご成績に忖度なし」「礼節と質素」「軍務への備え」などの6項目を教育方針として定め、全教職員に徹底を命じていました。
裕仁親王は雨の日も風の日も徒歩で登校され、つぎあての制服を誇りにし、鉛筆は短くなるまで、消しゴムは豆粒ほどになるまで大切に使われました。乃木院長は毎朝玄関で殿下を迎え、殿下はその前で立ち止まり、きちんと挙手の礼をされたそうです。
尊敬する人は?との問いに、周囲が明治天皇と答える中、裕仁親王だけが「源義経」と答えられました。養育係「足立たか」から義経の話を聞き、深く感銘を受けていたのです。この“たか”こそ、のちの鈴木貫太郎元首相の妻であり、夫の命を救ったことで知られる伝説的な人物です。
■ 日本人と天皇家の「本家と分家」の関係
昭和天皇のご幼少時代の教育やエピソードから見えてくるのは、日本人にとっての「天皇家」との独特な精神的関係です。日本人にとって天皇陛下は、単なる国家元首ではなく、「本家」にあたる存在であり、私たち国民は「分家」のような感覚を持っています。
この“本家と分家”の関係は、上下でも命令服従でもありません。本家に法事があると言えば、自然と分家が集まるような関係。陛下が侮辱されれば怒り、陛下が慕われれば誇りに感じる。こうした感情は、教育で植えつけられたものではなく、日本人に根ざしたDNAレベルの感覚だと語られています。
飛騨に伝わる阿礼家の口伝では、神武天皇以前にも250代以上の天皇がいたという話も紹介されます。こうした口伝が意味するのは、天皇が“民のために尽くす長”として慕われてきた歴史の重みです。
私たちが昭和天皇の幼少時代の写真を見て、どこか懐かしく、誇らしく思うのは、この深い精神的つながりがあるからなのかもしれません。
【ブログ記事】
https://nezu3344.com/blog-entry-4757.html