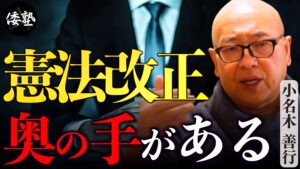4月1日はただのエイプリルフールではありません。新学期の始まりとして、教育制度の節目でもあります。日本の教育史を振り返りながら、かつての師範学校制度や寺子屋の学びの姿を通して、真の教育のあり方を問い直します。
◉ エイプリルフールの由来と「新年」のすり替え
4月1日は「エイプリルフール」として知られ、嘘をついても許される日とされています。この習慣の起源には諸説ありますが、有力なものの一つが、16世紀のフランスでの暦改革に由来します。当時、ヨーロッパでは3月25日を新年とし、そこから1週間続く春の祭典が行われていました。しかし、1564年にフランス王シャルル9世が1月1日を新年と定めたことで、従来の暦に反発した人々が、4月1日を「嘘の新年」として馬鹿騒ぎを始めたのが、エイプリルフールの始まりだといわれています。
このような風習が民間信仰として定着し、「4月1日は嘘をついても神様が許してくれる日」という考え方が生まれ、現在のような習慣へとつながっていったのです。
◉ 4月1日生まれは早生まれ? 新学期と就学制度の仕組み
日本では4月1日が新学年の始まりとされていますが、実はこの仕組みが導入されたのは明治19年(1886年)からと、比較的新しい制度です。それまでは入学の時期は家庭や地域によってまちまちであり、子どもが学び始めるタイミングは自由でした。
また、4月1日生まれの子どもは「早生まれ」として、前年度の学年に組み込まれます。これは、日本の教育法により、「満6歳になった翌日以降」に就学の義務が発生するというルールによります。つまり、4月1日生まれは、満6歳になるのが4月1日であるため、就学義務が発生するのは翌日の4月2日からとなり、「前年度の新入生」となるのです。
こうした年齢の計算方法や制度の背景には、近代以降の法的整備がありますが、それ以前の日本には、もっと柔軟で実践的な教育の姿があったのです。
◉ 寺子屋と師範学校──日本の教育の誇り
江戸時代の日本では、寺子屋が全国各地に広まり、庶民も高い識字率を持っていました。その背景には、年齢にこだわらず、必要なときに学び始められる教育制度があったことがあります。
寺子屋では、上級生が下級生を教える「助け合いの教育」が基本でした。小学校5年生や6年生に相当する子どもたちが、1・2年生にあたる新入りの子どもたちを指導し、わからないことがあれば共に考える。こうした学びの中で、子どもたちは「教えることこそが学び」であると自然に体得していきました。
明治時代に入ると、教育制度の近代化が進められ、明治19年には高等師範学校が新学年を4月1日始まりと定めます。これが明治21年から全国に広がり、現在の学年制度の基礎となりました。
特筆すべきは、東京・広島・金沢・岡崎の4都市に設置された「高等師範学校」です。これらは、民衆の中から優れた教育者を育成し、全国に民度を高める指導者を送り出すことを目的としたエリート教育機関でした。特に「師範学校卒業生」という肩書は、社会的な信頼の証でもあり、その言葉には大きな説得力がありました。
◉ 失われた師範学校、そして教育の未来
戦後、GHQの指導により師範学校制度は廃止され、「東京教育大学」などの新たな大学制度へと再編されていきます。さらに現在では、「筑波大学」と名前を変え、その面影を一部に残しつつも、民衆の中に教育の模範たる人材を育てるという師範学校本来の使命は失われつつあります。
この流れの中で、日本人の民度や誇りが徐々に損なわれてきたという指摘もあります。教育は知識を詰め込むものではなく、「考える力」を育むことに本質があります。その力は、ただの知識ではなく、人間の魂と神々から授かった知恵によって養われるものです。
現代の教育制度では、教師の権威が低下し、生徒に注意すれば保護者からクレームが入るなど、教育現場の崩壊も懸念されています。こうした現状を打破するためには、かつての師範学校のように、道徳的・精神的な柱を持った人材を育てる仕組みを復活させる必要があるのではないでしょうか。
日本の未来を支えるのは、やはり教育です。今こそ、過去の良き伝統に学びつつ、現代の知恵と融合させた新しい教育制度を築くべき時が来ているのかもしれません。4月1日という「始まりの日」にふさわしく、私たち一人ひとりが学びと誇りを取り戻すきっかけとなることを願ってやみません。