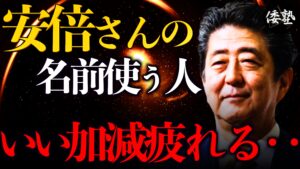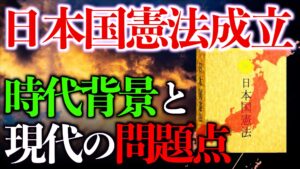あんぱんは、明治時代に武士から転身した木村安兵衛が、日本酒の酵母で生地を作り、小豆あんを包んだ和洋折衷のパンです。明治天皇への献上をきっかけに、全国に広まり、日本人の定番菓子となりました。
◉ あんぱん誕生の裏にあった武士の再出発
あんぱんが誕生した背景には、明治維新によって職と身分を失った元武士・木村安兵衛の再出発があります。安兵衛は茨城県牛久藩の出身で、藩が幕府側についたために明治維新後すぐに解体され、55歳で無職となってしまいます。まだ幼い子を抱えた彼は、家族を養うため本家を頼って江戸に出て、東京府の職業授産所(職業訓練所)で働くようになります。
授産所では、オランダ人宅で料理人をしていた梅吉という人物と出会い、初めて「パン」の存在を知ります。文明開化の時代にふさわしいと考えた安兵衛は、妻の蓄えを元手に、新橋でパン屋「文英堂」を開業しました。「文」は妻の名から、「英」は息子・英三郎の名から取ったものです。
しかし、開業して間もなく火事で店は焼失。無一文となった一家は絶望の淵に立たされますが、安兵衛は決してくじけず、家族とともに銀座の裏通りでパン屋を再出発。立地に恵まれず、売れ行きも乏しい中、毎朝パンを焼き、親子三人で行商に歩くという苦労の日々を送ります。
◉ 和の知恵が生んだ“あんぱん”と天皇献上
そんな中、安兵衛は「和の知恵」をパンに取り入れることを思いつきます。通常、西洋式パンはホップ由来の酵母で発酵させますが、安兵衛はこれを米から作られる日本酒の麹に置き換えました。この日本酒酵母によって、パンは日本人の口に合う、柔らかく香り高い風味を持つようになります。
そして、ある日安兵衛は、この米麹パンの中に小豆あんを入れた“あんぱん”を開発しました。この試みが大成功。評判は口コミで広まり、ついに剣術家・山岡鉄舟の耳にも入ります。鉄舟は感動し、明治天皇が水戸家に行幸される折に、あんぱんを献上。明治天皇は大いに気に入り、皇后陛下は特に愛されました。こうして木村屋のあんぱんは、宮中御用達の栄誉を賜ることとなったのです。
店の看板「木村屋」の文字は、山岡鉄舟が自ら揮毫したものとされており、木村屋の品格と歴史の深みを象徴する存在となっています。
◉ あんぱんが“軍用食”として全国に広がる
明治10年、西南戦争が勃発。政府軍の兵糧として選ばれたのが、このあんぱんでした。木村屋は陸軍から大量の注文を受け、全国に向けてあんぱんを供給します。兵士たちはこの和風パンを口にし、「こんなうまいパンは食べたことがない」と驚嘆。こうしてあんぱんは、軍を通じて全国津々浦々にまで広まっていきました。
あんぱんの普及は単なる食品の流行ではありませんでした。日本人の口に合う、日本人の心に寄り添う「和洋折衷のパン」として、あんぱんは人々の暮らしの中に自然と溶け込んでいったのです。
そして木村屋は大繁盛し、現在の「銀座木村屋總本店」へと発展。現代でも多くの人々に愛され続けていますが、その根底には、安兵衛の「めげず・くじけず・明るく・清く」努力と精神が息づいているのです。
🍞最後に…
私たちが何気なく手に取るあんぱん。その一つひとつに、明治という激動の時代を生き抜いた男の想いと、日本の美徳が宿っています。
苦しいときこそ前を向き、精いっぱい働き、未来を信じてチャレンジしていく!!
あんぱんには、そんな日本人の心が詰まっているのです。