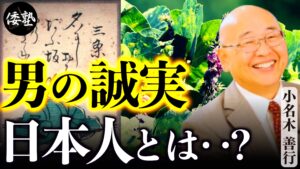忠犬ハチ公の物語は、単なる美談ではありません。
上野博士が追い求めた「農業土木」による日本の農業復興を、今なお伝えようとしている――
そのハチの姿に込められた“日本の心”を見つめ直します。
◉ 忠犬ハチ公は何を待っていたのか
渋谷駅前に立つ「忠犬ハチ公」の像は、今や誰もが知る待ち合わせスポットですが、その背後には、深い歴史と日本の未来への願いが込められています。飼い主である上野英三郎博士は、東京大学農学部の教授であり、農業土木の第一人者でした。
農業土木とは、小規模な農地を集約・整理し、共同経営によって高生産性を実現し、食料自給率の向上を目指す学問です。上野博士はこの分野の創始者であり、その教えを受けた人は3000人を超えました。日本の未来のために食料生産の基盤を整え、民が豊かに暮らせる仕組みを整えようと尽力していた人物です。
その上野博士が突如急逝した後も、ハチは毎日渋谷駅に通い続けました。家を転々とさせられ、時に虐げられながらも、ひたむきに博士の帰りを待ち続けたのです。
◉ 「忠犬」の物語の裏にある日本の心
ハチは多くの人から可愛がられた一方で、屋台の店主から邪魔者扱いされ、棒で叩かれたり、子供に落書きされたり、野犬捕獲人に追われるなど、つらい目にも遭っていました。それでも毎日駅へ向かう姿に、人々の心は動かされ、昭和7年に朝日新聞にて紹介されると、一躍全国にその名が知られるようになります。
翌年には銅像建立の運動が起こり、日本全国の小中学生、さらにはアメリカからも寄付が集まりました。これは日米合作でできた記念像とも言えるでしょう。教科書にも掲載され、戦前の子供たちに「忠義の心」を教える象徴とされました。
しかし、ハチの死後に行われた解剖では、胃から焼き鳥の串が刺さっていたことも判明し、人々の無理解や冷たさも浮き彫りになります。にもかかわらず、ハチは最後まで博士の帰りを待ち続けたのです。
◉ ハチが待っているのは、農業の復興と日本の未来
ハチの物語は、単なる飼い犬の忠義話にとどまりません。彼が待っていたのは、上野博士の「帰り」、すなわち、日本の農業がもう一度再興される日ではないか――
それがこの動画で語られた最大のメッセージです。
天照大神の神勅にある「豊葦原の瑞穂の国」とは、金色の稲穂が揺れる日本の風景そのものです。ハチは、博士と共に夢見た“豊かな水田が広がる日本”の帰還を、今も静かに待っているのではないでしょうか。
戦後、日本の農業は効率化と経済論理に飲まれ、伝統や共同体的な心が薄れてきました。しかし、ハチが示したように、一途に信じ、待ち続ける姿こそが、日本人の心そのものです。
渋谷駅前のハチ公像は、ただの銅像ではありません。そこには、日本の未来への祈りと希望が込められているのです。