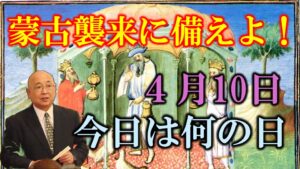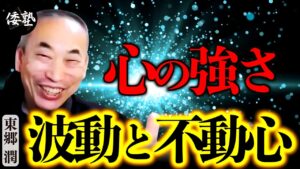モヒの戦いでは、戦力で勝るハンガリー軍が、民衆の支持と戦術に優れたモンゴル軍に敗北しました。モンゴルの庶民を大切にする統治が、軍事力を超える強さの秘密だったのです。
◉ ヨーロッパ最大の戦い「モヒの戦い」とは
1241年4月11日、ハンガリー平原でモンゴル軍とハンガリー軍が激突しました。モンゴル側はバトゥとスブタイが率いる約1万の兵、対するハンガリー軍は王ベーラ4世が率いる1万1千の兵でした。数ではハンガリー軍が上回るものの、モンゴル軍は戦術に優れ、効果的な火器(花火状の爆発物)や投石器を駆使し、ハンガリー軍を大混乱に陥れます。さらに別働隊のスブタイ軍が背後から挟撃し、ハンガリー軍は壊滅。王ベーラ4世は辛うじて逃れたものの、ヨーロッパに大きな衝撃を与える敗戦となりました。
◉ モンゴル軍の強さの本質は「庶民重視」にあり
この圧倒的勝利の背景には、単なる軍事力だけでなく、モンゴル帝国の統治制度にあります。当時のヨーロッパや中央アジアの城塞都市国家は、王や貴族が富を独占し、庶民は重税と過酷な労働に苦しんでいました。しかし、モンゴルが支配すると、通行税や税制が公平化され、交易が盛んに。農民たちは農産物を城内で自由に販売できるようになり、生活が劇的に向上しました。
さらに、モンゴル軍に加わると、戦利品が明確に分配される「恩賞システム」がありました。これは日本の源氏に似た制度で、戦死者の家族にも報酬が渡されるなど、非常に公正でした。このような制度が民衆の支持を集め、モンゴル軍の力の源泉となったのです。
◉ 現代日本と重なる教訓──庶民軽視の政治からの脱却を
動画後半では、この歴史から現代日本への示唆が語られます。現在、日本では物価高騰やガソリン価格の上昇、食料価格の急騰(特にお米)が進んでいるにもかかわらず、政府の議論は庶民の暮らしから離れたものばかりです。お米の価格が2.5〜3倍になっても、輸出政策が優先され、国内の農家や消費者が置き去りにされていると指摘されました。
モンゴル帝国が成功した背景には、庶民を中心に据えた政治と経済の仕組みがありました。今の日本も、輸入頼みの構造から脱却し、国内農業を活性化させる必要があるのではないか――そのような問いかけがなされています。
モヒの戦いはただの過去の戦争ではなく、「どんな国が真に強いのか」「庶民の力がいかに国の土台を成すか」を教えてくれる重要な出来事なのです。
そしてその本質は、日本が持っていた価値観と深くつながっているのです。