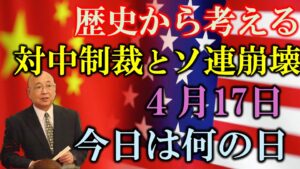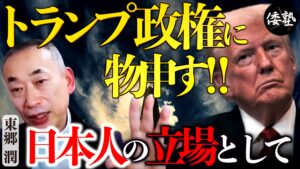絵島生島事件は、単なるスキャンダルではなく、
大奥という公の場における規律と責任の重みを問い直すものでした。
上に立つ者の慎みと公正こそが、社会の安定を支えていた。
現代にも通じる教訓を探ります。
◉ 江島生島事件とは何だったのか
1714年(正徳4年)3月5日、江戸城・大奥の御年寄であった絵島(本名・みよ)が、月光院の名代として芝の増上寺に参詣した帰り道、芝居小屋・山村座で人気歌舞伎役者の生島新五郎の芝居を観劇。その後、生島らを招いた宴が長引き、大奥の門限に四半刻(約1時間)遅れてしまいます。
それが江戸城内で問題となり、江島は高遠藩預かり、生島は三宅島へ流罪、関係者50名近くが処罰されるという大事件へと発展しました。処分の対象は「門限遅れ」ではなく、「大奥の規律弛緩」。このことが事件の本質を物語っています。
◉ 江戸城は“行儀見習い”の場だった
大奥に限らず、江戸城内は将軍の身の回りを世話する場であると同時に、直参旗本の娘たちが“行儀見習い”として奉公する教育の場でもありました。ここで身につけた品格や作法は、上流階級の女性にとって必須の素養。江戸の民衆も、大奥の規律に注目していました。
その中で、江島は年寄として多くの娘たちの“模範となるべき者”でした。その人物が門限を破るとなれば、大奥の緩み=幕府全体の緩みと見なされるのは当然の流れでした。
◉ 「たかが門限」では済まされなかった理由
不義密通の証拠は一切ありません。幕府もそれを問題にしていません。処分の核心は「規律の維持」にありました。上に立つ者が規律を守らなければ、下はそれを真似し、組織全体が崩れていくからです。
徳川幕府は、綱紀粛正を通じて「筋を通す政治」を貫こうとしたのです。
だから、「たかが数分の遅れ」で済まされる問題ではなく、
「重責にある者の行動が社会に及ぼす影響」が重く見られたのです。
◉ 日本の伝統:上に立つほど慎みを
世界では、権力者ほど贅沢が許される風潮が多くありました。しかし日本は逆で、上に立つ者ほど、慎み・公正・品格が求められてきました。
江戸時代の日本人は、「立場が上だからこそ、自らを律する姿が必要だ」と考えてきたのです。
日頃、思想を人よりも上にすることは疑問と申し上げています。
これは、思想ではなく「文化(Culture)」の問題なのです。
「文化」を大事にする。
その姿勢こそが、未来を築くものなのです。
◉ 江戸の知恵を、現代のわたしたちへ
私たちが生きる現代は、SNSなどを通じて、誰もが発信力を持つ時代ですが、そうであればこそ、それなりに社会に影響を及ぼそうと情報発信する人は、「自らを律する覚悟」が必要といえるのではないでしょうか。
たとえ「たかが数分の遅れ」「ちょっとした言動」であっても、それが社会にどれほどの影響を与えるのか。そういうことへの自覚なしで、未来を築くことなど、できないことといえるのではないでしょうか。
絵島生島事件は、私たちに次のことを問いかけます。
(1) 公に関わる者としての自覚を持っているか?
(2) 自らの言動が周囲に与える影響を意識しているか?
(3) 責任ある立場にある人間として、人々の模範となっているか?
その教訓は、まさに現代日本にも通じる「日本人としての文化」の根幹であり、未来の私たちに託された道しるべといえるのではないでしょうか。
◉ おわりに
絵島生島事件は、決して“江戸のお色気スキャンダル”などではありません。
「規律とは何か」「公の姿勢とは何か」を深く問い直す、真剣な社会的事件です。
わたしたちもまた、公に生きる者としての覚悟と慎みを忘れず、
次の世代へ誇れる社会を築いていきたいものです。
「ありがとう、日本!」