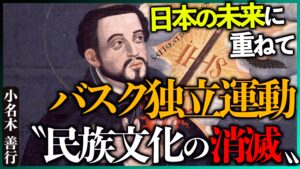八十八夜の茶摘みと唱歌に込められた文化や命の循環を紐解きながら、清水の次郎長の逸話、大隅国設置の背景などを通して、日本人の再生と寛容の精神を掘り下げます。
◉ 長寿の象徴・八十八夜と「茶摘み歌」に込められた命の文化
5月1日は「八十八夜」。
立春から88日目にあたるこの日は、新茶を飲むと長生きできると言われる、古くからの吉日です。文部省唱歌『茶摘』で歌われた「夏も近づく八十八夜…」の旋律は、今でも多くの人の記憶に残っていますが、その作詞作曲者は不明。実はこの歌、子どもたちの手遊び歌として自然発生的に広まったもので、茶葉を摘む手の動作に由来しているとも言われています。
この『茶摘』には地域ごとの歌詞バリエーションも存在し、たとえば京都の宇治、奈良の田原、滋賀の大津など各地で「摘まねば日本の茶にならぬ」などの表現がありました。そこに通底するのは、日本人の「手を動かし、自然とともに生きる」喜びの文化です。
茶摘み歌に現れるような、命の循環を歌う言葉と行動の中には、単なる農作業ではなく、生きることへの祈りと祝福がこめられていたのです。
◉ 清水次郎長に学ぶ──「やり直しを許す」日本の文化
中盤では、浪曲『石松三十石船道中』や清水次郎長の逸話を取り上げながら、日本における“赦しと再生”の価値観が語られました。
たとえば人を斬ってしまった次郎長が、牢獄ではなく「凶状旅」という修行の旅に出るという話。
人を殺した者は罪を償うべきですが、その償いを「自ら下働きし、魂を磨きなおすことで果たす」という日本的な考え方がそこにあります。
この文化はただ「悪を裁く」というだけではなく、「人が変わること」を受け入れて、
「やり直す場を社会が用意する」
という循環の思想に立っています。
親分としての誇りを捨て、全国を旅しながら厄介になり、炊事洗濯までこなす・・そうした下座と呼ばれる修行を経ることで、生まれ変わった次郎長親分が再び清水港の人々に歓迎される。
こうした姿は、日本人がいかに「人の再起」に価値を置いてきたかを物語っています。
「やり直す勇気」と「受け入れる寛容さ」。
それこそが、この国が古くから大切にしてきた社会の骨格だったのです。
◉ 大隅の国に見る“神話と現実”の接点──国造りの真の意味
713年(和銅6年)の5月1日は、歴史的にも特別な日です。この日、大隅国・丹後国・美作国が新たに設置されました。中央から地方へ国司(いまの県知事に相当)を派遣する制度が整備され、日本の国づくりが進められた重要な時期でもあります。
しかし、実は大隅国だけは国司がなかなか決まらなかった。なぜか。それは「神武天皇ご生誕の地」だったからです。その土地にいる人々は神武天皇の血を引く、すなわち「御皇室の親族」にあたる・・・そんな土地に「国司として赴任なんてとんでもねえ」という日本人の謙虚さから、以後、大隅の国は「国司なき聖地」として長く保たれたのです。これは実は沖縄も同じです。このことは、単なる行政の話ではなく、神話と現実が交錯する国づくりの在り方を示しているといえます。
◉ 茶を摘み、命を尊び、何度でもやり直す
今日、八十八夜に改めて想うべきは、「循環と宥(ゆる)しの思想」です。
ただ茶を摘むことを言うのではなく、「再び立ち上がる、何度でも立ち上がる」という人の営みそのものと通じています。
どんな失敗をしても、また一歩を踏み出す。自らの人生を、またいちからやり直す。何度だって立ち上がる。それが、縄文以来の日本文明の根幹です。
八十八夜の新茶は、そんな「命の循環」「魂の再出発」を祝福するものとして、今も私たちにそっと語りかけてくれているのかもしれません。