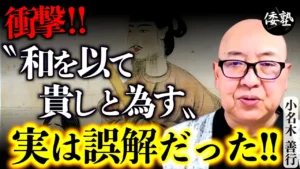5月5日は、端午の節句・こどもの日・立夏が重なる特別な日です。伝統行事に込められた命の尊重と、現代社会の課題を結びつけ、未来へとつなぐ日本人の精神文化を考察します。
◉ 端午の節句と「こどもの日」の意味
5月5日は、古来より「端午の節句」と呼ばれ、男子の健やかな成長と武運長久を願う行事が行われてきました。兜や武者人形を飾り、菖蒲湯に浸かり、柏餅を食す──それらの風習はすべて、命を大切にし、次代を担う子どもたちへの祈りから生まれています。
「端午」はもともと「月初めの午の日」を指しましたが、やがて「5月5日」に定着。菖蒲(しょうぶ)の読みが「尚武=武を重んじる」と通じたことで、男の子の節句として広まりました。
一方で、戦後の1948年には、国民の祝日として「こどもの日」が制定され、性別を問わず「こどもの人格を尊重し、幸福を願う日」となりました。さらに「母に感謝する」という意味も込められています。
◉ 立夏──季節の変わり目を生きる感性
2025年の5月5日は、「立夏」とも重なります。これは二十四節気の一つで、太陽の黄経が45度に達し、春が極まり、夏の気配が立ち始めるとされる日です。旧暦ではこの日を境に「夏」が始まり、立秋の前日までが夏とされます。
日本人は、こうした季節の移ろいを大切にし、自然と共に生きる感性を育んできました。菖蒲や蓬を軒に挿す、季節の和菓子を味わう──これらの行為には、ただの風習以上の意味が込められています。それは、自然や命に対する敬意であり、日々の暮らしを丁寧に生きる知恵でもあるのです。
◉ 戦後の記憶と「命を大切にする文化」の再確認
5月5日には、近代以降の重要な出来事も多くあります。たとえば1995年の「オウム真理教による新宿駅青酸ガス事件」、そして1945年の「九州大学生体解剖事件」です。
九州大学事件では、墜落した米軍B29の搭乗員が重傷を負い、救命措置の一環として大学病院に搬送されました。しかし、戦後GHQの裁定によって「生体解剖」と断定され、日本人が非人道的であるかのように国際的に広められました。
このような事例を通じて、あらためて皆様と共有したいことは、どこまでも「人間が主役である」という日本古来の価値観です。宗教も政治も思想も、人が幸せに生きるための手段であり、目的ではありません。
オウム事件にしても、教義が人間を支配するようになれば暴走は避けられない。人が人を大切にする、命に対して謙虚である──それこそが、戦後の歪みを見直す鍵です。
◉ 顔を隠す文化と「誠実な生き方」の対比
現代は、どういうわけか、マスクや前髪、サングラスなどで「顔を隠す文化」が生まれています。清潔感や安心感を求める一方で、それが人間関係における「誠実さの希薄化」につながっているのではないかと疑問に思います。
「顔を見せること」は、昔の武士にとっての覚悟の表れであり、武道やスポーツにおいても同様。誠実に、堂々と自分をさらけ出して生きる姿勢こそが、日本人が大切にしてきた精神だからです。
◉ 「2025年」から新しい時代へ
2025年は、時代の転換点でもあります。経済的には豊かでも、精神的には貧しくなってしまった現代。今こそ、日本人が本来持っていた「命を尊び、人を大切にし、共に生きる文化」を取り戻すべきときです。
「こどもの日」は、子どもたちの未来を守るだけでなく、大人たちが日本人としての原点を思い出す日でもあります。「人間が主役である社会」を取り戻す──その第一歩として、伝統行事や歴史の意味を今一度見つめ直すことが求められています。