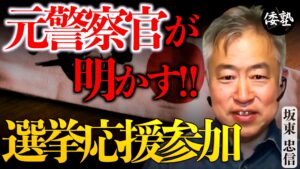1609年5月8日、琉球王朝は薩摩藩に降伏。だがその成立には、13世紀の朝鮮半島から逃れた武装勢力「三別抄」の移民が関係しているとの説がある。古代沖縄の文化とその断絶を通して、歴史の真相を考察します。
◉ 琉球王朝が降伏した「5月8日」の意味
1609年5月8日、琉球王朝は薩摩藩に降伏しました。この日は、いわば琉球王国の自主独立が終焉を迎え、日本本土と深く関わるようになる歴史的な転換点です。今回はこの日をきっかけに、琉球王朝の成立にまつわる可能性について、一つの仮説をご紹介いたしました。
◉ 三別抄とはどのような存在だったのか
「三別抄(さんべつしょう)」とは、13世紀の朝鮮半島に存在した武装集団です。当時、モンゴル帝国の侵攻によって高麗王朝の王族や官僚たちは逃げ出し、国家の統治機構が崩壊する中で、この三別抄が暴力団的な存在として各地を荒らしまわっていました。その後、元・高麗の連合軍に追われ、済州島に逃れたものの、1273年にはこの地でも壊滅したと伝えられています。しかしながら、武器と船を保有していた彼らが、さらに海を越えて琉球(現在の沖縄)へ移動した可能性は十分にあるのではないかという視点を持つことができます。
◉ 移民が築いた王朝という可能性
この三別抄の一部が沖縄に移り住み、自らの王朝を築いたという説は、学会の主流では否定的とされていますが、実際の文化的痕跡や社会構造の変化をみると、非常に興味深い一致点が見られます。たとえば、14世紀ごろから突如として沖縄に城塞都市が出現し、「按司(あじ)」」と呼ばれる支配階級が登場します。これらの構造は日本本土の村落共同体的な文化とは異なり、大陸や朝鮮半島に見られる専制支配的な特徴を有しています。
また、琉球の王朝が明王朝に対して冊封を申し出たのは、元が滅びた後であり、まるでモンゴルの支配が終わったことを確認してから新政権にすり寄ったような動きに見えることも注目すべき点です。さらに、「琉球」という表記も、もとは「流れを求める」と書かれ、明の時代に応援を加えて現在の「琉球」となったものであることから、王朝の成立そのものが後世的な政治的構築の可能性を示唆しています。
◉ 古代琉球=竜宮城だった可能性
そもそも「琉球」は、古代には「竜宮(りゅうぐう)」とも呼ばれていました。伊平屋島には「天岩戸」伝承が残っており、ここが高天原の一部だったという説もあります。つまり、琉球(沖縄)は、万年単位の歴史を有する海洋文化圏の中心地の一つであり、決して「何もない島」ではなかったと考えられるのです。
現在の地形や常識では理解できないことも、1万年〜2万年前の地質時代を視野に入れれば、例えば黒潮の流れによって自然に人と文化が移動したと考えることができます。足(あし)を使って編んだ船が行き交い、海を渡って魚を追うように移動していた人々が、琉球列島で文化を育んでいたとするならば、「竜宮」と呼ばれたのもうなずけます。
◉ 琉球王朝の文化と日本文化の違い
日本文化の根幹には「庶民を宝とする」考え方があります。対話と共生を重んじる村落共同体的な社会では、兵(つわもの)を巡らす文化は発達しません。そのため、日本本土の縄文遺跡などからは武器類がほとんど出土しないのです。
一方、琉球王朝では武器を保有する支配層「味(アジ)」が存在し、城郭を備えた都市構造が整備されました。これらはチャイナ文化や朝鮮半島文化に通じるものであり、日本本来の「非武装の民衆文化」とは対照的です。
その背景に、武装移民の流入があったとすれば、沖縄の伝統文化が大きく塗り替えられた可能性もあるわけです。実際、沖縄には武術である「空手」がありますが、これは「武器を取り上げられた民衆が、素手で戦う術を身に付けたもの」という伝承が残ります。どこかで聞いたような「被害者意識」による説明にも通じ、文化的な断絶の匂いを感じさせます。
◉ 結語──歴史を自らの頭で考えることの大切さ
今回ご紹介した「三別抄=琉球王朝移民説」は、あくまでも定説に対する一つの視点に過ぎません。しかし、史料や文化的背景、地理的条件を突き合わせていくことで、むしろこちらの説の方が現実味を帯びてくるのではないか──そう思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私たちが学校で学んできた「定説」は、時として政治的意図や近代国家の都合によって形成されたものであることもあります。だからこそ、歴史とは「資料を集め、自分の頭で推理し、仮説を立てて検証する」学問なのです。
琉球王朝と三別抄の話は、現代の沖縄が抱える分断的な社会構造──親日的な人々と反日的な人々の乖離──を理解するための一つの鍵ともなり得ます。台湾における本省人と外省人の違いとも類似点が見られます。
今回の配信では時間の関係上、概要のみをお伝えしましたが、今後は倭塾でこのテーマをより深く掘り下げ、古代日本文化の本質に迫る講義も行ってまいります。歴史の裏に隠れた真実を一緒に考察してまいりましょう。