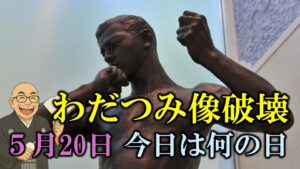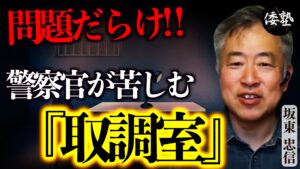5月21日の「小満」にちなみ、自然の恵みと人の営みの意味を考察。
小野小町の恋と和歌に込められた想い、そして民の力で創られた日本初の小学校の物語を通して、
教育と感謝の原点を見つめ直します。
◉ 二十四節気「小満」と自然の恵み
5月21日は二十四節気のひとつ「小満(しょうまん)」です。
草木が芽吹き、陽気が満ち、農作物が発芽し始めるこの日は、
「小さな満足」を感じる時節とされています。
自然に対する感謝と生命の息吹を感じる日として、
古来より日本人は季節の移ろいに心を重ねて生きてきました。
この「小さな満足」という感覚こそが、自然と共に生きる日本人の美徳であり、
現代の「もっともっと」という欲望主義とは対照的です。
◉ 小野小町と分野康秀の恋──千年を越える心の共鳴
905年のこの日、紀貫之らにより『古今和歌集』が撰進されました。
その中でも18首を収められた小野小町の和歌は、
時代を超えて人々の心に深く響きます。
小町と文屋康秀(ふんやのやすひで)の恋は、
「夢の中でしか会えない」切ない想いを連ねた連作和歌に描かれています。
たとえば──
思ひつつ寝ればや人の見えつらむ 夢と知りせば覚めざらましを
夢に現れた恋しい人が、現実にはいないことに気づいた時の切なさ。
この歌には、小町の「一緒にいたかった」という真心と、
康秀の「君を思いやって独りで去った」という優しさが交錯しています。
男女の考え方の違い、そしてそれでも消えない想い。
やがて小町が老いてもなお「女は女」として咲き誇る気概を詠んだ──
花の色は移りにけりないたづらに 我が身世にふるながめせしまに
この歌に込められた「美しさの本質」は、外見ではなく「心の華」にあることを教えてくれます。
◉ 日本初の小学校と民の力──教育の原点にあるもの
明治29年(1896年)の5月21日、京都市にて日本で最初の近代小学校──
「上京第二十七番組小学校」と「下京第十四番組小学校」が開校しました。
この小学校は、国の制度で設けられたものではありません。
まだ「学制」すら整備されていなかった時代に、
京都の町衆たちが自分たちの意思で立ち上げたものです。
土地の提供も、建設費も、すべて地域住民の寄付と労働によるもの。
「子どもたちに学ばせたい」「未来をつくる力を育てたい」
という純粋な想いが、この国の教育を先導したのです。
ところがその小学校は1998年に廃校に。
理由は「老朽化」と「少子化による効率性」でした。
強く伝えたいのはここ──
歴史を知ることは、感謝を知ること。
感謝を知ることは、教育の根幹。
校舎という物理的な建物ではなく、
そこに込められた「思い」や「営み」が、教育の本質なのです。
◉ 経済優先の先にある危機──効率よりも人の尊厳を
戦後日本は「経済性」と「効率性」を至上のものとして突き進んできました。
その結果、失ったものもあります。
地域の絆、文化、そして心の豊かさ──。
教育とは本来、人を育て、心を養うもの。
経済的価値で換算されるべきものではありません。
だから、断言します。
日本が目指すべきは、効率化ではなく「心の国づくり」である。
民を「おほみたから」とする“シラス国”の理念に立ち返り、
誰もがまっすぐに生きられる社会を築くことこそ、本当の国の豊かさです。