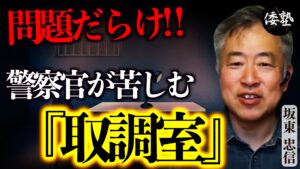江戸時代、禅海和尚が30年をかけて掘り抜いた「青の洞門」。その一念が人々の命を救い、後の時代にも影響を与えました。この偉業を通じて、現代の私たちが学ぶべき「根本から変える力」を語ります。
◉ 禅海和尚が拓いた「命の道」── 青の洞門の物語
江戸中期、越後高田藩の武士・福原市九郎は、両親を早くに亡くした悲しみをきっかけに出家し、禅海と名を改めます。修行の旅の中で訪れた耶馬渓の断崖絶壁。そこに通された「青の渡し」は人も馬も命を落とすほどの危険な道でした。禅海はその現実を見て、「人々の命を守るために、新しい道を掘ろう」と決意。たった一人、ノミと金槌を手に岩山に向かい、掘削を始めます。
最初は資金も仲間もおらず、村人たちからは「無謀だ」と笑われます。それでも彼は日々ひたすら岩を叩き続け、托鉢で得たわずかな糧で身を支え、黙々と岩と向き合いました。やがて小さな成果が見え始めたとき、村人たちも「手伝いたい」と声をかけ、支援が広がっていきます。最終的には中津藩のみならず周辺諸藩も協力を申し出、1763年、ついに全長340メートル、高さ6メートルの立派な隧道「青の洞門」が完成しました。これが日本最初の有料道路とされます。
◉ 現代日本に通じる「三つの教訓」
禅海和尚の偉業には、現代日本にも通じる三つの大きな教訓が込められています。
1. 誰かのために生きると決めた「一念」は、30年を貫く力になる
自分のためではなく、人のためと決めたとき、人間は想像を超える持続力を持つことができます。
2. 自ら鍬を取り、行動を始めた者にこそ、仲間と支援が集まる
禅海はただ「困っている」と嘆くのではなく、自ら行動したことで、人々の心を動かしました。
3. 目の前の困難をどう捉えるかで、未来は変わる
「危険だから仕方ない」と諦めるのか、「何かできることがある」と考えるのか。その違いが大きな時代の分かれ目になるのです。
◉ 「誰の手を待つまでもなく、私たちの手で」
この日(5月22日)は、実は「ガールスカウトの日」でもあります。もともとは1920年に「日本女子補導団」として始まり、戦後、1947年に再始動したこの運動の合言葉は──
「誰の手を待つまでもなく、私たちの手で、未来を担う少女たちを育てよう」
この言葉は、まさに禅海和尚の行動とも通じるものがあります。待つのではなく、自分から始める。未来は、自らの意志と行動によってこそ拓かれるのです。
◉ 日本再生への原点回帰
現代の日本も、まさに「断崖の道」に立たされているような時代です。政治、経済、教育、社会、それぞれが行き詰まりを見せています。しかし、かつて終戦直後の焼け野原から復興したように、私たちには「立ち上がる力」があります。
そのためには、日本という国の「根っこ」、すなわち「国柄」に立ち返ることが不可欠です。
「誰もが豊かに、安全に暮らせる国」
「喜びあふれる楽しい国」
それが、歴代の天皇陛下が目指してきた「シラス国」の姿であり、日本人が培ってきた精神です。
この30年間、多くの政策や議論が交わされましたが、本質的な変化は乏しいままです。それは、私たちが「根っこ」を見失ってきたからではないでしょうか。今こそ、行動の原点に立ち返るときです。
*
私たち一人ひとりが「掘るべき道」を見つけ、ノミを手に岩に向かう──そういう意識こそが、日本を再びよみがえらせる鍵となるはずです。