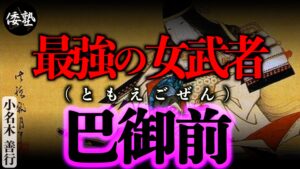鹿児島・屋久島で発見された縄文杉は、アカホヤ噴火を経てもなお生き続けています。その存在は、縄文文明の精神がいまなお連綿と受け継がれている証です。
◉ 縄文杉発見──屋久島の森に宿る時の記憶
1966年5月28日、鹿児島県屋久島で、ひときわ大きく荘厳な屋久杉が発見されました。それが今日「縄文杉」と呼ばれる一本の巨木です。発見当初は命名も定まっておらず、「大株主」や「大王杉」といった名が候補に挙がっていましたが、やがてその樹齢や存在感から「縄文杉」の名が定着しました。推定樹齢は2000年以上とも、場合によっては7200年を超えるともいわれ、まさに縄文時代からこの地に立ち続けてきた“森の守人”です。
屋久島という場所そのものが、降水量の多い特殊な環境下にありながらも豊かな生命を育んでおり、杉の木は数百年をかけてゆっくりと成長し、過酷な環境に耐えながらその寿命を重ねてきました。特に、縄文杉が立つ高地地帯は、台風や降雨の直撃を受けやすく、樹木にとっては極めて過酷な条件です。それでも生き延びたという事実そのものが、奇跡とさえいえるのです。
◉ 倒木更新と「命の継承」
縄文杉の樹齢については、一本の幹から年輪を数えるだけではなく、倒木の上に新しい命が芽吹く「倒木更新」という仕組みがあるため、目に見える木そのもの以上に命の歴史が古い可能性があります。つまり、いま立っている縄文杉は、その根元にある前世代の木々の命の“延長”として生きているとも言えるのです。
これは、単に生物としての繁殖ではなく、「つながりの中で命が受け継がれていく」という、まさに縄文的な自然観を体現している現象です。日本人が古来より大切にしてきた「命はつながり、重なり合っていくもの」という感覚は、この一本の杉の中にも宿っています。
◉ アカホヤ噴火とヤクシマザル──災害を越えて生きる力
約7300年前、九州南部では史上最大級の火山噴火とされる「アカホヤ噴火」が起こりました。屋久島もその影響を強く受け、火山灰に覆われた地層がいまも残っています。通常であれば生態系が壊滅するほどの破壊力ですが、それでもなお生き残った動植物たちが存在しました。
代表的なのが「ヤクシマザル」です。彼らは食物の乏しい過酷な環境下でも、仲間との協調を通じて生き延びてきました。人間においても、縄文人たちはこのような自然の猛威の中で、森と共生し、災害を乗り越えて文明を継続してきたのです。
つまり、縄文杉とは「災害を超えてつながれてきた命の象徴」であり、「縄文文明は決して過去のものではなく、今もなお私たちの中に生きている」ということを教えてくれる存在です。
◉ 縄文文明は“消滅していない”
一般的には、弥生時代の到来とともに縄文文明は終わったとされていますが、精神文化や自然観といった“見えない財産”は、実は今も私たち日本人の生活や価値観に深く根付いています。
自然を神と捉え、感謝し、共に生きるという感覚。権力で支配するのではなく、関係性で治めるというリーダー像。そして、「命は天から預かったものであり、自分のものでさえない」という生命倫理──こうした縄文的世界観は、まさに今の混迷した時代にこそ再び注目すべきものです。
縄文杉は、その静かな佇まいのなかで、そうした思想と歴史を語り続けてくれているように思います。