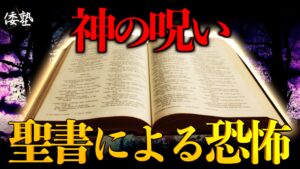田村匡俊先生が立ち上げた現代版寺子屋「あけぼの」は、歴史を通じて子供たちに日本人の誇りと自己肯定感を育てる教育の場。教科書の枠を超えた本質的な学びが、子どもも大人も変えていきます。
■ 教科書では育たない「誇り」と「志」──田村先生が寺子屋を始めた理由
田村匡俊先生は、国交省のエリートキャリアから転身し、小中学校の教員として17年間、子どもたちに寄り添ってきました。
しかし、戦後教育の現場において自虐史観の歴史教育を強いられる中で、子どもたちの自己肯定感が低くなり、誇りを持てなくなっている実態を目の当たりにし、「このままではいけない」との想いから、現代版の寺子屋「あけぼの」を立ち上げる決意を固めました。
寺子屋の目指すところは、ただ知識を詰め込むのではなく、歴史を通して「日本人であることを誇りに思う心」と「自ら考え、自ら動く志」を育むこと。教科書通りの授業では伝えきれない“本当の日本”を伝えることに情熱を注いでいます。
■ 本物の教育が子どもを変える!──寺子屋のカリキュラムと驚くべき効果
寺子屋あけぼのでは、週1回60分の授業をオンラインで実施。
小学校高学年から大人まで参加でき、内容は歴史・偉人伝・志教育に加え、哲学的な問いかけやディスカッションも含まれます。
西郷隆盛と大久保利通、どちらを支持するか?という問いに、小学生たちが自分の意見を持ち、議論に参加する様子は、まさに生きた学びの現場です。
ご父兄や社会人も授業に参加し、子どもと大人が共に学ぶ姿がそこにはあります。
実際に参加した子どもたちは、数か月で自己表現ができるようになり、「自分の国を守りたい」「選挙に行きたい」「日本をもっと良くしたい」と発言するようにまで変化しました。
その成長ぶりは、寺子屋での教育が単なる“学力”ではなく、“人間力”を養うことを証明しています。
■ 寺子屋教育が導く未来──「誇りある日本人」を育てる場
田村先生の授業を受けた子どもたちの感想は、どれも胸を打つものばかりです。
「ご先祖様の生き方を知り、自分にもできることがあると思えるようになった」
「今の大人が無関心なのは、教育とメディアの責任だと気づいた」
「歴史から道徳を学び、社会に貢献する自分になりたい」
こうした言葉は、小学6年生が書いたとは思えないほど力強く、大人顔負けの志に満ちています。
自虐史観に縛られた戦後の教育では、決して育てることのできない「誇り」「感謝」「志」「行動力」。それを現代の寺子屋は、子どもたち一人一人に芽生えさせているのです。
さらにこの寺子屋は、単なる“塾”ではありません。
大人も参加できる「共育」の場であり、「学び直し」の場でもあります。YouTubeや本では得られない“生きた対話”が、そこにはあるのです。
■ 結びに
「学びを楽しく」を実現する場として、寺子屋あけぼのは、今後ますます重要な存在となるでしょう。
子どもに誇りを、大人に気づきを、日本に未来をもたらすこの活動を、ぜひ一度体験してみてください。