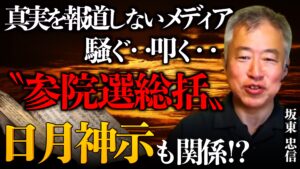米価高騰に端を発した大正時代の米騒動。その背景には、吉野作造の唱えた民本主義の思想がありました。国民の幸福を政治の中心に据えたこの考え方が、今こそ再評価されるべき理由を解説します。
女たちが動いた!──富山発「女米騒動」の衝撃
1918年7月23日、富山県魚津の主婦たちが県外への米の移出に抗議して起こした集団行動。これが全国へ波及し、日本中を揺るがす「米騒動」となりました。背景には、国内の米の自給体制が崩れたことや、米価の急騰がありました。当時、日本は米の輸入をほとんど行っておらず、政府も地方自治体も1年分の備蓄しか持っていなかったため、天候不順などによってすぐに供給不足に陥ってしまったのです。
この富山の「女米騒動」は、ただの生活苦による暴動ではありません。家族の食卓と未来を守るために立ち上がった女性たちの声は、やがて国家全体の在り方を問い直す動きに発展していきました。
民主主義じゃない?吉野作造の「民本主義」とは
この米騒動の背景には、よく「民本主義の普及が反政府的な機運を高めた」とする言説がありますが、これは誤解を招きやすい表現です。民本主義を唱えた吉野作造が主張したのは、「政治の主権は天皇にありながら、その目的は国民の幸福にある」という考え方です。
民本主義は、政治の正当性を「誰のための政治か?」という視点で問います。すなわち、政治家は国民を豊かに、安全に、幸せに暮らせるように努める「奉仕者」でなければならないという姿勢なのです。
吉野は「君主君本でも民主民本でもない、日本は君主民本の国である」と述べ、日本の国体にふさわしい形として民本主義を提示しました。彼は、神話的な国体論だけでは現代の青年は動かせないとし、合理的かつ倫理的に日本の使命を説いています。
「民本主義」は今も生きている──現代への問いかけ
民本主義は反政府運動ではありません。それは「話し合いと選挙による穏やかな改革」を目指す思想です。吉野作造の主張は、現代の私たちにも大きな示唆を与えてくれます。国民の生活が困窮し、権力や資本が一部の手に集中するような政治体制が続けば、人々は政治に関心を失い、社会の活力は失われます。
だからこそ、「国民こそが宝である」「政治の目的は国民の幸福である」という民本主義の原点に立ち返ることが求められます。話し合いと共鳴を重視するこの日本的な価値観は、分断の時代にこそ力を持ちます。
倭塾では、「議論ではなく“話し合い”を」「支配ではなく“共に支え合う”」という姿勢を大切にしています。今こそ、吉野作造のまなざしと主張に、もう一度耳を傾けてみましょう。