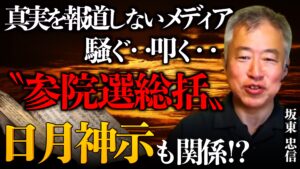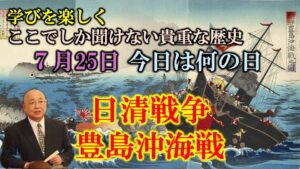『ガロ』創刊による劇画文化の誕生、桓武平氏の起源、清涼殿落雷、バテレン追放令、そして航空戦艦「日向」の最後の砲撃──歴史の深層を通じて日本の国防と未来を考えます。
1.劇画の誕生と『ガロ』の革新性
1964年7月24日、日本の漫画文化に革命をもたらした雑誌『ガロ』が創刊されました。白土三平の『カムイ伝』や水木しげるの『鬼太郎夜話』、つげ義春の『ねじ式』など、リアリズムと個性が爆発する作品群が大人たちをも惹きつけました。みうらじゅん氏は、「漫画はガロ系とそれ以外に分けられる」と評するほど、その影響は計り知れません。
一方で、出版業界の保守・革新の偏向についても触れられ、保守系出版社が図書館に置かれない不条理さや、思想による扱いの差についても問題提起されました。
2.7月24日の歴史の節目──桓武平氏、雷、宣教師
この日はまた、825年に桓武天皇の孫・高棟王が「平」姓を賜った日であり、桓武平氏の始まりとなりました。これは後の平清盛などへとつながる武家の出発点です。
930年には清涼殿に落雷が走り、公卿2名が即死するという事件が起こり、これが菅原道真の怨霊とされ、後の天神信仰の出発点となったと語られます。
さらに1587年には豊臣秀吉による「バテレン追放令」が発令されました。背景には、宣教師を装って日本人女性をヨーロッパに奴隷として売るなど、一部の西洋人による非道な行為がありました。
ただし、すべての宣教師が悪であったわけではなく、信仰心篤く誠実な宣教師が大多数であったことも事実。そのうえで、わずかでも危険な要素を持つ存在を許せば、国を蝕むことになりかねないという秀吉の決断は、素晴らしいものと言えます。
3.航空戦艦「伊勢」「日向」──神話の名を持つ姉妹艦の最期
昭和20年7月24日、呉軍港への米軍空襲により、航空戦艦「日向」と「伊勢」が沈められました。特に「日向」は、この日、日本海軍として最後の主砲を放ちました。
伊勢・日向は当初、扶桑型戦艦として計画されたものの、大正デモクラシーの中で国会の予算が通らず、結果として装備不十分な“使えない艦”とされ、練習艦扱いとなります。しかし後に、空母の不足を補うために後部を空母化した「航空戦艦」として改装されました。
離陸は可能でも着艦できない構造は非効率そのものでしたが、その分、強力な対空砲火を備え、レイテ沖海戦などで百機近い敵機を撃墜するなど、活躍を見せました。
戦争末期、燃料もなくなり、呉で海上砲台となった両艦に対し、米軍機が襲来。「日向」は最後の主砲を放ち、その砲撃の風圧によって複数の敵機を墜落させたとされます。これは日本帝国海軍最後の主砲発射となりました。
「伊勢」は天照大神、「日向」は天孫降臨の地の名──ともに神話に由来する姉妹艦は、最後の最後まで祖国を守り抜いたのです。
4.歴史の教訓と現代日本への提言
本ライブでは、こうした史実を通して「国家とは何か」「国防とは何か」を問い直しました。
過去の歴史を見ると、白村江の敗北、元寇、戦国の乱といった混乱の果てに、日本は大きな復活を遂げてきました。神々は混乱の中で私たちに「学びと再生」の機会を与えてくださっているのです。
また、現代の政治課題として、通貨発行と金利、財政の構造改革についても言及。必要な通貨を必要な形で発行することや、金利の在り方を見直すことの重要性が語られました。強い改革には正しい理解と段階的な実行が不可欠であること、そしてそのためには学びと対話が必要だというメッセージで締めくくりました。