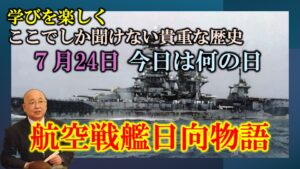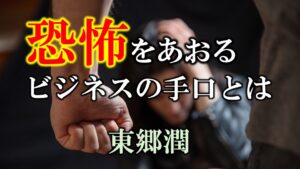日清戦争のきっかけとなった豊島沖海戦では、清国の奇襲に対し日本海軍が圧倒的勝利を収めました。無法な挑発と情報戦に晒されながらも、国際法に則った対応で世界の理解を得た日本の姿が明らかになります。
清国の無法な挑発と始まった戦い
1894年7月25日、豊島沖にて日本海軍の巡洋艦が清国の軍艦「済遠」「広乙」と遭遇しました。通常であれば挨拶程度で済む距離でしたが、午前7時52分、突如として清国側が日本に向けて砲撃を開始。これはまさに国際法を無視した無法行為であり、日本側はやむなく応戦することになります。
逃走を始めた清国軍艦に対し、日本の「吉野」「秋津洲」「浪速」が追撃を開始します。「広乙」は座礁し、「済遠」は降伏を装っては逃げ、イギリス船籍を掲げた「高陞」に紛れ込みながら最終的に逃走しました。
東郷平八郎の決断と国際社会の目
この海戦で東郷平八郎大佐の指揮する「浪速」は、逃げる「高陞」を撃沈し、その乗組員である英国人と清国兵を丁寧に救助しました。日本側に死傷者は一人もおらず、艦船の損害もゼロ。圧倒的勝利でした。
しかし、清国は「済遠は日本に一方的に攻撃された」「高陞は英国船籍であった」と国際社会に虚偽の情報を流布。日本は非難される状況となりますが、イギリスの国際法学者ホランドとウェストレーキが、日本の行動は国際法に適っており違法性がないと明言したことで、日本の正当性が証明されます。
歴史から学ぶべき、毅然とした対応
この海戦を契機に、8月1日には明治天皇から宣戦布告の詔勅が発せられ、日本と清国の全面戦争へと発展します。ですが実際には、日本は清の繰り返される挑発を受け、やむを得ず戦闘に至ったことが明らかです。日清戦争の勃発は日本からの侵略ではなく、自衛のための応戦であったことが事実として確認されます。
この一連の出来事から、日本がどれほど戦争を避け、外交努力を重ね、最終的には正々堂々と対応したかがよく分かります。いっぽう清国は、軍艦に英国の旗を掲げて逃げるような卑怯な行動を繰り返しました。こうした事実こそが、いまの教育現場でも正しく伝えられるべき歴史なのです。
「最高気温の日」と「かき氷の日」──時代は変われど夏の風景
余談ながら、7月25日は「最高気温の日」でもあり、1933年のこの日、山形市で40.8度が記録されました。以降、41度台が各地で記録され、猛暑は年々激しさを増しています。そしてこの日は、「かき氷の日」でもあり、「な(7)つ(2)ご(5)おり」という語呂合わせと、この暑さをしのぐ風物詩として制定されました。
文明が進んでも、自然の猛威とそれを楽しむ知恵──氷の甘さに涼を求める日本人の夏の感性が今も生きています。