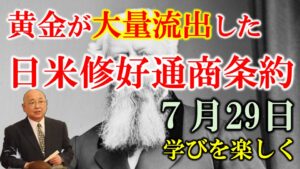1950年、GHQの指令によって始まったレッドパージにより、報道機関や企業から共産主義者が大量解雇されました。裁判所は「GHQの指示には従う義務がある」と判示し、憲法の上にGHQが存在する体制が固定化されました。ねずさんは、この“見えない支配構造”の継続に警鐘を鳴らし、日本人の意思による政治を取り戻す必要性を語ります。
1.「今日は何の日」からはじまる、地域の違いと心の温かさ
7月28日は、ちょっとユニークな記念日でもあります。
その名も「大判焼きの名前を皆で議論する日」。
あんこやクリームの入ったあの丸いお菓子、私の故郷では「今川焼き」と呼ばれていましたが、調べてみると日本各地でまったく違う名前があるんですね。
北海道では「おやき」、東北や中部では「大判焼き」、関西・九州では「回転焼き」、兵庫では「御座候」……などなど。
これだけ呼び方に地域性があるというのは、日本ならではの豊かさであり、日常に潜む「違い」を楽しむ心が生きている証拠でもあります。
こうした話題を通して、私は“地域の多様性”というものが、実は私たちの国家観や独立観にも通じていると感じるのです。
2.レッドパージ──戦後日本に刻まれた「超憲法構造」
さて、今日の本題です。1950年(昭和25年)7月28日、この日、日本の報道機関などにおいて「レッドパージ」が始まりました。
たった1日で、朝日新聞社から72人、毎日新聞社49人、NHKでは104人が一斉に解雇されました。
“共産主義者”またはそのシンパとされた人々が追放されていったのです。
この動きの背景にあったのは、GHQ──つまり連合国軍最高司令部の指示です。
もともとGHQは、日本占領前から23万人分のリストを用意し、日本的な精神を持つ人々を先に公職追放しました。
その上で、戦前に共産主義思想によって特高警察に収監されていた人物を大学教授やマスメディアへと登用していきました。
その結果、戦後の報道機関には保守的な人物は姿を消し、共産主義的傾向をもつ人々が影響力を強めていったわけです。
このような統治の仕方は、典型的な「植民地型の間接統治」と言えます。
言語も文化も理解できない外国人による支配を成り立たせるには、その国における“少数派”や“異分子”を特権階級に据え、彼らを媒介に支配するのが常套手段です。
実際、GHQは当初、国内に不満や恨みを持つ勢力、つまり日本社会で冷遇されてきたような立場の人々に特別な権限を与え、統治を行いました。
そこには「治外法権」のような扱いも含まれており、たとえ乱暴や不法占拠を行っても、警察が手を出せないという異常な状態が広がっていきました。
3.「GHQの指示に従うしかなかった」──日本司法の判断と戦後体制
その後、GHQ内部でも「このままでは日本社会が崩壊する」との危機感が生まれ、
“利用された”はずの共産主義者や一部外国系勢力への締め付けが始まります。
レッドパージはその象徴的な出来事の一つでした。
ここで重要なのは、後年の日本における裁判所の判断です。
主権を回復した後の1952年「共同通信事件」や1960年「中外製薬事件」では、
レッドパージによって解雇された人々が裁判を起こしましたが、いずれも原告敗訴となり、
判決では「GHQの指示に日本政府は従う義務があった」と明言されました。
これはつまり、「憲法よりもGHQの命令が優先される」ことを日本の司法が認めたということです。
しかもこの考え方は、2004年〜2013年の訴訟においても変わりませんでした。
2008年には日弁連から人権救済の勧告も出ましたが、裁判所は「GHQの指示があった以上、従うのは当然」として原告の請求をすべて棄却しました。
この一連の流れを見れば、戦後の日本が、いかに“外からの指示でしか意思決定できない構造”になっていたかがよくわかります。
4.戦後体制の構造は、今なお続いている
私は、ここに日本という国家の根本的な課題があると考えています。
つまり、私たちは今もなお「日本人の意思で物事を決められない国」に生きているのではないか、ということです。
国会、内閣、裁判所――三権分立の上にあるべき憲法。
しかし、戦後の日本ではその憲法のさらに上に「GHQ的な意思」が存在し、今日に至るまで多くの分野に影響を残しています。
かつてはそれを「アメリカ」と呼びました。
近年はそれに「グローバリズムの圧力」が加わっています。
国際機関の“指導”や“合意”という形で、日本の政策が外から左右されている現実を、私たちは直視しなければなりません。
5.世界は変わりはじめている──日本もまた、自ら動くとき
一方、世界はすでに動き出しています。
アメリカではトランプ政権の登場によって「自国優先主義」への揺り戻しが起き、
ヨーロッパでも同様に「自国の文化や歴史を大切にしよう」という政党が台頭しています。
これは、単なる「右か左か」の話ではありません。
これまで“グローバリズム”という名のもとに進められてきた支配構造への、民衆側からの明確な「NO」なのです。
日本もまた、その流れと無関係ではいられません。
“公職追放”や“レッドパージ”が過去の話でないのなら、
“自国で決められない体制”もまた、過去の遺物として清算していく時期に来ているのではないでしょうか。
6.結びに──日本らしい交渉と未来への道
最後に、私はこう申し上げたいのです。
アメリカと日本では、交渉のスタイルも文化も異なります。
アメリカは「25%だ、従え」と迫るビジネスを好むかもしれません。
しかし日本には、日本ならではの“和をもって貴しとなす”交渉術があり、
それは人と人とが信頼を通じて物事を前に進めていく美しい文化です。
私たちは、その文化を胸に、日本人の手で未来を描いていく。
それができるのだと、心から信じています。