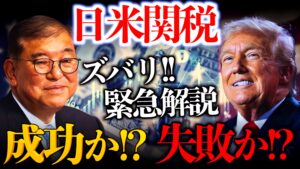1858年の条約により、銀4枚で日本の金1枚と交換できる異常な比率が発生し、膨大な黄金が海外へ流出。アメリカはその資金で南北戦争を勝利に導き、アラスカ買収やフィリピン侵略に繋がりました。
◆ 幕末日本の通貨を襲った“罠”──条約第5条の衝撃
1858年7月29日、江戸幕府はアメリカとの間で「日米修好通商条約」を締結しました。
この条約は、港の開港や輸出入に関する規定など、おおむね友好的な内容でしたが、実は第5条にとんでもない“罠”が仕込まれていました。
それが、「外国通貨と日本通貨は、同種・同量で流通させる」という条文でした。
これは、金貨は金貨と、銀貨は銀貨と同じ量で交換できる、という約束です。
一見公平な内容のようですが、当時の国際的な金銀比価(1:15.3)と、日本国内の比価(1:4.65)には大きな差がありました。
その結果、たった銀4枚で日本の金貨1枚(=小判)と交換できるという“錬金術”が成立しました。
この条文により、米国は、日本から莫大な黄金を手に入れることに成功したのです。
◆ 流出した黄金はどこへ?──南北戦争・アラスカ買収・フィリピン侵略へ
幕府が気づいたときには、手遅れでした。
条約締結から3年後、アメリカでは南北戦争が勃発。
なんとこの戦争で、北部軍は大量の金貨を戦費にあてて勝利し、ヨーロッパからの外債もすべて黄金で完済してしまいます。
こうしてアメリカは、国際的な信頼と経済力を一気に獲得。
さらに1867年には、財政難のロシアからアラスカをたった720万ドルでキャッシュ購入。
1平方キロメートルあたり5ドルという破格で手に入れたこの地は、のちに漁業・資源ともに“天国”のような場所となっています。
そして1902年、アメリカはスペインから奪ったフィリピンで、数十万人の民間人を虐殺して植民地化。
南北戦争で得た経済力が、そのまま帝国主義の礎となっていったのです。
◆ 黄金の流出と日本の命運──歴史は“つながっている”
こうした歴史を振り返ると、日米修好通商条約における第5条が、単なる経済的損失ではなく、日本の主権と国力を大きく削ぐ出来事であったことが見えてきます。
幕府の信頼は失墜し、やがて明治維新へと至る伏線となりました。
また、同日には「保元の乱」や「大化の改新」といった、大きな転換点となる出来事も歴史上起こっており、日本にとって“変革”の日でもあります。
さらに、日本人の責任感と誠実さを象徴する逸話として、日清戦争のラッパ手・木口小平の「死んでもラッパを口から離さなかった」話も紹介されました。
彼の行動には、日本人が共有する“関係責任”の美徳が表れており、戦後の歴史教育では教えられなくなったものの、いまこそ再評価されるべき精神であると語られました。
🌸結びに
現在の国際政治や通貨制度、そして日本の自立や未来を考える上で、幕末のこの一条約がいかに深い影響を与えたかは計り知れません。
歴史を知ることは、未来への羅針盤です。
日本の誠実さと、アメリカの現実主義──その狭間で見失われた“黄金”を、私たちは今一度見つめ直す必要があるのではないでしょうか。