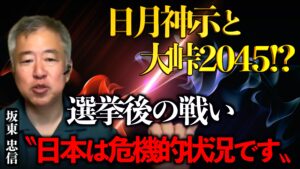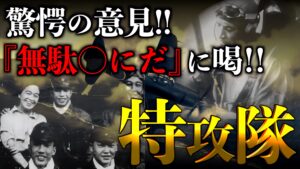食物に囲まれながら餓死した日本兵。その姿に刻まれていたのは、誇りと礼節の心でした。補給の実態、報道の偏り、そして日本人の精神性について、立秋の日に改めて問いかけました。
◆ 立秋の朝に、戦場の記憶を語る
8月7日は、二十四節気の「立秋」にあたります。今年2025年は、午後2時52分にその瞬間を迎えました。この日から「残暑お見舞い申し上げます」となり、暦の上では秋が始まることになります。語呂合わせで「花の日」「鼻の日」とも言われ、浅草の「花やしき」が170周年を迎える節目の日でもあります。
そんな日だからこそ、朝の放送では、南太平洋の島・ガダルカナルで始まった戦いの記憶を、あらためて皆さまと共有させていただきました。
◆ ガダルカナル島──補給を断たれた戦場
1942年8月7日から翌年2月7日まで続いたガダルカナル島の戦い。私はこの戦いにおいて、当時の報道や教育が私たちに植えつけたイメージと、実際の歴史的事実とのあいだに、大きな隔たりがあると感じています。
例えば「日本軍は補給を怠った」とよく言われますが、実際には38隻もの日本艦艇が失われており、そのうち多くが兵員や食料を運ぶための輸送船でした。米軍によってそれらが次々に沈められた結果、補給が物理的に「断たれた」のです。
航空機の損失数も、日本側683機、米側615機と拮抗していました。限られた資源と人員の中で、日本軍がどれほど奮闘したかは、この数字からもうかがえるはずです。
◆ 椰子とバナナに囲まれて──なぜ日本兵は餓死したのか?
ガダルカナル島には、椰子の木も、バナナの木も、豊かに実っていました。にもかかわらず、日本兵の多くが餓死しています。
理由は明確です。
島の人びとは、土地の所有という意識をあまり持ちませんが、それでも「この椰子の木は誰のもの」といった認識はしっかりとあります。日本兵たちは、それを理解していました。そして、「人様のものに手を出してはならない」という当たり前の感覚──すなわち“恥の文化”を持っていたのです。
椰子の実が目の前にある。手を伸ばせばココナツジュースが飲める。けれど、それが「島の人のもの」である限り、どんなに飢えていても、彼らは手を出さなかった。だから餓死しました。
私が心を打たれるのは、帰還兵の誰一人として「俺は椰子の実を盗らなかった」と誇らしげに語っていないことです。なぜなら、それは誇ることではなく、彼らにとって“当然のこと”であったからです。
◆ 天岩戸の教え──暗闇に光を取り戻す力
戦争の悲惨さを語るだけなら、それは過去をなぞるだけの話になります。でも私は、そこから「何を学ぶか」が大事だと思っています。
神話の中の「天岩戸隠れ」の物語──世界が暗くなったとき、神々は誰も悪口を言わず、ただ明るく、楽しく、称賛と喜びで太陽の女神を呼び戻しました。
今の世の中も、闇に包まれているように感じることがあります。だからこそ、明るく、朗らかに、他者の良さを見つけ、心に灯をともしていくことが求められているのではないでしょうか。
私も、先輩から教わって、かつて部下の良いところを毎日50個挙げるという習慣を続けたことがあります。最初は大変でしたが、それを続けるうちに、店内が明るく、希望に満ちたものとして見えてくるようになりました。
◆ 結びに
人は、極限状態でこそ「本性」が問われます。
「人のものには絶対に手をつけない。
どんなに美味しそうなものが目の前にあっても、
それは他人様のものだから。」
ガダルカナル島の日本兵たちは、腹が減っても、人様のものに手を出しませんでした。
その誇り高さ、礼節、そして思いやりこそが、日本人が大切にしてきた魂であり、今に伝えたい“生き方のかたち”だと思っています。
彼らの犠牲の上に、私たちの今がある。
そのことを、立秋の朝に、感謝とともに胸に刻みました。