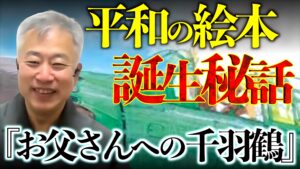昭和12年8月13日、第二次上海事変が勃発しました。当時のチャイナ情勢は国ではなく軍閥が割拠する状態であり、そこに至る背景や、「歴史を持つ国」とは何かを解説し、日本人が事実に基づく歴史認識を持つことの大切さをお話しします。
■ 歴史を持つ国と失った国
歴史とは、過去の事実を正確に把握し、時系列に沿って物語として構築する営みです。世界において、体系的な歴史を継承してきた国は多くなく、西洋史・東洋史(中国史)・日本史の三系統が代表的です。
インドは500年にわたるイギリス植民地支配で1500年代以前の記録をほぼ失い、沖縄も戦後のアメリカ統治下で14世紀以前の琉球史が教育から消されました。アフリカ諸国も植民地化により歴史の多くを失い、遺跡など断片的な痕跡しか残っていません。
こうした中、日本は天皇を中心とした一貫した歴史を今日まで受け継いできた、世界でも稀有な国の一つです。
■ 第二次上海事変の背景と真実
1937年(昭和12年)は、盧溝橋事件、大山中尉惨殺事件、通州事件など日中間の衝突が続発した年でした。その中で8月13日、第二次上海事変が勃発します。
当時のチャイナは統一国家ではなく、蒋介石の国民党軍閥と毛沢東の共産党軍閥などが乱立し、暴力で支配する状態でした。これを国と国の「戦争」と区別して、日本ではこの出来事を「支那事変」と呼びました。
日本が派兵したのは、軍閥の暴力に苦しむ市民を守るための平和維持活動であり、上海には米・英・仏なども治安維持のために駐留していました。
事変後、日本軍は上海派遣軍を上陸させ国民党軍を撃退しましたが、南京へ退いた国民党軍が市民に対して暴虐を働く悲劇が起こりました。
「日本が侵略目的で中国に出兵した」というのは、戦後のプロパガンダによる印象操作であり、史実とは異なります。
■ 歴史認識と日本人の姿勢
「日中戦争」という呼称は、当時の日本と中国が国同士で戦ったかのような誤解を与えます。昭和12年のチャイナは国家ではなく軍閥支配下であり、相手が国でない場合は「事変」と呼ぶのが正確です。
歴史は「正しい・正しくない」で争うのではなく、まず事実を確認することが重要です。解釈は人によって異なりますが、事実が誤っていれば解釈もまた成り立ちません。
また、日本と西洋・チャイナでは「武力」と「暴力」の概念も異なります。日本では武力は正義のための力、暴力は不当な力と区別しますが、欧米やチャイナではいずれも「パワー」「バイオレンス」として区別されません。この認識差も歴史理解の齟齬を生みます。
歴史を連綿と継承してきた日本人は、事実に基づく歴史観を持ち、共感と響き合いで未来を築く責任があります。怒りや憎しみではなく、天岩戸開きの神話のように、明るく笑顔で人心を開く姿勢こそが、日本人の本領です。