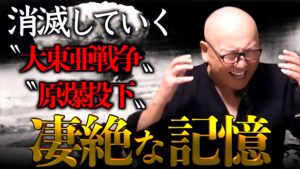昭和20年8月18日、ソ連軍が占守島に侵攻しました。池田末男聯隊長率いる士魂部隊は奮戦し、女子工員の避難と北海道の防衛に大きな役割を果たしました。その意義を振り返ります。
士魂部隊と池田聯隊長の人柄
昭和の軍人の多くに厳しい評価を下した司馬遼太郎が、唯一尊敬を寄せた人物がいます。戦車学校校長を務め「戦車隊の神様」と呼ばれた池田末男少将です。彼は豪放磊落で温厚ながら、信念の強さと人間的な魅力で部下に慕われていました。
占守島駐屯時、池田聯隊長は自分の下着を決して当番兵に洗わせず、氷のように冷たい水に自ら手を入れて洗濯しました。当番兵が「それは私の仕事です」と声をかけると、「お前は私に仕えるのではない。国に仕えているのだ」と答えた逸話は、彼の姿勢をよく表しています。部下はこの言葉に胸を打たれ、心から信頼を寄せたと伝わります。
終戦直後の占守島侵攻
昭和20年8月15日、日本は降伏を宣言しました。しかし戦いはすぐには終わりませんでした。8月17日深夜、濃霧の中、不気味なエンジン音とともに国籍不明の舟艇が占守島に迫ります。やがて数千の兵士が上陸し、銃火が夜を切り裂きました。相手はソ連軍でした。
日本側は武装解除の途上にあり、迎え撃つ兵力はわずかでした。それでも必死の抵抗でソ連の舟艇や艦艇を撃沈します。しかし敵は圧倒的多数であり、次々と上陸を果たしました。このとき島には女子工員400名を含む日魯漁業の従業員がおり、師団は「女子工員を必ず北海道に送り届けよ」と決断。砲撃と航空攻撃の中、漁船で避難させ、全員を無事に北海道に送り届けることに成功しました。これは兵士たちにとって大きな安堵と誇りとなりました。
一方で戦車第十一聯隊、通称「士魂部隊」は天神山に集結します。池田聯隊長は全隊員に「白虎隊たらんと欲するか」と問いかけました。霧が晴れ、兵士たちが一斉に挙手する姿が月光に浮かび上がりました。全員が死を覚悟して立ち上がったのです。
壮絶な戦いと歴史的意義
8月18日午前6時50分、池田聯隊長が日章旗を振り下ろし、士魂部隊は四嶺山に突撃しました。砲弾が飛び交い、濃霧の中で敵も味方も必死の攻防を繰り広げます。装填が追いつかないときは、戦車はキャタピラで敵兵を踏み砕きました。砲塔の上で池田聯隊長は身を晒し、日章旗を振り続けました。
40分に及ぶ激戦の末、士魂部隊はソ連軍を殲滅寸前まで追い詰めました。戦車27両が大破し、池田聯隊長も戦死しましたが、その抵抗によってソ連軍は一週間、占守島に釘付けとなりました。この遅滞行動こそが、ソ連による北海道侵攻を阻止し、日本を南北に分断から救ったのです。
ソ連の公式記録にも「占守島の戦いは甚大な損害を生み、全く無駄な作戦だった」と残されています。日本側の損害は大きかったものの、この戦いは女子工員を守り、国土の一体性を守る結果をもたらしました。
戦後、この戦いは教科書に記されず、しばしば「無駄な戦い」と切り捨てられてきました。しかし実際には、日本の運命を大きく左右した決戦だったのです。占守島には今も戦車や遺骨が眠り、兵士たちの犠牲と勇気を静かに物語っています。
池田聯隊長が兵士に語った「諸士、ついに起つときが来た」という言葉は、今を生きる私たちへの問いかけでもあります。国を守る覚悟、人を守る使命をどう果たすか。占守島の戦いは、決して「無駄」ではなく、日本を救った最後の勝利だったのです。