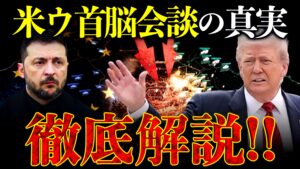8月20日は交通信号設置記念日。日本独自の工夫や歴史を振り返るとともに、2014年の広島土砂災害を通じて、地名の伝承や災害対策の重要性を学びました。自然と共に生きる日本の知恵を再確認します。
日本初の信号機設置と「日本の知恵」
1931年8月20日、東京の銀座四丁目や京橋など34か所に、日本初の3色灯自動信号機が設置されました。これが「交通信号設置記念日」の由来です。
当時の信号機は、色が変わるたびにベルが鳴る仕組みでしたが、信号の意味が浸透しておらず、かえって事故が多発しました。
日本の信号は横型で、赤信号が向かって右側に配置されています。これは日本が左側通行で運転席が右側にあるため、赤が最も見えやすい位置に工夫されたからです。海外では縦型が主流ですが、日本の知恵と環境適応の象徴といえるでしょう。また、豪雪地帯では雪の積もりにくい縦型が採用されるなど、地域の事情に応じた柔軟な対応も見られます。
こうした背景から、日本は単なる模倣ではなく、自国の実情に合わせた創意工夫を重ねてきたことが分かります。
広島「蛇落地悪谷」と2014年の土砂災害
2014年8月20日、広島市安佐北区・安佐南区で発生した土砂災害は、わずか1時間に121ミリという豪雨により発生し、75名の尊い命が失われました。
山口大学の調査によると、この地域では過去2000年間に少なくとも7回、同様の土砂災害が起きており、2014年は8回目にあたります。地名「蛇落地悪谷(じゃらくじあしだに)」には、古来から「人が住んではならない土地」とする伝承があり、大蛇退治の伝説とも結びついていました。
こうした地名や伝承は、先人が危険を避けるための知恵として受け継いできたものです。しかし、戦後の宅地開発や地名改変により、本来の意味が失われ、危険な土地に住宅が建設されるようになりました。災害は自然現象であっても、人的被害が出るのは人災でもあるのです。
水害と人災、そして未来への学び
日本各地では過去にも多くの豪雨災害が発生しました。1938年の阪神大水害では24時間で616ミリの雨が降り、715人が亡くなりました。1967年の羽越豪雨では死者104名、2008年の豪雨では1時間で146ミリもの雨が観測されています。
これらの災害の多くは、適切な土地利用や堤防整備があれば被害を最小限にできたと指摘されています。とりわけ堤防や宅地造成における手抜き工事は、人命を脅かす重大な要因です。本来、日本は価格競争ではなく品質競争の国であり、誠実な工事に正当な対価を払う文化を持っていました。しかし近年は価格優先の風潮により、結果的に高くつく悪循環が生まれています。
2014年の災害を機に「線状降水帯」という言葉が広まりましたが、それは古来からある気象現象でもあり、日本人はもともと自然と共存し、災害と向き合いながら暮らしてきました。災害を単なる「脅威」とみなすのではなく、恵みとリスクの両面を受け止め、先人の知恵を活かした暮らしを取り戻すことが求められます。
【所感】
交通信号の設置や広島の土砂災害の歴史を振り返ると、私たちは自然と共に生きる知恵をいかに失い、また取り戻さねばならないかを考えさせられます。
地名に込められた警告や、先人が残してくれた伝承は、単なる迷信ではなく命を守るための大切な道標でした。ところが現代は、経済の論理や利便性を優先するあまり、その知恵を軽んじてきたのではないでしょうか。
土砂災害や豪雨は自然の営みの一部です。しかし、人的被害を最小限に抑えるかどうかは、人間の選択にかかっています。価格競争に流されず誠実な工事を貫くこと、危険な土地を見極めて利用を控えること──その積み重ねが未来の命を守ることにつながります。
「雨は恵みであり、また災いともなる」。日本人はその両面を受け入れ、共に響き合いながら生きてきました。これからも自然への畏敬を忘れず、互いに支え合う社会を築いていきたいと思います。