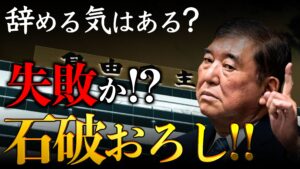1944年の対馬丸事件では1,400名以上が犠牲となりました。本来非難されるべきは米潜水艦の攻撃であり、護衛艦は命をかけて他の輸送船を守りました。戦後の歪んだ記憶を正し、日本人の「思いやりの心」を見つめ直します。
はじめに──歴史に刻まれた二つの出来事
1944年8月22日、沖縄から本土へ学童を疎開させる途中だった「対馬丸」が米潜水艦の魚雷攻撃を受け、わずか11分で沈没しました。乗員乗客1,788名のうち1,418名が犠牲となり、その多くは子供たちでした。
また翌1945年の同じ時期には「愛宕山事件」や「大東塾十四烈士」の自決もありました。戦争末期の混乱の中で、命を懸けて自らの信念を貫いた人々の姿は、いまも私たちに大きな問いを投げかけています。
対馬丸事件の真実──護衛艦は見捨てたのか
沖縄の「対馬丸記念館」では「護衛艦が学童を見捨てて去った」という説明がされることがあります。しかし実際には、護衛艦は他の二隻の輸送船を守るため、やむを得ず現場を離脱しました。その結果、残り約3,000名の命が救われたのです。
本来、責められるべきは学童疎開船を狙った米潜水艦ボーフィンの攻撃でした。輸送船は国際法上「非戦闘船」として保護されるべき存在であり、学童を狙った魚雷攻撃は明らかな戦時国際法違反です。
それにもかかわらず戦後は裁かれることなく、「日本が悪かった」とする印象操作が繰り返されてきました。
護衛艦はこれまで700隻以上の疎開船を無事に送り届けており、対馬丸はそのうち唯一沈められた船でした。事実を全体として見ず、一部だけを切り取れば、歴史は誤って伝わってしまいます。
背景にあった疎開政策と沖縄県民の苦悩
対馬丸事件の背景には、サイパン島陥落後の東条内閣による「沖縄から10万人疎開」という緊急決定がありました。民間人を戦場から退避させることは軍にとっても不可欠でした。
しかし、当時の沖縄県知事は疎開に反対し、実施は大きく遅れました。その中で、警察部長の荒井退造らが奔走し、一軒一軒の家を訪ね説得を重ねたことで、ようやく疎開が始まります。最初の疎開船「天草丸」は、敵潜水艦を避けながら実に2週間をかけて鹿児島に到着しました。
燃料不足と空襲の恐怖の中、子供たちを必死に守り抜こうとした船員や軍人の努力は、もっと広く知られるべき事実です。
戦後への教訓──思いやりの心を忘れない
対馬丸事件は、戦勝国による「勝者の正義」の中で真実が覆い隠されてきました。しかし私たちが忘れてはならないのは、犠牲となった命への哀悼と、最後まで仲間を守ろうとした人々の思いやりの心です。
漂流中に子供たちを筏に乗せ、自分は海に浸かりながら励まし続けた小関一等運転士。沈没直前まで救命胴衣を子供に着せ、声を枯らして避難を叫んだ船員たち。彼らの姿は「日本男児の誇り」であり、未来に伝えるべき精神です。
また、愛宕山での自決や大東塾十四烈士の覚悟も、戦争の悲劇の中で「自分の責任を果たす」ことに命を懸けた姿でした。彼らの行動に賛否はあっても、その誠実さと信念は、今の時代にも通じるものがあります。
私たちが学ぶべきは、犠牲を「誰のせい」と責めることではなく、苦境にあっても互いを思いやり、未来を護ろうとした心です。
その心を引き継ぐことこそ、先人たちへの最大の供養であり、現代を生きる私たちの責任だと思います。
結び
対馬丸事件や愛宕山事件に学ぶのは、戦争の悲惨さそのもの以上に、人々が最後まで持ち続けた「思いやり」と「誇り」です。
歪められた歴史を正しく見直し、真実を語り継ぎながら、私たちは未来に向けて安心と笑顔あふれる社会を築いていきたいと思います。