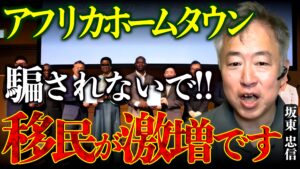米国の公民権運動と黒人差別撤廃、日本の同和・在日問題を比較。差別と差蔑を区別し、制度ではなく心の響き合いこそが解決の鍵だと説きます。
はじめに|日米の差別問題に共通する構造
8月28日の放送では、アメリカでの黒人差別の歴史を起点に、日本の同和問題や在日コリアンの特権問題と比較しながら、差別を法律や制度で解消しようとすると何が起こるのかを考えました。アメリカでも日本でも、差別撤廃の名の下に行われた「優遇策」が、結果として利権化し、逆差別や新たな対立を生んだことが共通しています。ここには、人間社会に普遍的な「差別」と「差蔑」の混同が横たわっています。
公民権運動とアメリカの現実
1950年代の米国では、黒人が白人女性に口笛を吹いたことで撲殺されるという事件まで起きました。当時の黒人は兵役でも「盾」として使われるなど、まさに人間扱いされていませんでした。1963年、ワシントン大行進でキング牧師が「I have a dream」と訴え、1964年公民権法、1965年投票権法、1968年公正住宅法が成立します。しかし、法律ができても社会で差別がなくなったわけではなく、1970年代にようやく黒人の進学や就職が現実のものとなりました。
ただし、その過程で「黒人を一定割合で入学・採用せねばならない」という制度が導入され、逆差別が発生しました。白人やアジア系の若者が「努力しても報われない」と不満を募らせる一方、「差別された」と主張すれば補助金や昇進が得られるという被害者特権も広がりました。結果として、黒人社会の中でもニューリッチ層と貧困層の格差が拡大し、社会対立を長引かせたのです。
日本の同和対策と在日問題
同じころ日本でも、部落差別問題や在日コリアン問題に対して、特別措置法や補助金制度が導入されました。これにより住宅やインフラは改善されましたが、「差別されている」という立場が利権化する構造が生まれました。差別解消を掲げながら、特権意識を持つ層が生まれ、逆に一般日本人が差別される事例すら起こりました。また、同じ集団の中でも超VIP層と貧困層に二極分化が進み、問題は解決するどころか固定化してしまいました。
こうした歴史を見れば、「差別を制度で解決しようとしたことには限界がある」ことが明白だといえます。
差別と差蔑の違い、日本文化の知恵
本来「差別」は社会秩序を維持するための区別でありす。社長と社員、教師と生徒、警察官と市民といった役割の違いは社会秩序の上で必要なことです。問題は「差蔑」──相手を見下し、人間としての尊厳を奪うことにあります。
つまり差蔑は「制度の問題」ではなく「心と行動の問題」なのです。
日本文化には「和を以て貴しとなす」や「しらす統治」の伝統があり、役割の違いを尊重しながらも人を蔑まないという精神がありました。これは「共震・共鳴・響き合い」の文化でもあります。制度で強制するのではなく、心の持ち方によって差蔑を防ぐ──ここに日本の知恵があります。
結び|人間の愚かさを超えて響き合う
アメリカでも日本でも、差別を解消しようとした制度が逆に差別を固定化し、利権構造を生み出しました。人間は時に愚かさを露わにしますが、同時に「これは愚かしいことだ」と気づく力も持っています。そして「響き合い」を選び取ることができるのです。
人類が未来に向けて進む道は、「差別はいけない」と制度で縛ることではなく、「差蔑をしない」「互いに響き合う」という心の文化を育てることです。そこにこそ、日本が世界に示せる希望があるのだと思います。
【所感】
差別(区別・役割の違い)は discrimination / distinction、差蔑(見下し・非道な扱い)は contempt / derogation / demeaning discrimination と表現することができます。
しかし英語圏には、両者を厳密に切り分ける言葉が存在せず、いずれも discrimination として一括りにされてしまいがちです。
日本語でも、どちらも「さべつ」と同じ発音で表されるため、混同されやすい素地があります。
この言葉の曖昧さが、「差別=悪」と短絡的に捉えさせ、制度による解消策へと傾かせてきた背景の一つではないでしょうか。
しかし、日本文化には古来より「区別は必要であるが、蔑視はしてはならない」という思想が息づいています。
この視点こそ、いま世界に向けて伝えるべき日本の知恵であり、人類が響き合う未来を切り拓く鍵となると考えます。