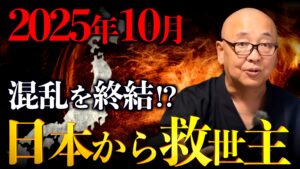今朝のライブでは、1923年の関東大震災を手がかりに「火災拡大の構造」と「備えの実践」を整理しました。非常持出袋や在宅避難の準備、家族の連絡計画など、9月1日に見直す具体策を私の視点で提案しました。
1.関東の地震史と「1923年」の異常値をどう読むか
今日は関東大震災があった日です。関東では、1703年の元禄地震(死者約1万人)、1782年の天明地震(死者少数)、1855年の安政地震(死者7,444人)、そして1923年の関東地震(死者約14万人)と、大規模地震が周期的に発生してきました。元禄‐天明は79年、天明‐安政は73年、安政‐関東は68年、そして関東から現在まではすでに98年が経過しています。私は、いつ巨大地震が来てもおかしくないという前提で、歴史の数字をいまに活かすことが大切だと考えます。
大正12(1923)年9月1日11時58分、相模湾北西沖80kmを震源とするM7.9の地震が発生しました。特筆すべきは、被害の突出度です。江戸(元禄・天明・安政)と東京(大正)の人口規模は概ね200~250万人と大差がないのに、関東大震災では死者・行方不明が約14万2,800人、負傷10万余、避難190万人超、家屋全半壊約25万戸、焼失約44万7,000戸に達しました。なぜここまで差が開いたのか。私は、直接の揺れよりも、震災後に拡大した火災と延焼が決定的な要因だった点に注目します。
当日の同時多発出火(確認136〜139件)は訓練と消火で概ね鎮圧された一方、翌日以降に大規模火災が連鎖しました。たとえば本所区被服廠(現・墨田区横網町公園〈旧・被服廠跡〉)では、広大な避難地に集まっていた人々が火炎の渦に巻き込まれ、大量の犠牲が出ました。明暦の大火(1657年)や東京大空襲(1945年3月10日)と比較しても、関東大震災時の火災被害は桁違いだったという現実があります。
2.「火災拡大の構造」と治安の乱れ――当時資料にみる事実の範囲で
関東大震災では、当日の初期出火が消し止められたにもかかわらず、翌日以降に広域の火災が発生したという事実があります。多くの住民が避難所に移動して、無人になった住宅地から突然火の手が上がりました。いくつもの箇所で同時多発的に起きたこの火災は、避難者が集う広場や空地さえも焼き尽くす火力となり、被害の範囲と速度を一気に拡大しました。
また、当時の新聞号外や行政の公表文には、放火・爆発・略奪などの行為が各地で相次ぎ、軍・警察が治安維持と保護に動いたことが記録されています。大切なことは、属性で人を一括りにしないことです。保護すべき人は保護し、違法行為者は厳重に取り締まる。これは憎悪(ヘイト)ではなく、公共の安全を守るための原則です。混乱期には流言が拡散しやすいため、一次資料の確認・複数資料の突き合わせ・時系列の整理を徹底し、検証可能な事実と評価・推測を明確に区別して伝える姿勢を、私は大切にしています。
3.現代への提言――延焼を断ち、備えを更新し、憎悪ではなく秩序で守る
過去の地震周期と現在の経過年数を踏まえれば、首都直下地震は「いまそこにある危機」です。しかも、1923年当時の都市圏人口約380万人に対し、現在の首都圏は約2,000万人規模。人口密度・高層化・地下空間・臨海部の埋立など、都市構造は複雑化・脆弱化の両面を抱えています。
まず今日できることとして、非常持出袋の点検・家族連絡カードの更新・在宅避難の可否確認(建物安全性・水とトイレの確保)の三点を挙げます。
関東大震災から100年。歴史は「恐れるため」ではなく「備えるため」にあります。
火災の連鎖を断ち、デマに惑わされず、弱者を守り、違法行為は行為として正しく扱う――この当たり前を積み重ねることが、命と暮らしを守ります。過去を現在に活かし、未来の安全をつくるために学ぶのだと、改めてお伝えしたいと思います。
【所感】
関東大震災から100年を迎えたいま、私たちが学ぶべきは「恐怖」ではありません。
あの日の犠牲は、地震そのものではなく、火災の連鎖と混乱の中で拡大したものでした。
そこから導かれるのは、備えと秩序を大切にする姿勢こそが命を守るという教訓です。
災害は必ずやってきます。しかし、それをどう受け止め、どう次の世代に活かしていくかは、私たちの選択次第です。
日本人が昔から培ってきた「教訓を学びに変える文化」を忘れず、いまを正しく生きることこそが、未来の安心を築く道だと私は思います。