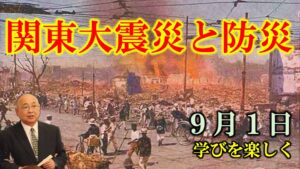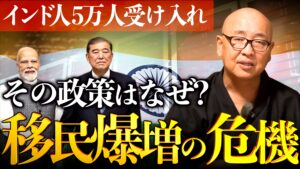終戦から80年。9月2日の降伏文書調印を機に、戦闘の終結と戦争の終結の違い、占領の現実、平和の本質を学び、日本が真の独立国となるための課題を語ります。
本稿の要点(先出し)
1. 戦闘の終結と戦争の終結は別物
8月15日に戦闘は止んだが、戦争は降伏文書と平和条約でしか終わらない。
2.「和平」と「Peace」の意味の違い
日本の「なごみ」と、西洋の「力による秩序」は根本的に異なる。
3. 真の独立への課題
日本はいまだ占領状態を脱していない。主体性を取り戻すことが急務である。
- 戦艦ミズーリの降伏文書調印 ― 戦闘は終わったのか
1945年9月2日、東京湾の戦艦ミズーリ上で降伏文書調印式が行われました。日本側からは外務大臣・重光葵と参謀総長・梅津美治郎が署名し、連合国はマッカーサー元帥をはじめとする代表者が臨席しました。
ここで大切なのは、8月15日の玉音放送によって戦闘行為は終わったが、戦争そのものは終わっていなかったという点です。戦闘の停止は国家間の合意ではなく、日本が自主的に武器を置いたにすぎません。戦争を法的に終わらせるには、降伏文書と平和条約の両方が必要なのです。
事実、日本が独立を回復したのは1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効のときでした。しかしその後も在日米軍基地は残され、日本はいまなお「占領状態」の影響下にあるのです。
- 「和平」と「Peace」 ― 言葉に隠された違い
日本では古来「和平(なごみ・へいわ)」という言葉がありました。ところが幕末に西洋語を翻訳する際、英語 Peace の訳語として「平和」という新しい熟語が生まれました。
この違いは決定的です。
・和平・・・・・・心が和らぎ、戦いをやめて共に歩むこと。
・Peace(Pax)・最強の軍事力によって秩序を維持すること。
つまり欧米の「ピース」は「力による平穏」であり、日本人が思い描く「調和的な平和」とは根本的に異なるのです。
この認識の差を理解しないまま「平和のために軍備は不要だ」と唱えるのは、現実から目を逸らす議論となります。真の平和を実現するためには、備えと抑止力を持たなければならないのです。日本の自衛隊は練度や能力で世界有数ですが、法的制約で力を発揮できないという矛盾を抱えています。ここをどう改革するかが、日本の未来を左右します。
- 戦後80年、日本の独立とこれから
サンフランシスコ講和条約で形式的には独立を回復した日本ですが、実態は完全な主権国家とは言えません。日米合同委員会や在日米軍の存在、そして憲法の制約によって、国家の意思決定は常に外部要因に左右されてきました。
私は、ここに「戦後日本の本質」があると考えます。
・大日本帝国憲法は廃棄されたのではなく、停止状態にある。
・日本国憲法もまた、執行停止できる仕組みが理論上は存在する。
・つまり日本は、自らの意思で主体的に立ち上がる余地を残されている。
いま求められているのは、「占領の延長線」に甘んじるのではなく、国民一人ひとりが真の独立国を取り戻す意思を持つことです。
戦争から80年。世界は再び不安定さを増しています。だからこそ私たちは「力なき平和」という幻想を捨て、歴史の現実に向き合い、日本としての進むべき道を自ら選び取らなければなりません。
結び ― 平和とは、未来を選び取る力
9月2日の降伏文書調印は、戦闘の終結を示す日でした。しかし真の戦争終結も、そして真の独立も、まだ道半ばにあります。
「平和」とは単に争いがない状態ではなく、未来を主体的に選び取る力のことです。
この節目の日に改めて、日本が世界に誇れる独立国となり、次世代へ確かな未来を引き渡すために、何をなすべきかを考え続けたいと思います。
【所感】
振り返れば、戦後80年の歩みは「失われた主権をどう取り戻すか」という問いの連続でした。
単に過去を批判するのではなく、そこから学び、未来に活かすことこそが大切だと思います。
歴史は「誰かが作ってくれるもの」ではなく、私たち一人ひとりの選択の積み重ねです。だからこそ、自分の小さな一歩でも、次世代へ響き渡る力になると信じています。