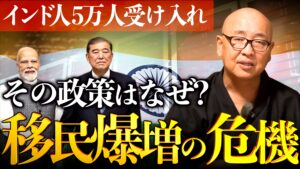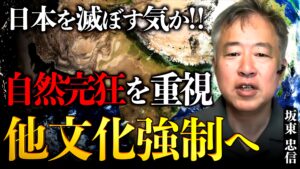9月3日配信の朝ライブを文字化。ドラえもん誕生日から最新技術、都市計画、外交・安保まで一気通貫で語りました。日本を強く賢くする“投資の勘所”を私の視点で整理します。
Ⅰ. 9月3日――ドラえもんの誕生日から見える「創造」と「作法」
9月3日は、ドラえもん(設定上は2112年9月3日生まれ)の誕生日です。
ライブでは、まずここから話を始めました。藤子・F・不二雄さんが「不思議なものがいっぱい出てくる漫画を描きたい」と志した物語は、単なる夢ではなく、未来の技術を“人が幸せに使う作法”まで含めて描いてきたと考えます。
四次元ポケットのどこでもドアやタケコプターは、便利さの象徴であると同時に、使い手の品位や社会全体の民度が問われる道具でもあります。
この“作法”の視点は、実社会の技術にもまっすぐ通じます。
日本は長く、世界に先駆けるものづくりの土壌を持ってきました。
ロボット技術や携帯端末の原型、素材・部品の匠の積み重ねがそれを証明しています。
一方で、素晴らしい芽が育ち切る前に資金や制度の壁に阻まれ、海外に先行されることも少なくありません。
新しいものは「空想→設計→試作→実装→市場」という長い階段を上ります。
途中で資金・人材・規制が詰まれば、芽はしおれます。
ここにこそ公的投資と規制設計の出番があり、民間の俊敏さを活かす“土台”づくりが要るのです。
同時に、日々の暮らしの作法も更新が必要です。
ライブ冒頭では、猛暑下での過剰なマスク着用や、独り運転中のマスクなど、行動と状況のずれにも触れました。
善意からの行動であっても、目的(自他の安全や健康)と手段が合っていなければ成果は出ません。
技術も政策も生活作法も、「目的に対して最適か」を絶えず問い直すことが、成熟社会の姿だと考えます。
Ⅱ. 政治とインフラ、産業投資――「邪魔をしない政治」と「攻める国家」
次に、戦後から現在までの政治と産業の関係を、具体例で振り返りました。
高度成長期を支えたのは、現場で汗をかく民間の創意と努力でした。
対して政治は、時に復興や産業育成の背を押すべき場面で、規制や為替、合併の強制など“現場の足を引っ張る”役回りだったのではないか――そんな疑念が拭えません。
名古屋の広い道路計画、東京五輪前の首都高整備など、先見ある都市計画の例もある一方、流入交通量と道路容量の数学が合っていない設計が慢性的渋滞を生むなど、「目先の都合に合わせ、長期の数理を外す」失敗も繰り返してきました。
産業面では、日産スカイラインGT-Rの打ち切り報道を引き合いに、象徴的技術を守れない体質を論じました。
合併や労使の対立、政治の関与など要因は複合的ですが、
核心は「価値の核」を国家として護る意思と資金を持てるかです。
もし国に、外国人受け入れや外向きのバラマキに投じる原資があるなら、その一部を“日本の技術遺伝子”の継承・発展に振り向けるべきではないか。
研究開発費は未来の所得の源泉です。宇宙・量子・半導体・先端材料・防衛転用可能技術への戦略投資は、「夢」ではなく安全と富のインフラです。
ここで、速度記録車の話題に触れました。
1935年、V12サンビームが時速約485kmを記録。
1997年、英国のスラストSSCはジェットエンジン2基で時速1228km、音速を突破しました。
公道を走れない“無用の長物”に見えるかもしれません。
けれど、極限の挑戦は推進・冷却・制御・素材などのブレイクスルーを生み、それが軍需・民生の広い裾野に波及します。
欧米が「最速」や「最強」に公的資金を入れるのは、見栄ではなく、抑止力と産業競争力を両立させる戦略だからです。
平和(peace)の語源が pax(力による秩序)にあることを想起すれば、「攻めの技術」が平和の基礎になる理路は理解できます。
外国人受け入れについても、私は“数先行”より“設計先行”を求めます。
言語・職能・賃金フロア・地域定着を含むプロトコルがない拡大は摩擦と不信を招きます。
逆に、産業と教育・住居・地域のセット設計を徹底し、日本人の賃金と生産性の底上げと並走させれば、“補完”は“相乗”に変わります。
政治が為すべきは、「分断の火に油を注ぐこと」でも「民の挑戦にブレーキをかけること」でもなく、長期の数理にもとづく交通整理です。
Ⅲ. 何にお金を使うのか――守りと攻めのバランス、そして笑顔
結局のところ、国家の意思は予算配分に現れます。誰を守り、何を伸ばすのか。私は、次の順番を大切にしたいと思います。
第一に、国民の生命と暮らしの安全(防災・防衛・エネルギー・食)。
第二に、未来の稼ぐ力(研究開発・人材・インフラ・企業の挑戦)。
第三に、地域の持続性(教育・医療・子育てと、空き家や交通の再設計)。
この三層に資金を「点」でなく「面」で投じれば、民間の創造は加速します。
量子や宇宙のような最先端も、地域の学校や中小企業の設備更新も、同じ「未来の面」に位置づけられるからです。
逆に、理念なきバラマキや、出口なき受け入れ拡大は、国力を薄めます。
安全保障では、2017年9月3日の核実験に象徴される現実を直視しつつ、日本独自の抑止力と同盟の実効性を高める必要があります。
ここでも、武力礼賛ではなく抑止=費用対効果の高い投資設計の発想が要です。
極端な「軍拡かゼロか」という二者択一ではなく、技術・情報・産業を束ねた総合抑止で、平時の豊かさと非常時の強さを両立させていくことが重要です。
最後に――ライブの締めくくりと同じく、私は「怒りより、笑顔」を選びます。
現状への苛立ちは、進歩の燃料になりますが、怒りだけでは舵取りを誤ります。
ドラえもんの道具のように、技術は使い手次第で世界を良くも悪くも変えます。
だからこそ、私たちは何に投資し、どう使うかを賢く決めたい。
9月3日の朝、速度記録と未来技術、都市計画と産業、受け入れ政策と安全保障を横断して語ったのは、すべて「日本を強く、賢く、優しくするための順番」を探るための事柄です。
今日も笑顔で、明るい未来を自分たちの手で開いて行きましょう。
【所感】
9月3日のライブを振り返りながら改めて感じるのは、怒りや不満だけでは未来は拓けないということです。
確かに政治や産業の現状には数多くの課題があります。
しかし、それを糾弾するだけでは心は疲れ、社会も荒れてしまいます。
大切なのは、知識を希望につなぎ、共に笑顔で次の一歩を踏み出すことです。
ドラえもんの四次元ポケットの道具が、使う人の心によって善にも悪にもなるように、私たちが手にする技術や制度もまた、響き合いの心次第で未来を変えます。
怒りを燃料にしつつも、最後は共震共鳴響き合いへと昇華させる――それこそが日本の未来を支える作法だと信じています。