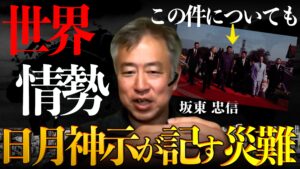戦後のGHQプレスコードは、表向きの建前と裏の運用が大きく乖離していました。その結果、日本人は「言えないこと」を無意識に抱え込み、今日まで影響が残っています。本来の慣習に根ざした自由な言論を取り戻す必要があります。
戦後日本に課された「プレスコード」
1945年9月19日、GHQによって発布された「プレスコード」は、占領下の日本の言論を大きく規制しました。その直前の9月10日、日本政府に示された覚書には「真実に即した報道をせよ」「事実を曲げてはいけない」といった至極まっとうな内容が記されていました。政府としても受け入れざるを得ない建前の文言でした。
ところが、実際に運用されたプレスコードは全く異なるものでした。天皇批判や連合国批判、原爆被害の真相や満州・シベリアでの邦人の苦難、さらには大東亜共栄圏の理念など、日本人にとって重大な出来事や歴史的事実の多くが報道禁止とされたのです。しかも日本政府にはその本当の内容が知らされず、建前と実際の間に大きな齟齬が生じました。これこそが、戦後日本の「二重構造」の出発点となったのです。
言えないことを抱え込む社会へ
この統制によって、日本人は「言ってはいけないこと」「考えてはいけないこと」を知らず知らずのうちに植え付けられました。占領が終わり独立を回復した後も、その空気は社会に根強く残りました。いまもなお、歴史や外交を語るときに「そこはタブーだ」「それは言ってはいけない」という無言の圧力が働いているのは、その名残といえます。
本来、言論の自由は「何を言ってもいい」という放埓さではありません。事実に即し、責任を持って語り合うことこそが成熟した自由の姿です。異なる意見を持つ者同士が「お前は間違っている」と排除し合うのではなく、その違いの中に真実の一端があると考え、共に探っていく――これこそが民主主義の根幹です。
日本人は古来「察する」文化を大切にしてきました。本音と建前の狭間で、相手の言葉の裏にある状況や心を感じ取り、互いに補い合う。仁徳天皇が「民のかまど」の煙を見て減税を決めた逸話も、その象徴でしょう。ところが、プレスコード以降の日本は、慣習よりも成文法や規制が優先される社会へと変わってしまいました。
自由の本質を取り戻すために
いま必要なのは、建前としての「自由」や、外から押し付けられた統制ではありません。日本本来の歴史・伝統・文化に根ざした自由な言論のあり方を取り戻すことです。そこでは「異なる意見を尊重し、共に真実を探る姿勢」が最も大切にされます。
法律は社会の最低限のルールでしかなく、人がまっすぐに生きるための基盤は歴史と文化の中にあります。そこに立ち戻ってこそ、言論は建設的に働き、人々の心に光をもたらします。
言論統制や規制の話はどうしても重たく、暗い印象を与えがちです。けれど、人間のエゴのむき出しに目を向けるだけではなく、日本的な心や響き合いを大切にしていくところに光があります。
戦後80年を経た今こそ、私たちは過去の統制の影響を直視し、自由に語り合い、未来を築くための新しい言論空間を創り直すべき時に立っているのではないでしょうか。
【所感】
戦後の「建前と運用」の二重構造は、気づかぬうちに“言えない空気”を社会に根づかせてきました。けれども日本には「察する」「共に真実を探る」という文化があり、それこそが統制を乗り越える力になるはずです。
言論の自由とは「何を言ってもよい」ことではなく、「事実に即し責任を分かち合う姿勢」であることを改めて思います。歴史と文化に根ざした慣習と、現代の検証や敬意、対話を重ね合わせることで、分断ではなく創造につながる言葉が生まれるはずです。
重いテーマを扱いながらも、その先に希望の光を見いだせる――そのような手応えを持ちました。