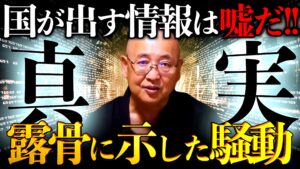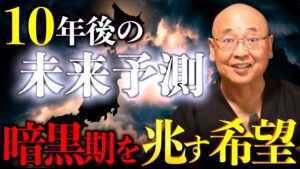1890年のエルトゥールル号遭難救助から、1985年のテヘラン日本人救出、さらにアタテュルク像の受難と再生まで。受け継がれた恩と友情をたどり、未来へ生かす視点を示します。
1) 9月16日に刻まれた“はじまり”――エルトゥールル号遭難と串本の献身
9月16日は、ハイビジョンの日として知られ、2018年には安室奈美恵さんの引退も重なります。
同じこの日に、日ト友好の原点となる出来事が起きました。
1890年(明治23年)、オスマン帝国の軍艦エルトゥールル号が親善訪日の帰路で暴風雨に遭い、和歌山県串本沖で座礁・遭難します。
特使を含む多数が犠牲となる一方、生存者69名は、台風で漁に出られず自らも食糧難にあった串本の人びとに救助・看護されました。
村人たちは非常時のために残していた鶏まで差し出し、遭難者の遺体も丁重に葬ります。
この報は和歌山県知事を通じて明治天皇に伝わり、後日、日本の軍艦2隻が生存者を本国へ送り届けました。
民の善意と公の迅速な配慮が重なり、国境を越える信頼の糸が結ばれます。
さらに一民間人、山田寅次郎が全国を歩いて義捐金を募り、1892年にイスタンブールで外相サイド・パシャを通じて皇帝アブデュルハミト2世に拝謁し、寄付を手渡しました。
要請を受けて寅次郎は現地にとどまり、日本語や礼節、日本文化を教えます。
その教え子の中に、のちにトルコ共和国初代大統領となるムスタファ・ケマル(アタテュルク)も含まれます。
串本村の献身、寅次郎の草の根外交は、個人の行いが国の友情に育つことを雄弁に示しました。
2) 95年後の“恩返し”――テヘラン空港に降りた一機のトルコ航空
時は流れて1985年。イラン・イラク戦争下、領空を飛ぶ航空機を撃墜するとの通告が発され、テヘランには各国の救援機が続々と集まりました。
ところが日本人は取り残され、刻限が迫るなか空港は不安に包まれます。
そこへ到着したのがトルコ航空の機体でした。
それは、日本人216名は同機に収容され、離陸はタイムリミットのわずか1時間余り前のことでした。
後に元駐日トルコ大使は「エルトゥールル号のときの日本人の献身を、トルコ人は忘れていない」と語ります。
トルコでは遭難と救助の史実が学校教育で語り継がれています。
だからこそ、危機の瞬間に「友を助ける」判断が迷いなく下されました。
一方で日本国内では、この連鎖が十分に共有されてきたとは言い切れません。
9月16日を手がかりに、恩と友情の記憶を掘り起こし、いまへつなぐ必要があります。
3) 信義の“試練”と再生――アタテュルク像が問いかけるもの
1996年、新潟県柏崎市に「トルコ文化村」が開業し、日ト友好の象徴としてアタテュルク像が寄贈されました。
日本への配慮から稀少な「非軍装」の立像が選ばれ、広場の中心に据えられます。
しかし金融危機の影響で施設は経営不振に陥り、倒産後は管理不全に。像は横倒しで覆いをかけられたまま長く放置され、在日トルコ大使館や地元有志から厳しい抗議と要望が寄せられました。
最終的に日本財団などの尽力で修復・公開が進み、2010年には和歌山県串本町へ移設。
エルトゥールル号の記憶と並ぶ場所で、本来の意味を取り戻します。
この経緯は、友情を語ることの易しさと、象徴を守り続ける難しさを同時に教えています。
要となるのは、政局や行政の事情を越え、約束と記憶を丁寧に扱う市民の良心です。
9月16日に思い出すべきは、逸話の列挙ではありません。
困窮しても差し出す一膳の食事、
海を越えて届ける義捐、
危機に駆けつける勇気、
象徴を敬う手間
こうした小さな行為の累積が、国と国の信頼を支える土台になります。
歴史を知識で終わらせず、今日の選択へと翻訳していくこと。
そこに“友情の連鎖”を未来へつなぐ鍵があります。
【所感】
9月16日に重なる三つの物語は、恩と友情が“制度”ではなく“ふるまい”で受け渡されることを教えてくれます。誰かの非常時に差し出す温かい一品、記憶を次の世代へ手渡す語り、象徴を丁寧に扱う手間。その小さな選択の合計が、国と国を支える土台になります。
いま必要なのは、語り継ぐだけで満足せず、自分の現場で一つの善きを積み上げる覚悟です。
そう信じて行動するかどうかが、これからの社会を大きく変えていきます。
人に何かを話すとき、その言葉は、そのまま自分に帰ってきます。
「勇気と希望を持とう。笑顔で行こう」と誰かに言えば、それはそのまま言った本人の姿になります。
誰それは「悪人だ」と批判すれば、その言葉もまた、そのまま自分に帰ってきます。
平和を口にしながら手前勝手な振る舞いをしていたかつての巨大政党は、いまでは議席数1が保持できるかどうかという姿になっています。
歴史や古典は、未来を生きる力を取り戻す道標です。
その力を今に活かそうとする歩みこそが、倭塾です。