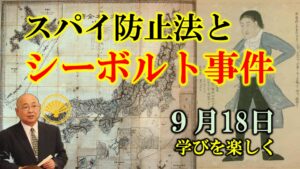1964年、銀座のみゆき通りで若者が一斉検挙に。アイビールック、週刊誌の煽り、五輪前の風紀強化を検証し、断罪より改善へ――日本的な合意形成で自由と礼節のバランスを考えます。
1 事件の背景──アイビールックと「みゆき族」
1960年代初頭、銀座のみゆき通りには、当時の若者文化を象徴するスタイル「アイビールック」に身を包んだ若者たちが集うようになりました。
七三分けの髪型にボタンダウンシャツ、三つボタンのブレザー、コットンパンツにローファー。女性は白いブラウスやロングスカート、ぺたんこの靴にスカーフやネッカチーフ。VANやJUNの紙袋を抱えて街を歩くこと自体がファッションでした。
アメリカ東部の名門私大群「アイビーリーグ」に由来するこの装いは、勉学中心の簡潔で清潔なスタイルです。それが日本に入ると、バミューダショーツや丈の短いパンツなど独自の解釈が加わり、軽快で明るいものとして定着しました。
銀座のVANの大型店舗前に集まった若者たちは「みゆき族」と呼ばれました。彼らは反社会的行為をするわけでもなく、ただ集い、歩き、語り合っていただけです。
それでも1964年9月19日、築地警察署の一斉検挙によって85人が連行されました。
2 一斉検挙はなぜ起きたのか──報道、苦情、そして「空気」
当時の週刊誌は、みゆき族を「不純異性交遊」と結びつけ、面白おかしく報じました。その記事が読者の好奇心を煽り、銀座の店舗からは「商売の邪魔」「不快だ」といった苦情が相次ぎました。結果として「公共の秩序」「五輪前の風紀向上」という大義名分が立ち、一斉検挙につながったのです。
この出来事の背後には、アメリカの人種問題も影を落としています。1961年、ケネディ大統領が発動したアファーマティブ・アクションによって、アイビーリーグのキャンパスには黒人やヒスパニック系の学生が増えました。本来は白人学生の象徴とされたアイビールックを、彼らが身につけることは、当時の一部の支配層には不快に映ったといいます。そしてその「不快感」は、対象外だったアジア系にも及びました。
1964年の日本は占領期を脱したばかりで、米軍の影響はなお強い時代です。日本人の若者が繁華街でアイビールックに身を包む姿は、国際的な「空気」と無縁ではなかったでしょう。こうした背景に、週刊誌の報道や苦情の集中が重なり、「一斉検挙」という形で現実化したのです。
また、日本の法律は網羅性が高く、運用次第で「誰でも逮捕できる」といわれるほど。普段は裁量で運用を控えていても、「空気」と結びつけば一斉対応が可能になる――そんな制度的側面も見逃せません。
3 今日への教訓──「誰が悪いか」より「どう直すか」
歴史を学ぶ意味は、年号を覚えることでも、誰かを断罪することでもありません。大切なのは「今を生きる力」に変えることです。
第一に、「事実を知る」こと。日本は「知らす国」とも呼ばれるほど、知ることを大切にしてきました。事実を共有してこそ話し合いが可能になります。
第二に、「人を責めて終わらない」こと。人が起こした問題は、人が改善していくしかありません。誰かを責めても仕組みは変わりません。トヨタの“カイゼン”にならうなら、問題の可視化→小さな是正→再検証という循環が社会にも必要です。
第三に、「合意形成の文化」を活かすこと。情報を共有し、現場の声を取り込み、対立を煽るのではなく改善へ結びつける。報道・苦情・空気の連鎖によって、日常の自由が脆くも崩れたのがみゆき族事件でした。この構造は、移民、教育、家族、LGBT、公共空間のマナーといった現代の論点にも重なります。
歴史は「扉」を示します。
過去を知ることは、今の選択肢を増やし、未来をひらく力になります。
誰かを打ち負かすためでなく、共に暮らしやすい社会を築くために。
事実を確かめ、小さな改善を積み重ねていく――その姿勢こそが、自由と礼節のバランスを取り戻す道ではないでしょうか。
みゆき通りを歩いた若者たちの姿は、そのヒントを今に伝えているように思えてなりません。
【所感】
何も悪いことをしていなかった「みゆき族」が一斉補導された経緯を調べていくと、何事につけ、「報道」「苦情」「空気」という三つの要素を結びつけば、一気に社会的な排除へと進ませることができるという事実を知ることができます。
半世紀以上前の出来事ではありますが、現代の日本社会でも同じ構造は形を変えて存在しています。
大切なのは、誰かを悪者に仕立てるのではなく、仕組みのどこに偏りや不具合があるのかを見極め、改善の工夫を重ねていくことだと思います。
歴史を学ぶ意味は、こうした「繰り返してはならない構造」を知り、未来への選択を増やすことにあるのではないでしょうか。