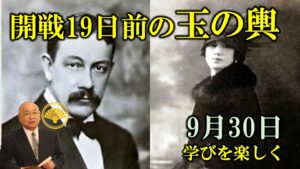招き猫の日に合わせ、左右の意味や色の由来、豪徳寺・今戸焼・吉原の伝承を紹介。農耕・養蚕との関わりや海外普及も踏まえ、祈りと感謝が文化を育てる過程を語りました。
Ⅰ 9月29日「招き猫の日」──左右と色に宿る願い
9月29日は【く(9)るふ(2)く(9)=来る福】の語呂から、日本招猫倶楽部が定めた記念日です。
招き猫には、右手を上げている猫、左手を上げている猫がありますが、右手は金運・福・健康など“身”に関わる実り、左手は人脈・縁・交流など“魂”に関わる良縁の猫です。参拝の作法にある「右手を少し引く所作」に触れつつ、身と魂を整える日本的感覚が招き猫の左右にも映っているのです。
招き猫の色の違いにも意味があります。
一般的な白や三毛は「開運招福」
黒の招き猫は、夜目の良さにちなんで「厄除安全」
金や黄色は「金運繁栄」
赤は疱瘡除け由来から「諸病快癒・健康長寿」
たまに見かけるピンクの招き猫は「恋愛成就」
招き猫がチャイナ由来という人もいますが、招き猫は小判を抱えています。小判は日本のお金です(笑)。
また、近年では、招き猫の腹掛けの福の字が逆さまになっているものも見かけますが、これはチャイナ由来の「倒福(到福)」で、福が上から降ってくることを願って逆さまに文字を入れたものです。
もともと猫が人と同居するようになった背景には、ネズミの駆除という実利からといわれていますが、いまでは招き猫は世界中に広がり、台湾や中華圏、米国チャイナタウンでも売られ、アメリカでは、“Lucky Cat”や“Welcome Cat”と呼ばれ、ドル硬貨を抱いた招き猫もよく売れています。
Ⅱ 誕生秘話をたどる──豪徳寺・今戸焼・吉原
さて、招き猫の誕生秘話は、実はいろいろなものがあります。今回はその中から代表的な三つの物語を紹介しました。
ひとつめは、世田谷・豪徳寺に伝わる逸話で、鷹狩り帰りの井伊直孝が白猫に導かれて寺に入り、直後の雷雨から難を逃れたというお話です。これを縁に豪徳寺は井伊家の菩提寺となり、豪徳寺は江戸時代を通じて大繁栄しました。ここから「猫が福を招いた」象徴として語り継がれたというものです。
ふたつめは、浅草・今戸焼のお話。
貧しさから愛猫を手放した老婆の夢枕に猫が立ち、猫の人形を作るよう告げました。不思議に思った老婆がそのようにして浅草寺の前で売り出すと、これが大ヒット。老婆はたいへんに豊かになったという話。
または病気の娘を励ますために職人が作った猫の人形が評判になった話が伝えられています。
江戸の人気民芸である今戸焼と結びつき、浅草神社界隈から庶民文化として広がった物語です。
みっつめは、吉原の薄雲太夫と愛猫「玉」の伝説です。
猫の首が大蛇に噛みついて主を救い、太夫が西方寺に猫塚を建てたとされます。
守護の物語が人形文化に受け継がれ、招き猫像の原型意識へつながった物語です。
Ⅲ 祈りと感謝の循環──庶民文化が“福”を動かす
さて、猫はもともと生活を守る実利の担い手でしたが、招き猫となる過程には、実に日本的な文化が存在します。
招き猫に伝わる伝承は、すべて単なる縁起話ではなく、「祈り」と「感謝」の物語である、という点です。
祈り(願い)と感謝(報恩)の循環が可視化されたもののひとつが、招き猫になっているのです。
日本の文化は、豪奢な権力文化ではありません。暮らしの中の「日常の美徳」が土台にあり、これに祈りと感謝が重なったときに、それが文化となって育っています。招き猫はそのひとつの象徴といえるのです。
日本は、天皇を中心とする秩序観の下で「庶民は宝」と考えてきた歴史を持ちます。そこにこそ、日本文化が「民衆文化」として発展した理由があるのです。
【所感】
今回のお題は「招き猫にまつわる歴史」ですが、ここでも歴史を、単なる年号と事実としての「縁起」としてご紹介するのではなく、庶民の「祈り」と「感謝」、そして日本の国体にまつわる話にまで発展させていただきました。
「庶民こそが国の宝」という日本の古からの知恵の発露を考えたとき、招き猫はただの置物ではなく、日本の精神性のひとつの象徴となっていることに気が付くのです。