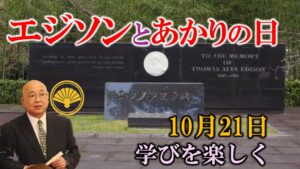高市総理誕生の喜びと共に、古代の高市皇子の和歌を再解釈し、政治の原点にある「愛」の精神を語りました。国を愛し、人を思う心こそ、日本再建の鍵であるというお話です。
日本初の女性宰相、その名に込められた縁
2025年10月21日。
日本の憲政史上初となる女性宰相、高市早苗総理が誕生しました。
市場は活気づき、社会には新しい風が吹きました。
けれども、ただ「女性初」ということだけではなく、
この“高市”という名に、不思議な縁を感じた方も多いのではないでしょうか。
その名を千三百年前に遡ると、
天武天皇の皇子であり、『日本書紀』や『万葉集』に名を残した
高市皇子(たけちのみこ)という人物が現れます。
彼は壬申の乱の英雄でありながら、
一首の悲しみの歌によって、その深い“人間の心”を後世に伝えた方です。
涙で詠んだ愛──高市皇子の真の心
高市皇子が愛した十市皇女(とおちのひめみこ)が亡くなったとき、
彼は深い悲しみの中で一首の歌を詠みました。
万葉集に残されたその歌は、
従来「山の泉に水を汲みに行きたいが道がわからない」と解され、
意味不明のものとされてきました。
しかし、原文を漢字のまま丁寧に読み直すと、
そこにはまったく異なる情景が浮かび上がります。
「見慣れた山さえも、涙で揺れて見える。
しっかり立っていなくちゃと思うけれど、
悲しみで立つことさえ辛い。
すぐそこにある清水を汲みに行くことさえ、
涙と嗚咽でできないよ。
十市皇女よ、帰ってきておくれよ・・・」
持統天皇の全幅の信頼を得た天下の太政大臣が、愛する女性の死を前にして、
まるで子供のように涙で暮れる姿を私たちは他に知りません。
そこにあるのは「権力者の威厳」ではなく、
人としての“愛”そのものです。
愛はすべてに通じる
誰かを真に愛する心は、やがて周囲の人への思いやりとなり、
郷土を思う心となり、国を思う心へと広がっていきます。
この「愛の連鎖と循環」こそ、
古代日本の政治の原点です。
高市皇子が生きた時代、
政治は支配や利害ではなく、
人を愛(おも)うこと、
そして響き合うことでした。
その精神は、『日本書紀』や『万葉集』にも流れています。
民を“道具”ではなく、“大御宝(おおみたから)”とする思想。
それはまさに、天皇と共に歩む国の理想です。
現代の高市──“愛の政治”の再来
いま、高市早苗総理の誕生に国民が期待を寄せるのは、
単に政権交代や女性リーダー誕生の話題性ではありません。
混迷の時代にあって、
「まっすぐに国を思う人」が現れたことへの共鳴です。
政治は対立ではなく、響き合いである。
打ち負かすのではなく、心を重ねる。
日本の政治の原点にあるのは、論理や権力ではなく、本当は“愛”なのです。
これから高市総理は、数多くの試練に直面するでしょう。
党内の思惑、外交の圧力、メディアの風。
しかし、その中で最も大切なことは、
国を愛(おも)い、国民を愛(おも)うこと。
そして、国民一人ひとりが、
家族を愛し、友を愛し、地域を愛し、国を愛すること。
愛は依存ではなく、自立の上に咲く花です。
自らの足で立ち、相手を尊び、互いを思いやるとき、
そこに真の響き合いが生まれます。
“愛の政治”が照らす未来へ
偶然にも、10月21日は「電気の日」。
エジソンが日本の竹でフィラメントを作り、世界を照らした日です。
竹のようにしなやかで、折れず、温かい光を放つ。
それはまさに、日本人の心そのものです。
高市皇子が涙の中で示した“愛”と、
高市総理が現代で灯した“希望の光”。
千三百年の時を超え、二つの“高市”が今、
一本の光の道で結ばれました。
政治とは、愛を形にする営み。
人を思い、国を思い、未来を照らすこと。
その道を共に歩むことこそ、
私たち国民の使命です。
そしてこの道を信じて歩めば、必ず光は広がります。
高市皇子の涙の歌が、いま再び、我が国の未来を照らし始めています。
【所感】
政治とは、制度や権力の話ではなく、本来“心の在り方”を映すものだと感じます。
高市皇子の涙の歌を通して見えるのは、人を思うことの尊さ、
そしてその心が千年を超えていまも国の礎を照らしているという事実です。
愛は、声高に語るものではなく、静かににじむもの。
その静けさの中に、真の力が宿ります。
高市総理の歩みが、この国の未来に優しい光を灯し、
人々が再び「愛によって響き合う政治」を思い出すきっかけとなることを願います。