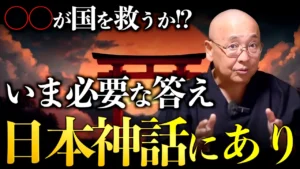人口の3分の1が渡来人でも文化を開花させた平安時代。
その秘密は「日本とは何か」を明確に示した日本書紀の教育にありました。
他者を恨まず、良きものを共有する精神が、愛と共鳴の文明を生んだのです。
Ⅰ.外国人が3分の1でも文化が花開いた理由
平安文化と聞けば、多くの人が紫式部や清少納言、小野小町を思い浮かべます。
まさに日本史上、最も優雅で、文化と美が爛熟した時代でした。
ところが史料『新撰姓氏録』によれば、この時代の日本の人口の3分の1は、渡来系の家系だったことが明らかになっています。
それでも平安時代が“日本らしさ”を失わず、むしろ輝きを増したのはなぜでしょうか。
それは、当時の日本社会が「日本とはどういう国であるか」という共通の基盤を、明確に持っていたからです。
その基盤こそが、『日本書紀』です。
奈良時代の720年、元正天皇に献上された日本書紀は、翌年から貴族の子女たちの教科書として用いられ、やがて全国的な教育の礎となりました。
この伝統は、実に終戦まで1300年近くも受け継がれました。
日本書紀は、御存知の通り歴史書です。
つまり、我が国における歴史教育には、もともと1300年の実績があったのです。
日本書紀を学ぶことで、人々は自らの国の成り立ち、天皇の存在意義、そして自然災害や争乱を乗り越えてきた歴史を物語として共有しました。
それが「日本人である」という自覚と誇りを形づくり、血筋や制度ではなく、心で「日本人となる」道を、誰もが選び取る社会を生んだのです。
Ⅱ.「愛」によって結ばれた共鳴の文化
平安初期、小野小町のような女流歌人たちは、人を思う心や自然を愛でる心を詠みました。
詩歌に国境はありません。
たとえ異国の血を引いていようとも、「よりよきものを共有し、響き合う」という精神を社会全体で共有したのです。
小野小町の生家・小野氏は秋田の名家で、渤海国との金交易に関わっていたとされます。
彼女は、中東商人と血のつながりを持っていた可能性すらあるのです。
しかし重要なのは血統ではなく、「日本文化に共鳴する心」です。
思ひつつ寝ぬれば人の見えつらむ
夢と知りせばさめざらましを
恋い慕う心を、夢と現のはざまに詠んだこの歌には、
民族や宗教を超えた万国共通のの「愛」が息づいています。
人を愛する心は、友を愛し、家族を愛し、郷里を愛し、国を愛し、世界を愛する力へとつながります。
この「愛の文明」が、平安の日本を文化大国へと導いたのです。
Ⅲ.現代に問われる「日本書紀」の精神
では、現代の日本はどうでしょうか。
外国人がわずか0.1%しかいないにもかかわらず、
「恨み」や「分断」によって国の形が揺らいでいます。
わずかな勢力が、ありもしない歴史のファンタジーを用い、
日本人の心を惑わせています。
それは、戦後の日本が「日本とは何か」という国のアイデンティティを見失ったことに起因します。
歴史教育を失った社会は、歴史伝統文化の精神を失い、見えない力の存在を否定し、他者を恨み、支配と隷属を軸に、制度や政局ばかりを語る風潮が生まれてしまうのです。
だからこそ、いま再び日本書紀の精神が必要です。
日本とは、血ではなく「心」で結ばれる国家だからです。
文化とは、よりよいものを共有し、響き合うための営みです。
恨みからは、文化が生まれず、
軽蔑からは、美が生まれず、
支配からは、平和は生まれません。
平安文化の豊かさは、愛と共鳴の文明を築いた日本人の心の姿にこそあったのです。
【所感】
平安時代の繁栄は、「和」と「共鳴」の結果でした。
その根底にあったのは、『日本書紀』が育んだ国家観と、「よりよいものを共有する」心です。
いま日本に必要なのは、他者を責めることではなく、再び「共に響き合う文化」を取り戻すこと。
愛こそが、国を結び、文明を生かす源です。
そして日本は、その愛の文明を世界に示す使命を持っています。
人でも民族でも国家でも、後ろめたいことがあると、無意識のうちに罪悪感から逃避しようとして、
過剰な理想主義や偽善的な人道主義、暴力による正義の演出に走ります。
罪悪感の処理不全が、社会的行動の過剰化を生むからです。
健全であること――それこそが、人間の、そして文明の成熟なのです。